記録だけ
2009年 128冊目
『観世流謡曲百番集』 から
「神歌」「石橋」「俊寛」「小鍛冶」「高砂」「安達原」「竹生島」「東北」「神歌」
観世左近 著
檜書店
昭和52年4月20日 第1版発行
昭和52年4月30日 第55版発行
『観世流謡曲百番集』 から 「神歌」「石橋」「俊寛」「小鍛冶」「高砂」「安達原」「竹生島」「東北」「神歌」を楽しむ。
本日は「神歌」に始まり、「神歌」に終わる。
最近は無性に舞台が見たい。
歌舞伎が見たい。
能楽が聞きたい。
日本はすばらしい。
日本の伝統芸能はすばらしい。
とにかく、見たい。
なかなか行く機会に恵まれないので、百番集を読む。
声に出したり、へろへろ読んだり、いい加減な事だ。
ところでこの百番集、【百番集】とパソコンのキーボードを打つと【百晩秋】と出てきた。
百晩秋か・・・。
そろそろ秋の夜長、読書には最適かもしれない。
外では秋の虫たちが合掌している。
もう、八月も終わり。
記録のみにて失礼いたします。
















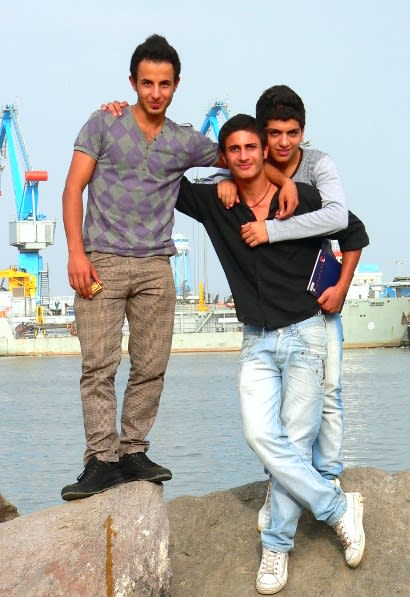











 。
。














