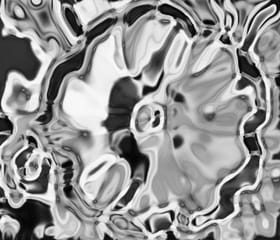ウォーター・ワールド
満足度 ★★★★☆
感動度 ★★☆☆☆
監督 ケヴィン・レイノルズ
1995年 アメリカ 135分
キャスト ケビン・コスナー
デニス・ホッパー
ジャック・ブラック
他
近未来SF映画。
地球温暖化などの理由で環境破壊の末、地球に大洪水が起こる。
陸地は海の底、世界はすっかりと変わり果て、残された少しの廃棄物をつなぎ合わせたような陸状態うをなす船舶で生き残った人は生活していた。
文明と共に漂流を余儀なくされた彼らは海中から引き上げられた既に消滅した世界の残骸から、巨大な人工の浮遊都市を築くことに成功していた。
地球の形態も恐ろしく長い年月の流れとともに、進化した(人間はもともとは魚から進化を遂げたことから考えると、進化という言葉は適当ではないのでしょうけれども、とにかく想像上の)人間ともいえる半漁人(ケビンコスナー)が一人で手作りの船舶にのって海での生活していた。
一方少女の背中には解読不能の地図の刺青。
底を目指せばグリーンランドにたどり着くことができると人々は信じていた。
グリーンランドを巡ってのトラブルや争い、女とケビンコスナー或いは少女とケビンコスナーとの種を超えた命がけの人間愛。
とにかく痛快で面白く、スカッとする満足殿高い映画でした。
この映画でとても気に入った点があります。
色彩も美しいのですが、造形美はなんともいえなく美しい。
新しいブリキなどをしようしているのですが、さび表現や古さ、寄せ集めの美学を見事に表現されており、まるで動くできの良い立体造形をみているようでした。なんだか『ポンピドゥーセンター』の作品を観ているようで、興味深く楽しめました。
衣装も同様、道具がない世界で工夫を凝らし、縫い目はゆがみ、色彩はぼかされてこれがまた美しい。メイクも好きでした。
ていうか・・・・
ケビン・コスナーとデニス・ホッパーがとても素敵でした・・・
満足度 ★★★★☆
感動度 ★★☆☆☆
監督 ケヴィン・レイノルズ
1995年 アメリカ 135分
キャスト ケビン・コスナー
デニス・ホッパー
ジャック・ブラック
他
近未来SF映画。
地球温暖化などの理由で環境破壊の末、地球に大洪水が起こる。
陸地は海の底、世界はすっかりと変わり果て、残された少しの廃棄物をつなぎ合わせたような陸状態うをなす船舶で生き残った人は生活していた。
文明と共に漂流を余儀なくされた彼らは海中から引き上げられた既に消滅した世界の残骸から、巨大な人工の浮遊都市を築くことに成功していた。
地球の形態も恐ろしく長い年月の流れとともに、進化した(人間はもともとは魚から進化を遂げたことから考えると、進化という言葉は適当ではないのでしょうけれども、とにかく想像上の)人間ともいえる半漁人(ケビンコスナー)が一人で手作りの船舶にのって海での生活していた。
一方少女の背中には解読不能の地図の刺青。
底を目指せばグリーンランドにたどり着くことができると人々は信じていた。
グリーンランドを巡ってのトラブルや争い、女とケビンコスナー或いは少女とケビンコスナーとの種を超えた命がけの人間愛。
とにかく痛快で面白く、スカッとする満足殿高い映画でした。
この映画でとても気に入った点があります。
色彩も美しいのですが、造形美はなんともいえなく美しい。
新しいブリキなどをしようしているのですが、さび表現や古さ、寄せ集めの美学を見事に表現されており、まるで動くできの良い立体造形をみているようでした。なんだか『ポンピドゥーセンター』の作品を観ているようで、興味深く楽しめました。
衣装も同様、道具がない世界で工夫を凝らし、縫い目はゆがみ、色彩はぼかされてこれがまた美しい。メイクも好きでした。
ていうか・・・・
ケビン・コスナーとデニス・ホッパーがとても素敵でした・・・