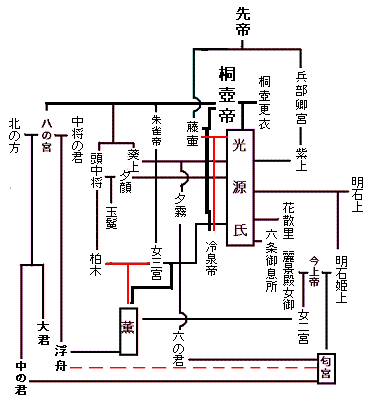2012. 2/9 1067
五十帖 【東屋(あづまや)の巻】 その(38)
「出で給はむことのいとわりなくくちをしきに、人目も思されぬに、右近立ち出でて、この御使を西面にて問へば、申し次ぎつる人も寄り来て」
――(宮は)ここを出ておいでになることが、なんとしても心残りで、今は人目もはばからぬご様子なので、仕方なく右近が立って行って、その御使いを西面に呼び寄せて尋ねますと、お取り次ぎを申した人も側にきて――
「『中務の宮参らせ給ひぬ。大夫は唯今なむ、参りつる道に、御車引き出づる、見侍りつ』と申せば、げににはかに時々なやみ給ふ折り折もあるを、とおぼすに、人のおぼすらむこともはしたなくなりて、いみじううらみ契り起きて出で給ひぬ」
――(その侍が)「中務の宮(匂宮の弟宮)が御所へ明石中宮様のお見舞いに参内されました。中宮の大夫(中宮職の長官)も唯今こちらへ参ります道で、御車を引き出されるのを、お見受けいたしました」と申し上げますと、匂宮は、なるほど中宮は急に時々御病みなさるのを、自分だけ遅参しては、人はどう思うであろうかと恥かしくなられて、くどくどと浮舟に後の逢瀬を約束なさって、ようやくお出かけになりました――
「恐ろしき夢の覚めたる心地して、汗におし浸して臥し給へり。乳母うちあふぎなどして」
――(浮舟は)恐ろしい夢から覚めたような心地がして、汗をびっしょりかいて、うつ臥していらっしゃいます。乳母は扇で煽いで差し上げたりしながら――
「かかる御住ひは、よろづにつけて、つつましうびんなかりけり。かくおはしましそめて、さらによきこと侍らじ。あな恐ろしや。限りなき人ときこゆとも、安からぬ御ありさまは、いとあぢきなかるべし。よそのさし離れたらむ人にこそ、よしともあしとも覚えられ給はめ。人聞きもかたはらいたき事、と思ひ給へて、蝦蟇の相を出だして、つと見奉りつれば、いとむくつけく、下衆々々しき女とおぼして、手をいといたくつませ給ひつるこそ、直人の懸想だちて、いとをかしくも覚え侍りつれ
――こういう御住居は何かにつけて気づまりで、具合悪うございます。このように一度立ち寄られましては、今後も決してよい事はございますまい。ああ恐ろしい。この上ない尊い御方といいましても、こうしたはしたないお振舞いはまことに怪しからぬことになりましょう。よその、縁もゆかりもない人から何とでも思って頂かれる方が余程よろしい。何にしましても、御姉君の背の君ではとんでもなく外聞の悪いことですので、私は蝦蟇(がま)の不動尊のような面相で、じっと睨みつけておりました。匂宮は私をたいそう気味の悪い下衆っぽい女だとお思いになって、私の手をたいそうきつく抓られたのは、なんとまあ、下人の者の色恋めいて、まことに可笑しく思いましたよ――
ところで…、と続けて、
「かの殿には、今日もいみじくいさかひ給ひけり。『ただ一所の御上を見あつかひ給ふとて、わが子どもをばおぼし棄てたり。客人のおはする程の御旅居見ぐるし』と、荒々しきまでぞきこえ給ひける。下人さへ聞きいとほしがりけり。すべてこの少将の君ぞ、いと愛敬なく覚え給ふ。このみこと侍らざらましかば、内々安からずむつかしき事は折り折り侍りとも、なだらかに、年ごろのままにておはしますべきものを」
――常陸の介の邸では、今日もひどく夫婦喧嘩をしておられました。殿が北の方に、「あなたは、ただ浮舟一人のことに心をくだいて、私の娘たちを放っりぱなしにしている。婿殿の御滞在中の外泊は体裁が悪いではないか」と、荒々しくお叱りになるのです。下人までもが、それを聞いて同情しておりました。これもみな、あの新婿君の少将殿のせいで、憎らしい方ですよ。こんなことさえなければ、内輪の気まずいことは時々ございましても、無事に今までのようにお過ごしになれましたものを――
と、溜息をつきながら言います。
◆蝦蟇(がま)の相=不動尊が悪魔を降伏する際に現す忿怒(ふんぬ)の相。
では2/11に。
五十帖 【東屋(あづまや)の巻】 その(38)
「出で給はむことのいとわりなくくちをしきに、人目も思されぬに、右近立ち出でて、この御使を西面にて問へば、申し次ぎつる人も寄り来て」
――(宮は)ここを出ておいでになることが、なんとしても心残りで、今は人目もはばからぬご様子なので、仕方なく右近が立って行って、その御使いを西面に呼び寄せて尋ねますと、お取り次ぎを申した人も側にきて――
「『中務の宮参らせ給ひぬ。大夫は唯今なむ、参りつる道に、御車引き出づる、見侍りつ』と申せば、げににはかに時々なやみ給ふ折り折もあるを、とおぼすに、人のおぼすらむこともはしたなくなりて、いみじううらみ契り起きて出で給ひぬ」
――(その侍が)「中務の宮(匂宮の弟宮)が御所へ明石中宮様のお見舞いに参内されました。中宮の大夫(中宮職の長官)も唯今こちらへ参ります道で、御車を引き出されるのを、お見受けいたしました」と申し上げますと、匂宮は、なるほど中宮は急に時々御病みなさるのを、自分だけ遅参しては、人はどう思うであろうかと恥かしくなられて、くどくどと浮舟に後の逢瀬を約束なさって、ようやくお出かけになりました――
「恐ろしき夢の覚めたる心地して、汗におし浸して臥し給へり。乳母うちあふぎなどして」
――(浮舟は)恐ろしい夢から覚めたような心地がして、汗をびっしょりかいて、うつ臥していらっしゃいます。乳母は扇で煽いで差し上げたりしながら――
「かかる御住ひは、よろづにつけて、つつましうびんなかりけり。かくおはしましそめて、さらによきこと侍らじ。あな恐ろしや。限りなき人ときこゆとも、安からぬ御ありさまは、いとあぢきなかるべし。よそのさし離れたらむ人にこそ、よしともあしとも覚えられ給はめ。人聞きもかたはらいたき事、と思ひ給へて、蝦蟇の相を出だして、つと見奉りつれば、いとむくつけく、下衆々々しき女とおぼして、手をいといたくつませ給ひつるこそ、直人の懸想だちて、いとをかしくも覚え侍りつれ
――こういう御住居は何かにつけて気づまりで、具合悪うございます。このように一度立ち寄られましては、今後も決してよい事はございますまい。ああ恐ろしい。この上ない尊い御方といいましても、こうしたはしたないお振舞いはまことに怪しからぬことになりましょう。よその、縁もゆかりもない人から何とでも思って頂かれる方が余程よろしい。何にしましても、御姉君の背の君ではとんでもなく外聞の悪いことですので、私は蝦蟇(がま)の不動尊のような面相で、じっと睨みつけておりました。匂宮は私をたいそう気味の悪い下衆っぽい女だとお思いになって、私の手をたいそうきつく抓られたのは、なんとまあ、下人の者の色恋めいて、まことに可笑しく思いましたよ――
ところで…、と続けて、
「かの殿には、今日もいみじくいさかひ給ひけり。『ただ一所の御上を見あつかひ給ふとて、わが子どもをばおぼし棄てたり。客人のおはする程の御旅居見ぐるし』と、荒々しきまでぞきこえ給ひける。下人さへ聞きいとほしがりけり。すべてこの少将の君ぞ、いと愛敬なく覚え給ふ。このみこと侍らざらましかば、内々安からずむつかしき事は折り折り侍りとも、なだらかに、年ごろのままにておはしますべきものを」
――常陸の介の邸では、今日もひどく夫婦喧嘩をしておられました。殿が北の方に、「あなたは、ただ浮舟一人のことに心をくだいて、私の娘たちを放っりぱなしにしている。婿殿の御滞在中の外泊は体裁が悪いではないか」と、荒々しくお叱りになるのです。下人までもが、それを聞いて同情しておりました。これもみな、あの新婿君の少将殿のせいで、憎らしい方ですよ。こんなことさえなければ、内輪の気まずいことは時々ございましても、無事に今までのようにお過ごしになれましたものを――
と、溜息をつきながら言います。
◆蝦蟇(がま)の相=不動尊が悪魔を降伏する際に現す忿怒(ふんぬ)の相。
では2/11に。