コメント(私見):
今回の症例は子宮後壁の癒着胎盤とのことですから、帝王切開の既往とも関係ありませんし、癒着胎盤と手術前に診断することも予測することも不可能だったと考えられます。極めてまれで予測不能な難治疾患と遭遇して、救命を目的に必死の思いで正当な医療行為を実施しても、結果的にその患者さんを救命できなかった場合に、今回のように極悪非道の殺人犯と全く同じ扱いで逮捕・起訴されるようでは、危なくて誰もリスクを伴う医療には従事できなくなってしまいます。
また、県の医療事故調査委員会の報告書は県の意向に沿って作成されたもので、佐藤教授が県に訂正を求めたが、「こう書かないと賠償金は出ない」との理由で却下されたとのことです。そもそも、正当な医療行為に対して、「医療過誤があったということにして賠償金を出させよう」という考え方が根本的におかしいし、そのために一人の医師の人生がめちゃくちゃにされ、日本の産科医療全体を崩壊の方向に加速させたこの事件の意味するところは非常に重大です。
以前より、我が国では「産婦人科医一人体制」の施設が多いことが問題視されてきました。その解決策の一つとされていたのが分娩施設の集約化です。本事件以降は、全国的に「産婦人科医一人体制」などのマンパワーの不十分な施設は次々に閉鎖に追い込まれています。結果的に、本事件は我が国の周産期医療体制の再編が始まる契機になったことも確かだと思います。
周産期医療に従事している限り、癒着胎盤にいつ遭遇するかは全くわかりません。そして、いざ癒着胎盤に遭遇した時には、本事件の担当医師と全く同じ対応をしなければならない立場にいるわけですから、多くの産婦人科医が「とてもじゃないがやってられない」という気持ちになって辞職しました。今度の判決次第では、現在まだ現場に何とか踏みとどまっている産婦人科医の中からも大量の離職者が出るかもしれません。
****** m3.com医療維新、2008年8月15日
福島県立大野病院事件◆Vol.13
延べ80時間、加藤医師本人を含め15人が法廷に
計14回に及んだ公判を振り返る(1)
来週8月20日、福島地裁で福島県立大野病院事件の判決が言い渡される。本事件は、2004年12月17日、帝王切開手術時に女性が死亡したもので、同病院の産婦人科医だった加藤克彦医師が業務上過失致死罪と、異状死の届け出を定めた医師法21条違反に問われていた事件だ。検察側は、業務上過失致死罪で禁固1年、医師法21違反で罰金10万円をそれぞれ求刑した。
これに対して弁護側はあくまで無罪を主張している。
2006年2月18日の加藤医師の逮捕により、産婦人科関係者だけではなく、医療界全体に大きな衝撃が走った。その後、各学会・医療団体が抗議の声明を出したことは、まだ記憶に新しいところだ。医療事故が刑事事件に発展することへの懸念が、今に至る“医療崩壊”につながっている。
2007年1月26日から、2008年5月16日の最終弁論まで、計14回の公判を傍聴した立場から、その経過を振り返ってみる。各公判は、以下の日時で開催された。
【福島県立大野病院事件の公判経過】 (時間は概算)
第1回公判(2007年1月26日)
・午前10時~午後4時(途中休憩は約1時間)
・一般傍聴席26席/傍聴席を求めて並んだ人(以下、行列者)349人
・起訴状朗読、冒頭陳述(検察側、加藤医師)、加藤医師への尋問
第2回公判(2007年2月23日)
・午前10時~午後4時半(途中休憩は約50分)
・一般傍聴席23席/行列者120人
・検察側証人尋問:緊急時に備え応援要請していた双葉厚生病院の産婦人科医と、本件で手術助手を務めた外科医
第3回公判(2007年3月16日)
・午前10時~午後6時10分(途中休憩は1時間強)
・一般傍聴席23席/行列者119人
・検察側証人尋問:本件の手術に携わった助産師と麻酔科医
第4回公判(2007年4月27日)
・午前10時~午後4時半(途中休憩は約1時間強)
・一般傍聴席23席/行列者78人
・検察側証人尋問:本件の手術に携わった看護師、大野病院の院長
第5回公判(2007年5月25日)
・午前10時~午後6時(途中休憩は1時間強)
・一般傍聴席23席/行列者84人
・検察側証人尋問:鑑定医(患者の死亡直後の病理検査や鑑定などを実施した病理医)
第6回公判(2007年7月20日)
・午前10時~午後4時半(途中休憩は約1時間15分)
・一般傍聴席15席/行列者90人
・検察側証人尋問:鑑定医(検察側の鑑定を実施した産婦人科医)
第7回公判(2007年8月31日)
・午前9時半~午後7時(途中休憩は約1時間40分)
・一般傍聴席15席/行列者121人
・弁護側証人尋問:加藤医師
第8回公判(2007年9月28日)
・午前10時20分~午後7時半(途中休憩は約1時間30分)
・一般傍聴席27席/行列者66人
・弁護側証人尋問:胎盤病理を専門とする医師
第9回公判(2007年10月26日)
・午前10時~午後4時20分(途中休憩は約1時間30分)
・一般傍聴席27席/行列者63人
・弁護側証人尋問:周産期医療の第一人者
第10回公判(2007年11月30日)
・午前9時30分~午後4時(途中休憩は約1時間25分)
・一般傍聴席27席/行列者54人
・弁護側証人尋問:周産期医療の第一人者
第11回公判(2007年12月21日)
・午前10時~午後3時(途中休憩は約1時間)
・一般傍聴席25席/行列者63人
・加藤医師本人への尋問
第12回公判(2008年1月25日)
・午前11時~午後2時すぎ(途中休憩は1時間10分)
・一般傍聴席25席/行列者64人
・死亡した女性の夫、父親、弟の意見陳述
第13回公判(2008年3月21日)
・午後1時30分~午後6時20分(途中休憩は10分)
・一般傍聴席27席/行列者171人
・論告求刑
第14回公判(2008年5月16日)
・午前10時~午後4時40分(途中休憩は約1時間20分)
・一般傍聴席27席/行列者162人
・最終弁論
以上のように、証人尋問を受けたのは、11人。そのほか、加藤医師本人、遺族3人、計15人が法廷に立った。11人の内訳は、本件の手術の関係者、鑑定人、周産期医療や胎盤病理の専門家。加藤医師は医師法21条違反に問われているが、弁護側が同条に詳しい法学者の証人尋問を求めたが、認められなかった。
公判の時間は、計約80時間に及んだ。最も長かったのは、加藤医師への尋問が行われた、昨年8月の第7回公判だ。また、第13回の論告求刑で検察側が読み上げた「論告要旨」は160ページ超、第14回の「弁論要旨」は157ページに及ぶものだった。
本裁判は、3人の裁判官が担当しているが、昨年4月には裁判長が、また今年4月には右陪席(中央に座る裁判長から見て右)の裁判官がそれぞれ交代している。一方、検察側も昨年春と今年春に何人か入れ替わっている。
橋本佳子(m3.com編集長)
(m3.com医療維新、2008年8月15日)
****** m3.com医療維新、2008年8月18日
福島県立大野病院事件◆Vol.14
検察側、弁護側の主張は最後まで平行線のまま
計14回に及んだ公判を振り返る(2)
「昨年1月の初公判における冒頭陳述をもう一回聞いたようなもの」。
今年3月の論告求刑時、計14回の公判を継続して傍聴していた、ある医師が思わずこうもらした。
検察側、加藤医師・弁護側、遺族の、それぞれの主張や事件への思いなどは、最後まで変わらなかった――。これが、2007年1月以降、計14回に及んだ、福島県立大野病院事件の公判を傍聴した感想だ。
死亡した女性は、帝王切開手術の既往がある前置胎盤の女性で、2004年12月17日、帝王切開手術時に出血を来し、死亡した。被告の加藤克彦医師は、業務上過失致死罪と医師法21条違反に問われている。
検察は初公判時、業務上過失致死罪については、(1)帝王切開手術前の検査時、遅くても胎盤と子宮を用手的に剥離する際に、癒着胎盤であることを認識し、大量出血の危険を予見できた、(2)用手的剥離が困難になった時点で剥離を中止して、子宮摘出術に切り替える義務があったが、それを怠り、大量出血を招いた、(3)死因は出血死であり、加藤医師の行為との因果関係がある――などと主張した。また、医師法21条違反については、異状死の届け出を怠ったとしている。この検察の主張は論告求刑時も変わっていない。
一方、弁護側は、これらを否定し、一貫して加藤医師の無罪を主張している。また、加藤医師は、初公判時、起訴事実を否定したが、「忸怩(じくじ)たる思いがあり、(死亡した女性の)ご冥福を心からお祈りします」と述べた。その後の証人尋問や今年5月の最終弁論時にも同様に、遺族へのお悔やみの言葉を繰り返し述べている。
一般的に刑事裁判では、公権力による捜査が行われることから、民事裁判と比べて、「いったい何があったのか、その真実が明らかになる」と考えられているが、今回の場合は当てはまらないようだ。遺族は、計14回の公判を傍聴し、約80時間に及んだ検察、弁護側のやり取りを聞いていた。それでもなお、「真実が明らかになった」とは受け止めておらず、加藤医師の責任追及を求める気持ちは変わっていない。
「剥離を中断し子宮摘出術に切り替えるべきだったか」が最大の争点
公判では、証人尋問を受けた医師が、加藤医師の起訴前の事情聴取時などとは異なる発言をする場面が何度か見られた。しかし、検察側の主張は変わることはなく、弁護側の主張とは平行線をたどったままだった。
裁判の最大の争点は、前述の(2)の「癒着胎盤であることを認識した場合、胎盤剥離を中止して、子宮摘出術に切り替える義務があったか否か」という点だ。
この争点を因数分解すれば、(1)子宮摘出術に切り替えることができたか、(2)子宮摘出術に切り替えれば、大量出血を防ぐことが可能だったか、(3)胎盤剥離を完遂したことが大量出血をもたらしたのか、(4)大量出血と死亡との間には因果関係があるのか――ということになる。
以下が、検察側、弁護側それぞれの主張だ。
【検察側の主張】
(2008年3月21日の論告求刑)
(1)について
手術時の女性の体位は子宮摘出術が容易な「砕石位」であり、女性の全身状態など、医学的観点から子宮摘出術が可能な状況にあり、術前の説明で「内容は不十分ながらも手術の危険性を説明し、子宮摘出術の同意を得ていた」などと主張。
(2)について
用手的剥離できない癒着胎盤をクーパーで無理に剥離したために、子宮内壁の動脈が子宮内壁に向けて開放された状態になり、子宮後壁下部からの出血が急増したと主張。
(3)について
胎盤娩出(午後2時50分)後の午後2時55分ころまでの総出血量は、5000mLに達していた。
(4)について
死因は、胎盤剥離を無理に継続したことによる大量出血であり、加藤医師の胎盤剥離行為と死亡との間には因果関係がある。
検察側が依拠した証拠
本件手術の麻酔記録、医学書類、病理鑑定医(第5回公判で証人尋問を受けた病理医)、検察側鑑定医(第6回公判で証人尋問を受けた婦人科腫瘍の専門家)など(弁護側の証人の意見については、「日本産婦人科学会などが本事件への抗議声明を出している状況下では、中立性・正確性に疑問がある」などとしている)。
【弁護側の主張】
(2008年5月16日の最終弁論)
(1)(2)について
胎盤剥離を完遂すれば子宮収縮により止血が期待できる、剥離を中断しても出血は止まらない、剥離を完遂した方が子宮を摘出しやすいことなどから、「胎盤剥離をいったん開始したら完遂するのが、わが国の臨床医学の実践における医療水準」であり、加藤医師の行為は「医学的な合理性がある」と主張。
(3)について
胎盤胎盤娩出(午後2時50分)後の午後2時52~53分ころまでの総出血量は、2555mLであり、胎盤剥離中の出血は最大でも555mL。
(4)について
死亡原因として羊水塞栓の可能性があり、出血の原因として産科DICの発症が考えられ、大量出血と死亡との因果関係には疑問の余地がある。
弁護側が依拠した証拠
麻酔記録、医学書類(検察の医学書の解釈は、「誤解もしくは曲解」していると主張)、弁護側証人(胎盤病理や周産期医療の第一人者=第8回、9回、10回の公判で証人尋問を受けた医師。検察側の病理鑑定医などと比較して、経験・実績から極めて信頼性・信用性が高いと主張)。
胎盤剥離時の出血量という「数字」も一致せず
加藤医師の医療行為の妥当性はもちろん、(3)の出血量という一見客観的に把握できる数字ですら、検察側と弁護側の主張は一致していない。(3)の客観的証拠として、「麻酔記録」に記載されているのは、「午後2時52~53分ころまでの総出血量は、2555mL」という事実のみ。しかし、検察は「出血があった時期と出血量が麻酔記録に記載された時期との間に間隔が生じることが避けられないこと」「輸血用製剤を手術室に持っていった助産師が『5000mL出てます』と聞いたこと」「加藤医師が、当日夜記載した記録で、『この辺りでbleeding 5000mLぐらいか』と記載したこと」などを指摘し、「胎盤剥離後までに5000mLの大量出血があった」と主張している。
要は、依拠する証拠およびその解釈によって、主張が異なるのである。果たして裁判所は、いかなる証拠の信憑性を重んじ、判断するのだろうか。
(m3.com医療維新、2008年8月18日)
****** m3.com医療維新、2008年8月18日
福島県立大野病院事件◆Vol.15
大野病院事件をめぐる5つの誤解・疑問を考察
計14回に及んだ公判を振り返る(3)
2006年2月18日の加藤克彦医師の逮捕、翌3月10日の起訴、そして2007年1月26日の初公判以降、福島県立大野病院事件は一般紙やテレビをはじめ、様々なメディアで取り上げられてきた。ネット時代にあって、各種情報が瞬時に伝わり、事件に関する議論が深まった一方で、中には事実とは異なる解釈がされているケースもある。さらに、計14回にわたった公判を傍聴し、疑問に思う部分もあった。今回はこれらについて考察してみる。
その1●「加藤医師の逮捕は、医師法21条がきっかけではない」
「福島県立大野病院事件の発端は、医師法21条に基づき、異状死の届け出をしなかったことにある」との見方が医療界にある。
確かに、加藤医師は、業務上過失致死罪に加えて、医師法21条違反でも起訴されている。しかし、加藤医師の捜査の発端となったのは、2005年3月22日に「県立大野病院医療事故調査委員会」がまとめた、「県立大野病院医療事故について」と題する報告書だ。ここに、
「出血は子宮摘出に進むべきところを、癒着胎盤を剥離し止血に進んだためである。胎盤剥離操作は十分な血液の到着を待ってから行うべきであった」
などと、加藤医師に過失があったと受け取られかねない記載がある。しかし、報告書は医師法21条に基づく届け出には言及していない。つまり、業務上過失致死容疑で捜査が開始されたのであり、医師法21条違反はその捜査の過程で浮上したものと見るのが妥当だ。
2007年6月27日に開催された、厚生労働省の「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会」で、警察庁刑事局刑事企画課長はこう述べている(下記は、当日の議事録から引用)。
「(平成9年以降、ここ10年間で)医師法21条に基づいて届け出なかったから事件になったというのは7件ありますが、これはすべていわゆる業務上過失致死が付いています。どちらかというと医師法21条は変な言い方ですが、当然過失致死等で立件にふさわしい案件に合わせて、21条の届出がなされていなかったから立件しているのだということで、届け出なかったゆえに、そのことをもって立件しているという21条だけのケースは1件もありません」
つまり、「医師法21条違反だけで立件することはない」と述べているのである。確かに、今の医師法21条をめぐっては様々な問題があり、今の“医療事故調”をめぐる議論に発展している。しかし、医師法21条だけを改正しても問題は解決しない。同時並行的に、「どんな医療行為に対して業務上過失致死罪を適用するか」、この点を議論しないと、医療事故が刑事事件に発展する懸念は払拭できず、“医療崩壊”を食い止めることもできない。
その2●「なぜ公判で医師法21条について、ほとんど議論されなかったか」
前述のように、加藤医師は医師法21条違反で起訴されている。しかし、加藤医師本人と、大野病院の院長がそれぞれ当時の様子を語り、また弁護団が最終弁論で医師法21条違反はないことを主張した以外は、ほとんど21条が取り上げられることがなかった。
医師法21条をめぐっては、1994年が日本法医学会がガイドラインを出して以降、各学会、さらには厚生労働省が解釈を出しているが、見解は一致しておらず、医療現場に混乱が生じている。加藤医師の弁護団は、医師法21条に詳しい法学者の証人尋問を求めたものの、理由は不明だが、認められなかった。このため、弁護団はこの法学者の「意見書」の形で証拠提出しているが、証拠採用されていない。
その3●「なぜ院内事故調査報告は証拠採用されなかったか」
「その1」で言及した通り、加藤医師の逮捕は、2005年3月の「県立大野病院医療事故調査委員会」の報告書が発端となっている。この延長線上で考えれば、検察側は、この報告書の証拠採用を求めるはずだが、実際にはされていない。
この報告書は、本文部分4ページ(A4判)に、表紙と目次、「用語集」が付いた体裁で、計3回の議論を経てまとめられている。
注目すべきは、「今回の事例は、前1回帝王切開、後璧付着の前置胎盤であった妊婦が…」としている点だ。この点が検察の主張と、実は異なる。「後壁付着」の場合、「前壁付着」と比べて、子宮と胎盤が癒着(癒着胎盤)しているかを、帝王切開手術前の検査などで診断するのは難しい。検察は「前壁」に癒着があったと主張し、術前、遅くても用手的剥離をした時点で癒着胎盤の予見が可能だったとしている。
なお、福島県立医科大学産婦人科教授の佐藤章氏は以前、「この報告書を見たとき、ミスがあったと受け取られかねない記載があるため、表現の訂正を求めたが、県は認めなかった」と語っている。この報告書は、示談金を支払うことを想定してまとめられたものとされ、医療側に問題がある内容でないと、示談金の支払いに支障が出ると県は判断したものと思われる。
その4●「加藤医師は、外来患者さんの前で逮捕されたのではない」
「加藤医師は外来診療中に逮捕された」と解釈している人がいるが、実際にはそうではない。加藤医師が逮捕・起訴以降、公の場でコメントしたのは、初公判の直後に開かれた記者会見の席上のみだが、ここで本人自身がこの点を否定している。
2005年3月の「県立大野病院医療事故調査委員会」の報告書以降、加藤医師は数回、警察に事情を聞かれていた。2006年2月18日の逮捕当日の3~4日前に、警察から家宅捜索に入る旨の連絡があった。当日、家宅捜索後、「警察で話を聞く」と言われ、加藤医師は警察署に同行した。警察署の取調室に入った後、突然、逮捕状が読み上げられたという。
「逮捕」は、証拠隠滅や海外逃亡の恐れなどがある場合に行われるのが一般的。今回の場合、既にカルテなどは押収され、加藤医師は数回取り調べを受けていた。書類送検ではなく、なぜ「逮捕」されたのかを疑問視する向きは多い。
その5●「遺族は告訴していない」
近年、「医療事故に遭った遺族が警察に訴える」というケースが見られる。しかし、大野病院事件の場合は、前述のように、警察の捜査の発端は、「県立大野病院医療事故調査委員会」の報告書であり、遺族が告訴したわけではない。なお、遺族への示談金は、現時点ではまだ支払われてない。
もっとも、帝王切開手術で死亡した女性の遺族が、今回の経過に納得しているわけではない。今年1月25日に開催された第12回公判で、女性の夫、父親、弟がそれぞれ意見を述べた。警察や検察に対する感謝の意を述べた上で、加藤医師の責任追及、事故の真相究明を求めている。
(m3.com医療維新、2008年8月18日)










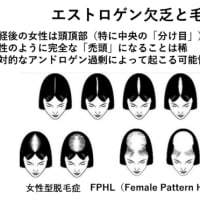


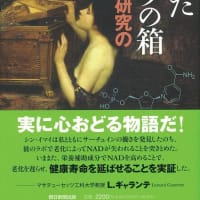
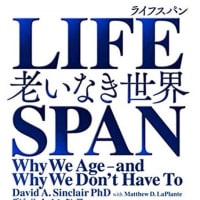
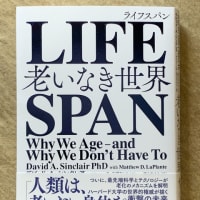
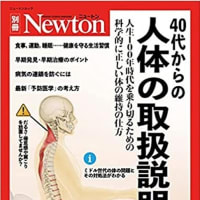
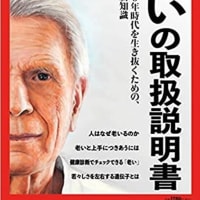
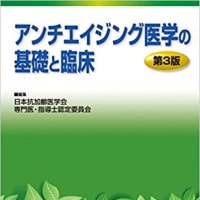

私が医学生の頃、産婦人科を選ぶと産科の親しい先生に言ったら、「物好きな。大変だよ」と厳しい意見を言われた。そのときは、せっかく自分と同じ道を選ぶ後輩をなぜ応援してくれないのだろうと思ったけれど、今思うと、本当に心配してくれていたのだと思う。
今、産科医不足が叫ばれ、産婦人科を選ぶ研修医もふえはじめているような気がする。
彼らの純粋な心は嬉しいが、でも私も、彼らに「本当にいいの?」といいたい。
今日も当直明けでぼろぼろです。
卒後6年目、これからという時期の産婦人科医の正直な意見。
都内勤務産婦人科医さんのご意見にまったく同意です。後輩に産婦人科(特に産科)を勧められる点は現時点でまったくありません。どうしてもやりたい方は止めませんし、むしろ大歓迎ですが、「物好きな。大変だよ」という厳しい意見は本当に親切な意見と思われます。
よほど有利な事(訴訟の免責など)を強引にでも作らないと、なり手の増加は望めないでしょう。
これを機に、日本の医療が良くなれば良いのですが。
私も、福島に行きます。
今、お産をとる人が少なくなって(男性の先輩や同僚、後輩でここ数年開業した方々は、お産をとらないクリニック開業ばかりです。、お産をとる医者が欲しいと思う気持ちは私も同じですが、だからと言って「女医はわがまま」という話をここで繰り広げるのはおかしい。
誰もが、自分の理想どおりの勤務形態や勤務内容を追求する権利があると思います。
医師数は増加していると言いますが、女性医師の急激な増加を考えると実働数はむしろ減っていると思います。国がもっと大胆な医師増加策を早急にとらなければいけないとも思います。