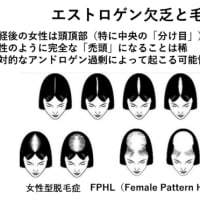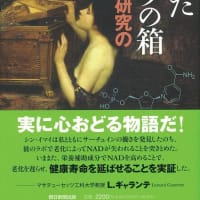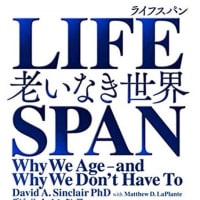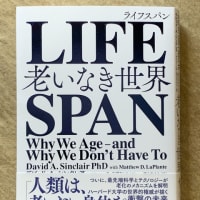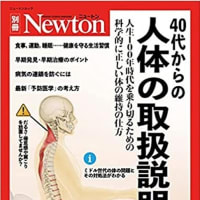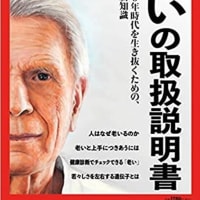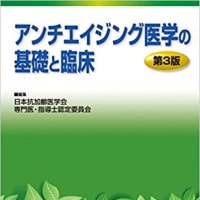私が勤務している病院は現在分娩を取り扱ってますが、5名の産婦人科医が交代で当直をして、当直の翌日も通常の勤務体制で、土日休日は当直医に加えて1名の拘束医を決めてます。当直でない日の緊急呼び出しも少なくありません。結局、フリーの休日はほとんどなく、年がら年中だらだらと病院に縛り付けられているような勤務体制で、子育て期間中もろくに子供達と触れ合う時間が取れず、家族旅行もほとんどできないうちに、いつの間にか子供達は大きくなって全員巣立ってました。最近では、どこの大学でも産婦人科の新入医局員は女性医師が大半を占めるようになって、今のこの過酷な勤務環境のままでは到底長続きする筈がありません。この業界の延命生き残り対策として、分娩取り扱い病院の集約化・大規模化を強力に推進して、持続可能な無理のない勤務環境に変えていく必要が(絶対に)あります。
****** 以下、m3.comの記事より引用
医師不足への処方せん
分娩取扱、1100病院から600病院の時代へ
産科婦人科学会、勤務改善に向け集約化を来年提言
日本産科婦人科学会の医療改革委員会委員長の海野信也氏(北里大学病院長)は、6月21日に開催された同学会総会フォーラム「わが国の周産期医療の持続的発展のため産婦人科の抜本的改善を目指す」で、来年策定予定の「産婦人科医療改革グランドデザイン2015」で、分娩を取り扱う病院を現在の約1100施設から、約600施設に減少させる方針を打ち出す予定であることを明らかにした。産婦人科勤務医の勤務環境改善に向け、分娩取り扱い病院の集約化・大規模化と交代勤務制を推進するのが狙い。海野氏は、「政策提言も必要だが、我々としてできることに取り組んでいく」と説明した。
(中略)
日本産科婦人科医会の調査によると、2013年度の分娩取扱病院の産婦人科医の1カ月当たりの平均当直回数は5.6回で、他科より多い。また1カ月当たりの在院時間は減少傾向にあるが、2013年度は296時間で、過労死認定基準を超える。海野氏は、「分娩取扱病院当たりの医師数は少しずつ増えているが、当直回数や在院時間はそれほど減っていない」と説明、女性医師数が約4割を占め、その半数が妊娠・育児中で、当直できる人に負担が偏る傾向にあるとし、その解消のためにも集約化・大規模化と交代勤務制の導入が必要だとした。
厚生労働省の医療施設調査によると、分娩取り扱い病院は、1999年には2072施設だったが、2002年1803施設、2005年1612施設、2008年1441施設、2011年1357施設と、一貫して減少している。「分娩取り扱い病院は約600」は、総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センター、大学病院を合計すると約400施設あり、それ以外に約200施設が加わるイメージだという。
(後略)