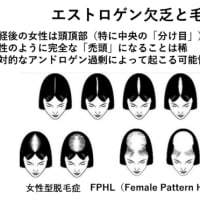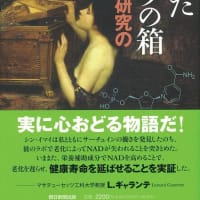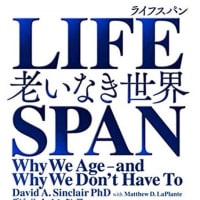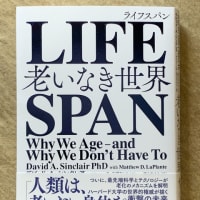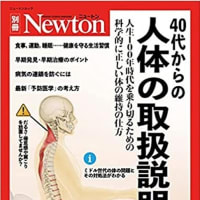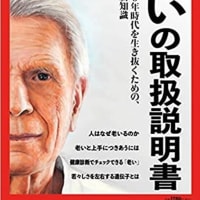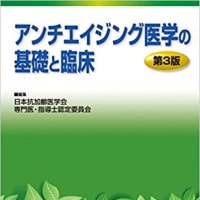****** 毎日新聞、奈良、2008年10月1日
県立三室病院:医師確保めど立たず、お産新規受け付け停止--三郷
県立三室病院(三郷町)が8月から、新規のお産の受け付けを停止していることが分かった。来年4月以降の医師確保にめどがたたないためで、4月以降、産科が休止となる可能性もある。県内では県立五條病院(五條市)も06年4月から産科を休止したまま。人口当たり産婦人科医師数が全国最低水準という深刻な医師不足が、地域の医療拠点の県立病院にまで影を落としている。
三室病院の年間分娩(ぶんべん)数は約200件。同病院や県によると、産科常勤医2人のうち、50代の1人が勤務の過酷さなどを理由に来年3月で退職の意向。常勤医1人での産科継続は困難なため、来年4月以降に出産予定を迎える新規のお産の受け付けを、8月中旬から停止している。
医師は昨年度も退職の意向を示して県などが今年度まで慰留した経緯があり、更に引き延ばすのは難しい状況。病院では、民間診療所の医師を招いて診療してもらう方式も検討し、近隣の医師らに打診したが、協力は得られなかった。県医療管理課は「産科継続に向け、最大限の努力をしている」とするが、人材獲得の見通しは立っていない。
厚生労働省の調査(06年12月時点)によると、15~49歳の女性10万人当たりの産科・産婦人科医師数は、奈良県は31・9人で全国43位。県内では昨年以降、大淀町立大淀病院(大淀町)が産科を休止。済生会中和病院(桜井市)でも分娩の取り扱いをやめている。【中村敦茂】
(毎日新聞、奈良、2008年10月1日)
****** 毎日新聞、奈良、2008年8月9日
妊婦転送死亡:発生2年 産科医療改善まだ途上、医師や看護師不足に課題
一昨年8月の大淀町立大淀病院(大淀町)の妊婦死亡問題を受け、県内ではこの2年、周産期(出産前後の母子双方にとって注意を要する時期)医療の改善が加速した。しかし、昨年8月には橿原市の妊婦が搬送中に死産した。医師や看護師不足を中心に残る課題も多く、体制整備はまだ途上だ。
今年5月26日には、高度な母子医療を提供する総合周産期母子医療センターが、県内最大の医療拠点である県立医大付属病院(橿原市)に開設された。都道府県で45番目の遅い出発だったが、同病院の母体・胎児集中治療管理室(MFICU)は3床から18床に増えた。新生児集中治療室(NICU)は21床から31床になった。県立奈良病院(奈良市)でも、NICU6床の増設計画が進んでいる。
勤務医の待遇改善にも手が打たれた。県は今年度当初予算で県立病院と県立医大付属病院の医師給与引き上げや分娩(ぶんべん)手当の新設などに2億9200万円を計上。「全国最低レベル」とされた給与水準は改善し、年間給与は産科医で約200万円、医師平均で約100万円上昇。県は過酷勤務による離職防止や欠員補充の難しさの緩和を期待する。
県は今年2月、勤務医の少なさをカバーするため、産婦人科の夜間・休日の1次救急に、開業医らが協力する輪番制も導入。4月には参加する開業医を増やして拡充し、一定の成果を出している。出産リスクが高くなる妊婦健診の未受診者を減らそうと、今年4月から妊娠判定の公費負担制度も始めるなど、他にも多くの策を講じてきた。
それでもなお、厳しさは続いているのが現状だ。荒井正吾知事は周産期センター開設に際し、「難しいお産も含め、県内で対応できる態勢がほぼできあがった」と語った。しかし、それはフル稼働が実現すればの話。
センターでは看護師約20人が不足し、NICUのうち9床は開設時から使えていない。このため実際のNICU運用は22床で、従来より1床増えただけ。受け入れ不能の主な要因となってきたNICU不足の実態に大きな変化はなく、大阪など県外へ妊婦を運ばざるを得ない状況は続いているという。
待遇改善で、すぐに医師不足が解消したわけでもない。昨年4月に産科を休診した大淀病院の再開のめどは今も立たない。県立三室病院(三郷町)でも、来年4月以降の産科医確保の見通しが立たず、今月中には新規のお産受け付けを停止する可能性が出ている。
この2年間で実現した改善は少なくないが、医師や看護師不足など、容易でない重要課題に解決の道筋はついていない。県などは、今年度設置した地域医療対策の協議会の議論で、現状打開に向けた模索を続けている。【中村敦茂】
(毎日新聞、奈良、2008年8月9日)
****** 長野日報、2008年10月4日
富士見高原病院 分娩の再開困難に
富士見町の県厚生連・富士見高原病院(井上憲昭院長)は、2009年4月からの分娩取り扱い再開を目指し、準備を進めてきたが、再開は困難な状況であることが3日、明らかになった。昨年3月に着任した産婦人科の深井宣子医師(52)が年度内に退職するためで、新たな産婦人科医の確保に向けた努力を継続するが、全国的な医師不足のため、めどは立っていない。
深井医師は取材に対し、茅野市の諏訪中央病院が6月から産婦人科を再開し、お産の「受け入れ態勢が整ったことが大きな要因」と退職の理由を説明。諏訪中央病院が茅野、富士見、原の3市町村をカバーすることで、富士見高原病院の医師として分娩を再開する「役目は終わった」と判断したという。産婦人科医の常勤2人態勢への「ハードルは高すぎた」とも語った。
常勤は12月末だが、来年3月末までは婦人科の外来診療をこれまで通り週4日担当する。井上院長は、4月以降の婦人科外来について「継続できるよう努力する」とし、山梨大学、信州大学の医学部と周辺の病院に対し、パート医師の派遣などの支援を求めている。
富士見高原病院は04年8月に産婦人科の常勤医師が開業に伴い退職。医師の確保ができず、分娩の取り扱いを中止してきた。05年5月には小児科の常勤医師も退職した。深井医師は昨年3月に着任し、4月から婦人科外来を再開。今年4月には小児科の常勤医師2人が着任し、再開に向けた準備は整いつつあった。
同病院は、産婦人科医が1人体制のため、急患に対応できるよう、病院内に医師の居住施設を確保。当時は町所有だった医局棟の2階を居住施設に改修した。事業費2200万円の半分は町が地域医療推進事業として補助した経過がある。
(長野日報、2008年10月4日)
****** 毎日新聞、愛知、2008年9月30日
医師不足:県内全病院の2割、診療制限 産婦人科3割、分娩の休止など
県内の全病院のうち医師不足を理由に診療制限をしている病院は約2割に上ることが県の調査で分かった。特に産婦人科は約3割で分娩(ぶんべん)の対応などを休止しており、深刻な医師不足の実態が改めて浮き彫りになった。【月足寛樹】
◇昨年度比5カ所増
県が社団法人・県病院協会の協力を得て6月末時点で334カ所の病院を調査した。入院の制限や診療日数の短縮、初診患者の受け入れ制限などの診療制限を実施している病院は67カ所あり、初めて調査した昨年度より5カ所増えた。
うち、診療科の全面休止や分娩対応の休止など特に深刻な状況にあると回答した病院は昨年度より6カ所増えて39カ所に上った。内訳は▽入院診療の休止が18カ所▽診療科の全面休止が17カ所▽時間外救急患者の受け入れ制限が16カ所▽分娩対応の休止が10カ所だった(重複回答含む)。
診療科別で診療制限を実施している病院の割合は、産婦人科が27・1%で最も高く、以下▽小児科11・7%▽精神科10・7%▽内科9・9%--と続く。地域別で診療制限をしている病院の割合が最も高かったのは尾張西部(一宮、稲沢)の30・0%で、以下▽尾張北部(春日井、小牧、犬山市など)25・0%▽西三河南部(岡崎、碧南、刈谷市など)21・6%▽東三河南部(豊橋、豊川、蒲郡市など)21・1%。
(毎日新聞、愛知、2008年9月30日)
****** 中日新聞、2008年10月3日
65%が「診療に制限」 中部9県自治体病院に本紙アンケート
中部9県(愛知、岐阜、三重、長野、静岡、富山、石川、福井、滋賀)の自治体病院の65%が、診療科の休止や手術数の制限など、診療体制を何らかの形で縮小・制限していることが、中日新聞社のアンケートで分かった。雇用している常勤医の総数は、必要とする数の83%にとどまり、ほとんどの病院が医師不足に悩んでいる現状が浮かび上がった。
アンケートは県立、市町村立などの182病院を対象に先月行い、57%にあたる104病院から有効な回答を得た。最近5年間に何らかの診療縮小・制限をしたことがあった病院は72病院。このうち68病院で、現在も制限が続いていた。
診療科を閉鎖・廃止したのは10病院、中止・休止が続いているのは32病院あった。また手術数の制限は16▽分娩数の制限6▽外来診療の制限46▽入院の制限26-の病院が続けていた。
各病院が必要としている常勤医は計4855人だったが、実際に雇用している常勤医は計4054人で、801人足りなかった。必要な常勤医の総数に対し、麻酔科と神経内科は66%、眼科は67%、病理部門は70%しか常勤医がおらず、医師離れが著しい産婦人科の71%を下回って全診療科に医師不足が広がっている現状が浮かび上がった。
医師が足りない理由(複数回答可)では、「大学病院の医局に医師を引き揚げられた」が最も多く、記入した83病院のうち55病院(66%)が理由に挙げた。次いで「定年前に開業して医師が辞めた」「診療体制の強化や医療の質の向上のためにはさらに医師が必要」が、ともに48病院(57%)で続いた。
研修医を受け入れている病院で、研修医を「診療体制上、戦力として不可欠」と位置付けている病院は76%を占めた。
(中日新聞、2008年10月3日)