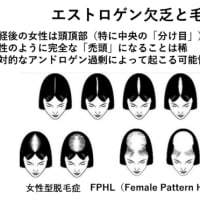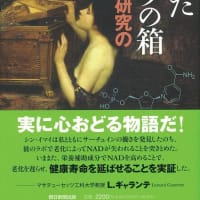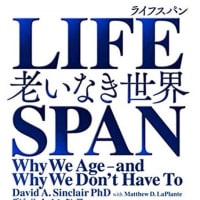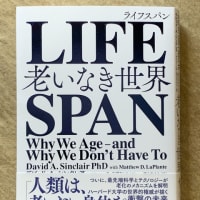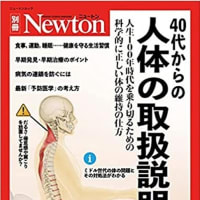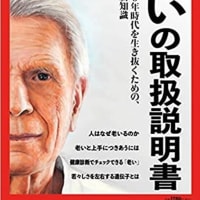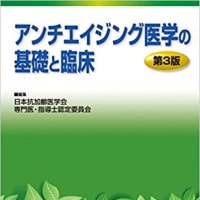はじめに
通常行われる細胞診は、対象から採取された検体をスライドグラス上に塗抹後、固定、染色、鏡検して、細胞を形態学的に診断する病理形態学的診断のひとつである。細胞診の検体は、病変との対応のあり方により大きくふたつに分けられる。
ひとつは、腹腔内の病変由来の細胞を含む腹水や、腹腔→卵管→子宮腔→子宮頸部→腟の病変由来の細胞を含みうる後腟円蓋に貯溜する分泌物のように、ある広い範囲内の一部に存在する病変に対応するものであり、他のひとつは、ビラン・潰瘍の擦過物や腫瘤の穿刺検体のように、病変そのものに由来する細胞を含み、細胞診が病変と1対1に対応しうる確率の高いものである。
細胞診の検体採取にあたっては、採取法と得られる検体の病変との対応状況を考え、スクリーニングや診断の目的に沿った採取法を選択すべきである。
細胞診標本の鏡検においては、細胞採取法とスライドグラス上に存在する細胞所見から、主たる病変や随伴する病変の診断の可能性と内分泌環境のような全身的な変化の把握の可否を考慮しなければならない。
細胞採取法
(1)外陰
外陰は角化重層扁平上皮に覆われているので、表面の擦過は診断的意義が少ない。外陰にPaget病のようにビランや潰瘍の形成をみる場合には、生理食塩水で湿した綿棒やスパーテルによる擦過により細胞を採取する。
(2)腟
腟鏡診により腟粘膜に異常を認める場合は、当該部位より、綿棒またはスパーテルの擦過により細胞を採取する。
内分泌細胞診においては、腟鏡診下に、腟上1/3の側壁の綿棒またはスパーテルによる軽い擦過、あるいは、腟に貯溜している分泌物をスパーテルですくい取るように採取する。
後腟円蓋のプールに貯溜している腟内容の採取は、かつては細胞診の主流であったが、現在はほとんど行われていない。
(3)子宮頸部
早期の子宮頸癌および子宮頸部の前癌病変発見のための細胞診の重要性は、歴史的にもルーチンの医療行為としても確立されている。
子宮頸部の前癌病変や初期癌では、扁平上皮系の病変の頻度が高く、細胞診の主たる目的も、このような病変の発見にある。
子宮頸部の異形成、上皮内癌、微小浸潤癌の発生部位は扁平円柱上皮境界であり、当該部位の細胞が確実に採取されている場合には、標本上に外頸部由来の扁平上皮細胞と頸管内膜由来の円柱上皮細胞の両者が観察される(どちらか一方の細胞を欠く場合は、診断に不適当な標本と判定される)。
細胞の採取は、内診、腟洗浄、その他の腟内操作の前に、腟鏡診下に行う。腟鏡診にて子宮腟部の大きさ、腟部ビランの範囲、扁平円柱上皮境界の状況を観察したうえで、適切な細胞採取器具を選択する。そして、扁平円柱上皮境界の部位に応じて、粘膜面を擦過して細胞を採取する。妊娠中の婦人にあっては、軟かい器具を選択すると出血が少ない。細胞を採取したらただちに塗抹・固定を行う。
(4)子宮体部(子宮内膜細胞)
子宮内膜の病変部位から直視下で細胞を採取することは、通常の診療では不可能であり、細胞採取は手さぐりの状況下で、吸引法または擦過法で行われる。子宮と採取器具との関係や子宮内膜病変部位との関係から、目的とする部位の細胞が採取されないことがある。
子宮内膜細胞の採取にあたっては、前もって内診を行い、子宮の傾・屈、偏位、子宮頸部と体部の大きさ、形を確認する。次いで、腟鏡をかけ、洗浄・清拭後子宮腟部を消毒し、マルチン単鈎鉗子で子宮腟部前唇を把持する。子宮ゾンデ診にて子宮頸管の太さ、長さ、子宮の位置、子宮腔の形、大きさ、腔内の病変部位、貯溜液等をさぐる。これにより対象に適した採取器具を選択する。また、外筒やチューブに付された目盛のいずれを指標にするかを決定する。次いで、採取器具を子宮ゾンデの挿入方向に従い静かに挿入、細胞を採取する。
i)吸引法
最近では、銀製の吸引チューブよりも、ディスポ吸引チューブがよく用いられる。充分な細胞量を得るためには、吸引回数は20回以上の操作がよく、チューブ抜去時は陰圧状態にしない。
ii)擦過法
本法に用いる器具は、頸管内細胞の混入をさけるため外筒内に装着のまま子宮腔内に挿入する。器具の先端が子宮底に達するか、外筒の目盛で挿入が完全であることを確認したら、外筒のみを目印まで引きもどし、採取器具の中軸を中心に回転させ擦過する。採取後は、採取部位を外筒に収納し、器具を抜去する。
(5)腹腔,卵巣の穿刺細胞診
腹水の細胞診を目的とした腹腔穿刺は、23~24G針付注射器を用い、モンロー・リヒテル線の中央で行う。超音波断層法ガイド下に行うこともある。採取した腹水には、フィブリンの析出を防ぐため、抗凝固剤(二重シュウ酸塩、EDTA、ヘパリン)を加える。
※Monro-Richter line:臍から上前腸骨棘に引いた線
近年、腹腔鏡の普及により、卵巣の穿刺細胞診が注目されるようになり、卵巣腫瘍の穿刺孔からの内容の漏出を防止する装置の開発と診断的意義の検討が行われている。
細胞の読み方
細胞標本をみる前に、検体の種類、検体の採取法と標本作製法、検査の目的、が何であるかを確認する。
鏡検時まず注意すべきことは標本の良否の評価である。細胞は適切に採取されているか、乾燥していないか、固定は良好か、塗抹の状態はよいか、染色はよいか、などをチェックする。
婦人科細胞診のみかたで重要なものは、性周期や内分泌環境の類推と前癌病変および悪性腫瘍由来の細胞の判定である。
以下の所見はパパニコロー染色による。
i)内分泌細胞診
腟側壁から採取された細胞標本には、重層扁平上皮由来の細胞が観察されるが、角化所見を呈する細胞、エオジン好性の細胞質の細胞や核濃縮を示す細胞の比率から、角化指数、好酸指数、核濃縮指数を求めたり、扁平上皮細胞100個あたりの傍基底,中層,表層の各細胞の比率から成熟度指数を計算し、内分泌環境の指標とする。
子宮内膜細胞診では、増殖期、排卵日周辺、分泌期の判定が可能である。
ii)腫瘍関連病変の細胞診
細胞の形態を観察するにあたり、ふたつの原則を知ることが必要である。
そのひとつは、核の形態はその細胞の活動性を、細胞質の形態はその細胞の機能的分化を反映しているということである。そして、細胞の活動性は、正常状態、退行状態、進行状態、悪性腫瘍状態に分類される。
もうひとつの原則は、生理的である正常状態にある細胞は、形態的に均一で規則性があり、円形傾向を示すことである。
a)正常状態
扁平上皮系の上皮細胞では、核は細胞質の中央にあり、球形または卵円形である。クロマチンは繊細で、均等に分布し、核小体は通常みられない。細胞質は均等、対称性で、分化状態により、淡いピンク色からうすい緑~青色に染まる。円柱上皮系の細胞では、核は基底部にあり、細胞の長軸に平行に配列し、卵円形ないし円形で、クロマチンは細顆粒状で、分布は均等である。細胞質は淡染で、空胞、繊毛を有するものがある。
b)退行状態
変性像である。核は大きくなり淡明化したり、小さくなり濃縮状で観察される。細胞質には、染色性の変化、核周囲淡明化や空胞化がみられる。
c)進行状態
この状態では、核は球状でやや大きくなり緊満しており、クロマチンは顆粒状で均等に分布し、核膜は薄く、緊張している。円柱上皮細胞では核小体がやや大きく明瞭となる。
d)悪性腫瘍状態
悪性腫瘍由来の細胞であることを判定する最大の基準は核所見である。
核の形が不整形となり、クロマチンの大きさ、分布が不整となる。核小体は大きく、数を増すが、細胞ごとに大小不同、形態のばらつきが大きい。核膜は肥厚したものが多いが、肥厚の程度が核の部位によって異る所見を呈するものもある。
核/細胞質比は、細胞における核の占める割合で、癌細胞では大きくなる。また分化度が低いほど大となる。
細胞相互の関係では、核の大小不同、核間距離の不整、細胞の極性の乱れがみられる。
iii)扁平上皮系病変
子宮頸部や腟壁の重層扁平上皮から採取された細胞には、傍基底細胞、中層細胞、表層細胞の三種がある。
これらの細胞の分化をともなったままの状態で、核の増大、核形が球~卵円形、一部不整で、クロマチンの増量、細顆粒状、一部不均等な分布を示す細胞をdysplastic cellと呼び、異形成由来と考えられている。また,HPV感染があればparakeratocyte、koilocyte、smudged 核などが観察される。
擦過法により採取された標本では、細胞の集塊に注意する必要があり、扁平上皮癌では大型の充実性集塊として観察されるものがある。
iv)腺上皮系病変
子宮頸部の円柱上皮や子宮内膜由来の細胞は、擦過法によりシート状、腺管状構造を保ったまま採取され、鏡検時にはその立体構造を思いうかべながら観察する。
子宮内膜増殖症では、子宮内膜腺細胞の核は葉巻状で長楕円形のものが多く、腺管の形態は複雑なものが多い。
腺癌由来の細胞集塊では、腺管状、篩状、乳頭状、索状、立体的不整形のものがあり、細胞の配列と構成細胞の形態から診断を進める。
v)非上皮性悪性腫瘍
女性性器の非上皮性悪性腫瘍は頻度が低いが、非上皮系細胞に異常をみとめたり、由来不明の異常細胞が観察されたら、本腫瘍の存在を疑ってみる。