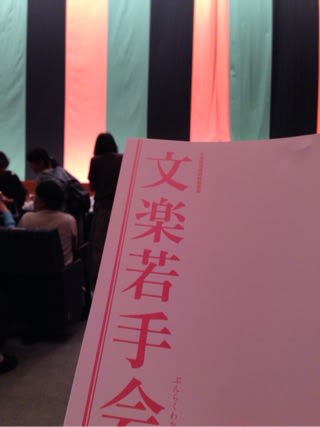私は文字通り長い学生生活の後半、アジアのエンターテイメントを追いかけて過ごした。あ、今日はちょっと文体変えて書いています。
「同時代」というキーワードで求めたその世界は同じ感覚のものもあれば土地それぞれのエッセンスもあり、非常に私を惹きつけた。アンテナをはりめぐらせ、そして、情報に飢えていた。時間があったのは幸い、お金がなかったけれど様々な国の様々な監督の映画を見た。
台湾の映画を劇場ではじめて見たのは、おそらく李安(アン・リー)の「ウエディング・バンケット」ではなかったかと思う。その後、もちろん侯孝賢に出会うも「恋恋風塵」には間に合わず、現在も未見。いくら「非情城市」が好きだ、「戯夢人生」が好きだと言ってもモグリと言われてしまう。この春に出会った人にもそれはおかしい、絶対に見るようにと言われ、TUTAYAディスカスを眺める日々である。
春に出たばかりの『歩道橋の魔術師』を手にしたのはやはりその素地があってのことだった。今はもうない台北市内の中華商場。それは西門町近くの住居兼ショッピングモールだった。
内容紹介
1979年、台北。物売りが立つ歩道橋には、子供たちに不思議なマジックを披露する「魔術師」がいた――。今はなき「中華商場」と人々のささやかなエピソードを紡ぐ、ノスタルジックな連作短篇集。
amazonより
現在の視点は私と同世代、となると、そこから回想される子ども時代も重なる。たしかこの時期の台湾を外地から語るに外せない「戒厳令下」というフレーズは本作にはでてこない。それは台湾の日常だったからであろう。食べ物や店の様子(扉がついてる店は高級店など)が説明しすぎることなく物語に添えられ自然とその様子が思い浮かぶ。いや、食べ物独特の香り、台北の空気はホンモノが思い出され、心は南へ向かうのだ。
主に語られるのは、30年ほど前の台北である。その中で、子ども、子どもから大人になる過程の登場者がその時代を描く。
これが出色である。
台湾、台北という土地による魅力とはまた別に語られるものは時代や場所を越えているのではないかと思う。
連作ほぼすべてに登場するマジシャンが見せた世界が本物であったかどうかは大人になった彼らと同じく読み手である私たちにさほど重要な問題ではなく、それぞれの記憶の中の輪郭がマジシャンによりひとつになるのである。
あえて物語それぞれのエピソードはあげないので興味がある方は他の方の書評をご参考くださいませ。
か・な・り、いいです。