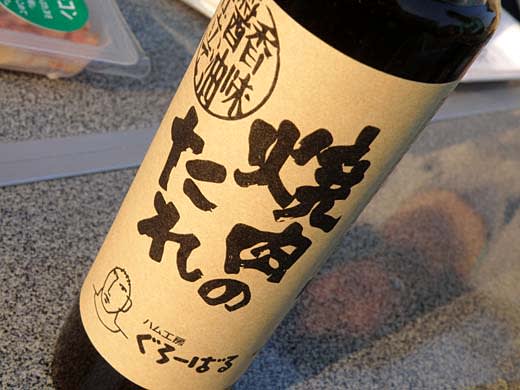仕事柄、川を歩く機会が多いのですが、この時期はキジの姿をよく見かけます。
高崎市内の烏川、車の流れの途切れることのない国道17線のすぐ横の川原でも頻繁にキジと遭遇します。

キジは日本の国鳥

キジを国鳥と決めたのは日本鳥学会です。選定されたのは1947年3月。
国鳥が狩猟対象になっていることは変だという意見もあるでしょうが、国鳥を選ぶ際に姿か形の美しさの他に、人との関わり合いの深さが選定理由になるのは自然なことです。
今日は、2羽のオスが睨み合っている場面を目撃しました。

激しい取っ組み合いになるかと思ったら、2羽は接近したり、少し離れたりしながら移動していき、視界から消えてしまいました。

烏川で見かけた虫や花
ナナホシテントウ

ナナホシテントウの幼虫

ノアザミ

ユウゲショウ

ユウゲショウはアメリカ原産の帰化植物。観賞用に栽培されていたものが野化して広がりました。
道ばたなどでもよく見かけますが、花がかわいいので除草作業でも他の雑草が刈られてもユウゲショウはそのままにされたり、さらに積極的に移植されることもあるでしょう。地味な植物よりも分布拡大は格段に早いと思います。“美人”は得です。
白い花を咲かせている株もありました。

藤岡市内の神流川にて
見慣れないシギがいました。図鑑やネットで調べたり、人に聞いたりしたところキアシシギのようです。

初めて見ました。
旅鳥として干潟などにたくさん飛来し、海の近くではありふれた鳥らしいです。時々内陸部にも姿を見せます。

ナヨクサフジ

ヨーロッパ原産の帰化植物。ナヨクサフジを漢字で書くと「弱草藤」。なよなよした草藤という意味です。
高崎市内の烏川、車の流れの途切れることのない国道17線のすぐ横の川原でも頻繁にキジと遭遇します。

キジは日本の国鳥

キジを国鳥と決めたのは日本鳥学会です。選定されたのは1947年3月。
国鳥が狩猟対象になっていることは変だという意見もあるでしょうが、国鳥を選ぶ際に姿か形の美しさの他に、人との関わり合いの深さが選定理由になるのは自然なことです。
今日は、2羽のオスが睨み合っている場面を目撃しました。

激しい取っ組み合いになるかと思ったら、2羽は接近したり、少し離れたりしながら移動していき、視界から消えてしまいました。

烏川で見かけた虫や花
ナナホシテントウ

ナナホシテントウの幼虫

ノアザミ

ユウゲショウ

ユウゲショウはアメリカ原産の帰化植物。観賞用に栽培されていたものが野化して広がりました。
道ばたなどでもよく見かけますが、花がかわいいので除草作業でも他の雑草が刈られてもユウゲショウはそのままにされたり、さらに積極的に移植されることもあるでしょう。地味な植物よりも分布拡大は格段に早いと思います。“美人”は得です。
白い花を咲かせている株もありました。

藤岡市内の神流川にて
見慣れないシギがいました。図鑑やネットで調べたり、人に聞いたりしたところキアシシギのようです。

初めて見ました。
旅鳥として干潟などにたくさん飛来し、海の近くではありふれた鳥らしいです。時々内陸部にも姿を見せます。

ナヨクサフジ

ヨーロッパ原産の帰化植物。ナヨクサフジを漢字で書くと「弱草藤」。なよなよした草藤という意味です。