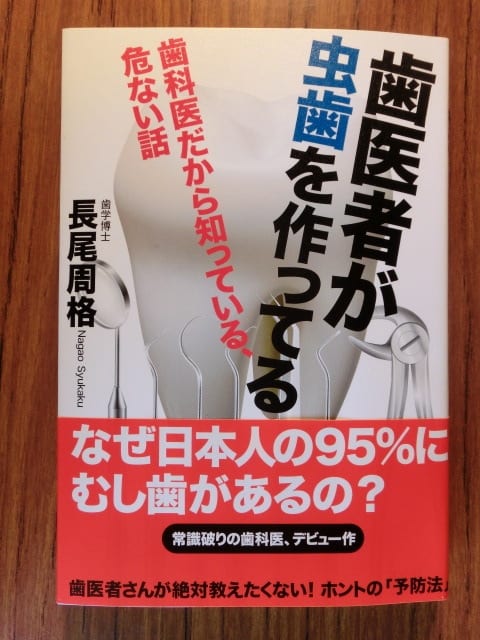
第1章で、間違いだらけの歯の常識が10個も紹介されます。
1.歯磨きは虫歯を予防する
2.フッ素は虫歯予防に効果的
3. シーラントは虫歯を予防する
4.歯磨き後にはマウスヲッシュ剤を
5.歯間ブラシでプラークコントロール
6.虫歯の原因は虫歯菌
7.歯周病は歯周病菌が原因
8.歯並び・咬み合わせの異常は遺伝的なもの
9.よく咬むことが不正咬合の予防になる
10.定期検診で虫歯を予防する
著者の長尾周格氏は、北海道大学出身の歯学博士ですが、分子整合栄養医学の研究者でもあります。
また、1939年に出版された予防歯学の父であるW・A・プライス博士の「食生活と身体の退化」の信奉者でもあります。
プライス博士は世界中でその土地の先住民族集団と近代化集団の虫歯罹患率を調査しました。
スイスでは虫歯罹患率はそれぞれ、4.60%と29.8%
ゲール族では、1.20%と30.0%
イヌイットでは、0.09%と13.0%
北方アメリカ先住民では、0.14%と21.5%
オーストラリア先住民では0.00%と70.9%
ニュージーランド・マオリ族では、0.01%と55.3%
マレー人では、0.09%と20.6%
アマゾン・ジャングル・インディオでは、0.00%と40.0%でした。
これら先住民族の人たちには、歯磨きの習慣はありません。
フッソを歯に塗ったりもしませんし、定期的に歯医者で検診を受けたり、歯石取りをしたりもしません。
彼らの歯にはプラークや歯石が存在しますが、何もしないのに虫歯や歯周病にはならないのです。
そして、これら先住民族の食事を分析して、虫歯予防の基本原則を以下のように記しています。
1.砂糖や異性化糖などの強い甘みを持つ糖類の摂取を一切やめること。
2.精製された糖質(白米や精製糖質で作られたパン、麺類など)の摂取を控えること。
3.加工食品、インスタント食品、ファストフードなどの摂取を控えること。
4.植物油の摂取を控えること。
5.牛乳やヨーグルトは一切摂らないこと。
6.タンパク質、特に動物性タンパク質を積極的に摂ること。
7.新鮮な野菜や果物を摂るようにすること。
8.動物性食品と植物性食品の摂取比率は、7:3が好ましい。
9.タンパク質、脂質、糖質の摂取比率はカロリーベースで、4:4:2にすべき。
結局は糖質制限が基本のようです。
さて、この本の内容で最も興味深かったのは、先住民族では結婚することが決まった花嫁には、式の6か月前から、特殊な栄養食を食べさせることが多いということでした。
特に重要なのは貯蔵鉄を増やしておくということだそうです。
生まれてきた子どもは腸管の吸収力が弱く、6歳になるくらいまでは、鉄分を吸収することができないそうなのです。
つまり、6歳までは生まれる時に母親からもらった鉄分だけで賄っていかねばなりません。
この鉄分が不足している子供は鼻中隔軟骨の形成不全を起こしやすく、それは不正咬合を誘発するのだそうです。
もともと鉄不足は不妊や、早期流産の原因とされています。
極端な肥満あるいは極端な痩せの女性が無月経になるのと同様に、神様は危険な出産を回避するシステムを採用されておられるようにも見えます。
ところで、昨日の当ブログへの訪問者数は1202名と過去最多を更新しました。
糖反射という地味なタイトルと地味な内容でしたので原因が分かりません。
1200名ですと知己も無い方々が大多数でしょう。
自分で読み直しても、最近は、特に面白い記事も無いように思えます。
不思議です。
不思議ではありますが、とりあえずは毎日の更新に励むこととしました。










