
子供同士の喧嘩で、負傷させた方の夫婦が、負傷した側の夫婦宅へ謝りに訪れます。
最初の和気あいあいの雰囲気が次第にピリピリしたものとなり、途中からは罵りあいに発展します。
更には、夫婦喧嘩が発生したり、男性二人がタッグを組んで女性二人に対峙したりのドタバタコメディーでした。
被害者側の妻ペネロプをジョディー・フォスターが演じていました。
ペネロプはアフリカの民族紛争や難民問題を憂慮する出版物?製作に関係したり、絵画の本を集めたり、
子供の情操教育を考えて、定期的にコンサートや絵画展に連れていくという、良き母親でした。
ところが彼女こそが、この喧嘩のA級戦犯なのです。
相手の男の子が、持っていた棒きれを振り回し、たまたま自分の息子の口にあたって前歯が2本折れ、唇が腫れたのですが、
ペネロプの表現では、”武装した少年に襲われ、フィギュア?が変形した。”となります。
また、加害者側の妻が息子を謝罪に連れてくることを提案しても、”無理やり連れてくることに意味はない。
本人が本当に反省して謝罪したがらない限りは、お断りだ。”と問題をややこしくしていきます。
ストーリーの終盤で加害者側の夫がペネロプに対して次のように怒鳴ります、
”正義の番人のような女なんて、クソックラエだ。男はみんなかわいくてセクシーな女が好きなんだ。
テレビにジェーン・フォンダが出てくると腹が立って、KKK(ク・クラックス・クラン?)に加担したくなる。”
ロマン・ポランスキー監督が最もしゃべらせたかった台詞はこれであったような気がします。(セリフはうろ覚えですので正確ではありません。)
この作品は冒頭で、タイトルとクレジットを流しながら、公園での少年達のいざこざのシーンが、顔も認識できないほどの遠くからの、音声も無い画像で始まります。
最後も同じような公園のシーンにエンディングクレジットが入ります。
この冒頭と最後のシーン以外はすべて、ずっと、ペネロプの住まいでの連続的な出来事なのです。
インターネットで検索してみると、もともとは舞台劇であったものを、ポランスキー監督が映画化したそうなのです。
何の為なのか意味がわかりません。監督の気まぐれか思い付きでしょうが、舞台ではとても実現できない映画の利点を最初から放棄しているのです。
この映画は玄人受けしたそうですが、素人の私には退屈な作品に過ぎませんでした。
特に前半はジョディー・フォスターの無神経な言葉遣いと、加害者側の夫の携帯電話にいらつかされるばかりでした。
この映画の製作費は通常のハリウッド映画の数十分の一に過ぎないように思われます。
単なるショボイ作品でした。












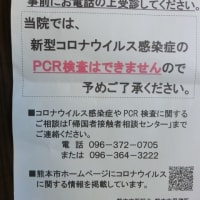








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます