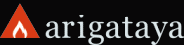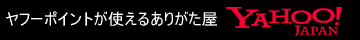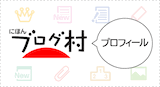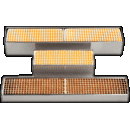薪ストーブ暮らしが大好きでブログ書いてます。
燃焼のこと、薪作りやメンテナンスのこと、そんな写真と駄文で毎日更新!
薪ストーブ|薪焚亭
アンコールのダンパー調整

快晴ではないんだが、梅雨の晴れ間的な日差しを浴びると暑いです。 ホント蒸し暑い。 まだまだ序の口なんだろうけど、カラダが慣れてないって感じかな。
そんな暑い時期に薪ストーブの話題ってのがまた粋な計らいだと思ってんですが、て言うか、味わい深いじゃないっすか? 風流ですぜ旦那(笑)
 28/494人
28/494人今日もヨロシクです!
あるんですねぇ便利なのが! のつづきです。
今さらアンコールのダンパーの調整について書いても、アンコールユーザーにはちっとも新鮮じゃないんだろうけど、もしかして知らない人もいるかも知んないんで、一応書いておこうかなと、なので、知ってる人はクリックしたらスルーしてちょ(笑)
調整って言ったって実に単純で簡単なことなんですがね。 下の写真の通りなんですが、順を追って説明です。
ここのボルトやナットは焼付きしやすい場所なので、少なくとも年に一回、調整の必要あるなしに関わらずシーズンイン前に動かしてやると焼付き防止になります。
その時にグリスを点してやるといいんですが、出来れば 耐熱グリス がいいです。

この全ネジは6角レンチで回すんですが、しっかりメンテしてあれば指でも回ります。
このネジを裏側へどのくらい出っ張らせるかでダンパー操作の感触が変わります。 きつ過ぎてもゆる過ぎてもしっくりこない。 特にゆる過ぎは触媒燃焼時の気密が悪くなるので良くないですね。
ガスケットを張り替えたばかりで調整すると、その時はきつくてもしばらく使ってるとガスケットが馴染んで少しゆるくなると思うので、そうなったらまた調整してやるといい。

これが裏側ですが、ネジそのものは見えません。 ダンパーランプというパーツの下に出てくるからで、このダンパーランプはボルトで留めてあるんですが、ある程度遊びがあるので加圧ネジの出っ張り具合に順応する訳です。

上の写真がダンパー開放時のロッドの位置で、下がダンパーを閉じた時の位置ですね。 見ての通りで理屈は簡単です。 ダンパーランプが盛り上がればきつくなり、逆ならゆるくなる。 ただそれだけのことです。

組付けて炉内から見ればこうなります。 まぁ仕組みは単純なので、ここでのポイントは上でも書いたように焼付き防止のために時々動かしてやることですかね。
ここはとにかく過酷な場所です。

これはオマケ画像です。 本来はダンパーユニット(アッパーファイヤバック)を組込む時はセメントで固めつつボルトで締めるんですが、自分はバックパネルだけでなくここもガスケット化してしまってます。 理由はというと、セラミックボックス(二次燃焼室)の交換を簡単にするためなんですがね。 それと、ダンパーガスケットの張替えも簡単になります。 それについてはヒミツの穴とともに後でまた書きます。
つづく

まきたきてー発電所 毎日の発電実績
2013年のキュウリ収穫累計 : 13本/ナス収穫累計 : 4本
大玉トマト収穫累計 : 0個/小玉トマト収穫累計 : 0個





コメント ( 0 ) | Trackback ( )