【比嘉政夫監修、大正治・杉浦孝昌・時雨彰著、明石書店発行】
雲南省は中国の南西部に位置する広大な山岳地帯。面積は日本よりやや大きく、ベトナム、ラオス、ミャンマーと国境を接する。2002~03年、日中の研究者12人がメコン川最上流に当たる同省南西部の9つの村の少数民族(タイ族、ワ族、ハニ族など)を対象に、伝統的な焼畑など森林の利用状況や森林に関する信仰などについて現地調査した。本書はその調査を踏まえつつ、森林と共生する少数民族の生活様式や森林文化の現代的な意義を指摘する。
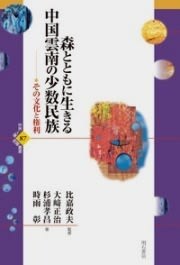
中華人民共和国成立直後の1950年代、中国では食料増産のための「大躍進」政策と人民公社化運動で、木材の伐採が全国規模で行われた。さらに60~70年代の文化大革命の時期には「改天換地」のスローガンの下、山や谷が全て段々畑に改造された。少数民族の多くが万物に霊的存在を認め、山や森林にも神が宿ると信じていたが、この間、神樹や聖域の森林も容赦なく伐採された。その結果、「森林破壊が進んだだけでなく、元来あった森林利用権も多く変化を被ったので、各地で権利紛争が多発した」。
転機となったのが98年に発生した長江(揚子江)と黄河での大洪水。これを機に中国政府は「退耕還林」という政策を打ち出した。「過去40年来進めてきた、森林を農地に変えるコースを180度転換して、耕地を森林に戻す」方向に舵を切った。「世界最大の自然環境対策事業」と自負する政策で、退耕地造林面積だけで906万ヘクタール(日本の森林総面積の2.6分の1)に達した。ところが2007年、政府は「退耕還林の暫時停止」を発表し急ブレーキをかける。「このまま続けると、農地と食料が不足する恐れが出てきた」という判断によるとみられる。
少数民族は多くが焼畑農耕を山林利用の中核に据えてきた。1年ないし数年の短期間耕作した後、長い間休閑して森林を回復する。休閑中に再び土壌に養分が蓄積され、休閑林は山菜や薬草、果実、小動物などを採集して自給や販売もできる。少数民族はそれを何百年も繰り返してきた。
焼畑といえば森林破壊の元凶とみなされることが多い。中国政府も退耕還林策を打ち出した際、「長江の大洪水は上流の傾斜地において長期にわたって続いた粗放農法が原因」と、責任を焼畑に転嫁した。だが本書は「化学肥料にも農薬にも頼らない点で、伝統的焼畑は人類生存と生命健康の観点からいえばすぐれた農法」「農林業を復活させるのは農業と林業を同時に営むアグロ・フォレストリだと言われているが、焼畑こそその元祖」と指摘、森林の荒廃が進み土砂崩壊が増えている日本でも「焼畑を維持復活していきたい」と望む。
最終の第Ⅲ部第3章「新しい森林政策と思想」では、①森林保護は少数民族文化の保存をベースに②少数民族の土地・森林利用権を認め充実する③自然との共生を優先し商品経済を制御する――ことを提言する。そして最後をこう結ぶ。「新しい森林政策は、森林に生きる少数民族を排除するものであってはならない。彼らの多くは焼畑という生業によって地域々々の豊かな生態環境を生み出し維持してきたのであるから、焼畑農法を禁止するのではなくそれを活かす方向で森林政策を再構成すべきである」。
















