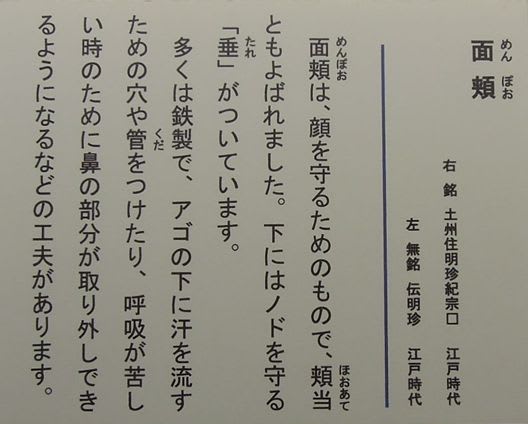六丁峠から嵐山方面に下っていくと・・・

「檀林皇后九相図」で知られる、第52代 嵯峨天皇后の嵯峨陵 でしょうか?
九相図とは、遺骸が朽ちていくさまを9段階に描いた仏教画のことです。

ここで通行止めでした。

● 京都の西福寺にある「檀林皇后九相図(だんりんこうごうくそうず)」
嵯峨天皇の皇后:檀林皇后(橘嘉智子)は、仏教に深く帰依し、自らが餌となって飢えた生き物たちを救うため、また、この世のあらゆるものは移り変わり永遠であるものは何一つ無いという教えを示すため、自らの遺骸は路傍に放置し、動物に食い荒らされてても哀れと思うな、と遺言したと伝わっている。美女として名高かったゆえに、死は身分や容姿にかかわらず必ず訪れるという教えとなり、どれほど美しくとも、死後は醜く腐り骨となり土に還る、と、僧の情欲を断ち切らせるために描かれたといわれる。死の瞬間のまだ美しい姿から、腐敗ガスで遺骸が膨らむ→腐る→虫がわく→鳥獣が食べる→ほとんど骨になる→完全な白骨になる→骨が散乱する→塚が建つ、の9場面に描き分けられた1枚の図です。(作者不詳)

いま、この奥の人の目も届かない静かな所で安らかに眠っておられるのです。

「檀林皇后九相図」で知られる、第52代 嵯峨天皇后の
九相図とは、遺骸が朽ちていくさまを9段階に描いた仏教画のことです。

ここで通行止めでした。

● 京都の西福寺にある「檀林皇后九相図(だんりんこうごうくそうず)」
嵯峨天皇の皇后:檀林皇后(橘嘉智子)は、仏教に深く帰依し、自らが餌となって飢えた生き物たちを救うため、また、この世のあらゆるものは移り変わり永遠であるものは何一つ無いという教えを示すため、自らの遺骸は路傍に放置し、動物に食い荒らされてても哀れと思うな、と遺言したと伝わっている。美女として名高かったゆえに、死は身分や容姿にかかわらず必ず訪れるという教えとなり、どれほど美しくとも、死後は醜く腐り骨となり土に還る、と、僧の情欲を断ち切らせるために描かれたといわれる。死の瞬間のまだ美しい姿から、腐敗ガスで遺骸が膨らむ→腐る→虫がわく→鳥獣が食べる→ほとんど骨になる→完全な白骨になる→骨が散乱する→塚が建つ、の9場面に描き分けられた1枚の図です。(作者不詳)

いま、この奥の人の目も届かない静かな所で安らかに眠っておられるのです。