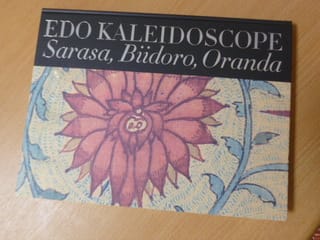台風10号が近づいているらしい
まるで亜熱帯の国のような雨が降る。かと思うと湿気を含んだ熱風に悩まされる
冷房の風が苦手なので、着物の助けを借りている。着物を着ていると刺すような冷たい風から体を守ってくれる
夏らしい服を着て汗をいっぱいかきたい。こんなささやかな希望も全く無視される冷房崇拝者の多い風潮が怖い
人は自然に生きられなくなっているのだ
夏は汗をかくのが当たり前なのにーーー常に体を冷やすようになってしまったので熱中症が増える
ここへきて自然に生きることの難しさに当惑している私がいる
湯文字がそう
湯文字をつけていた頃は生理センサーが敏感になっていて
生理を感じたら便所(といれ)に行って流す。それはお小水や大便をもよおしたときと同じ感覚だ。だからショーツだとか生理帯など全く必要がないのだ
病気とか遠出のときは自然素材でふんどしをつけててそこに脱脂綿を当てていたという
33歳で初めて着物の本を出版し曲がりなりにも着物の専門家顔をしてしまった手前
昔の人の着物の下着についての取材を始めた
母たちの世代の人はみんなノーパンで湯文字をつけていた
実の母親に「生理のときは?」という質問ができず、当時80代や90代で元気な女性に湯文字をつけたときの生理の状態は?という質問を重ねた
その結果が前述のようなこと
姑にも聞いてみた、そうしたら「こういう形のものを使っていた」という女性用のふんどしを作ってくれた
何でもすぐ行動するチャコちゃん先生早速湯文字の下にそのふんどしをつけ生理をしのいだが
本当はそういうものもつけないで生理コントロールを研ぎ澄ませなければいけない
そこで試してみたしかし失敗
生まれたときからショーツのある生活だもの生理コントロールは錆びついている
それでも何回かの失敗にもめげず続けた結果成功!
それは瞑想と似た内面集中でもあった
日本の女性が優しく明るくそれでいていつも覚悟ができているという外人の評価は、この湯文字生理コントロールにあったのかもと今は思う
#生理帯 #湯文字 #ふんどし #日本の女性 #ショーツ #ノーパン #湯文字生理コントロール #チャコちゃん先生 #中谷比佐子 #姑 #着物の専門家 #脱脂綿 #熱中症 #冷房が嫌い
話題の映画を観た
涙を流して感度をした
という方と
一言 酷い映画だ
という人がいる
ところで私は
感動はなかった
10代の少女と少年が何のための家出をし都会に出て風俗の仕事をしようというのか、その中の純愛を描きたかったのか
どうしてラブホテルに行くのか
どうしてカップヌードルやマクドナルドの食事なのか
そういう中でも愛だけは真実と言いたいのか
日本から
純文学や思想や哲学は無くなっていくのか
常識が非常識になるという時代の先取りなのか
つまりはよく理解できなかった
そして楽しくなかった それが全て
危うい!
京都に行くのに発車時間1時間半前に目がさめる
ふーーー間に合った
昨日いらした方 三時間睡眠を三十年続けているという
12時にやすみ3時に起きるのだそうだ
その結果は全て思い通りに事が運び
お金、人間関係、健康も全く心配がないーーーい
なんといっても21時間仕事に使える自分の時間 、いろんなことが解決できるとニコニコ笑って話された「ナポレオンの気持ちがわかります」だって!
お人がいいと言うことは一応すぐ実行してみるのがチャコちゃん先生の流儀それで11時に休み2時に起きるように言い聞かして休んだ
しかし
目が覚めたら6時30分
わーよく寝たなあ 今日は何する日だったかな!
いけないっ!8時の新幹線に乗るんですよ
「あなた3時間で起きるんじゃあなかったの⁈」
はや一夜で挫折
元々8時間寝たい人がいきなり3時間に挑戦するのは無理があるというもの
しかし
このかた3時に起きて2時間本を読み、1時間散歩して朝風呂に入り、朝食は取らず20分の瞑想 その後支度をして出社、会社は8時から16時
これは奈良時代から江戸時代初期の勤務状態と同じだ
自然の廻りと調和しているのでなんでも成功すると昔の人は知っていた
宇宙は「成功」という文字しかない!
人間が勝手に周波数を壊しているという教え
なのに私目はぐっすり寝込んでいたよ
#宇宙法則 #ちゃこちゃん先生 #周波数 #奈良時代の勤務状態 #宇宙は成功しかない #自然との調和 京都行き新幹線 #中谷比佐子