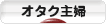カンヌのパルムドール大賞から数々の賞を受賞している本映画。
聞いてたとおり、眠かったぁ~
てか、無音状態になる度、睡魔に襲われブツ切れ観賞になっちまいました
1913年夏、北ドイツのある村。張られた針金が原因でドクターが落馬したのが発端だった。
翌日にはその針金が消え、小作人の妻が男爵家の納屋で起きた事故で命を落とす。
秋、収穫祭の日、母の死に納得できない息子が、男爵の畑のキャベツを切り刻む。
その夜、男爵家の長男ジギが行方不明になった。
一方、牧師は反抗的な自分の子供たちに“純心”の象徴である白いリボンを腕に巻かせる。
犯人がわからないまま、不信感が村に広がっていく。
(goo映画より)
とはいえ、モノクロ映像は美しかったです。
美しい村に次々起こる不可解な事件――。
無駄に脅しをかけるような映像も効果音も無く、むしろ極力そういった物を排除し、
静謐なまでに淡々と教師の語りで繋いでいく映画でした。
事件は起こりますが、解決をみるわけではなく、
語っている教師が後に事実をつきとめたわけでもなく、
監督が言うように「見えないものを見ようとすることで、見えてくるものを見てください。」
というスタンスで、どう受け取るかは観賞者しだい。
“第一次世界大戦前夜、後にナチとなった子供たちが暮らした時代”とあったので、
後半、もう少し戦争色が出てくるのかと思っていましたが、
ホントに“戦争前の一村での出来事”の描写でした。
女、子供は人として扱われなかった時代。
大人の言うことは絶対であり、男に逆らってはいけない時代。
大人であれ子供であれ、人は抑圧されると自己保全のために、どこかにはけ口を求めます。
それが外に向かうのか、内に向かうのか…。
(昨今の若者はイジメ、リストカット、引きこもり、自殺ですかね。)
男爵夫人は「この村で子供は育てられない。」と言います。
“純真無垢であれ”と腕に巻かれるリボン。
余計な疑問を持たないように育てられる子供たち。
そして時代はナチに向かってうねって行く。
映画を観終わったあと、ふっと母から聞いた「えんちこ」なる物を思い出しました。
こんなの
これはその昔、自分のいなかの方で、農家の人達が実際使っていたもの、
赤ん坊を入れるゆりかごのようなものです。
農作業をするさい、小さな赤ん坊がいると大変なわけで、
そこで「えんちこ」に入れて自分が働く畑や田んぼの脇にころがしておくんですが、
赤ん坊は手足を真直ぐに伸ばされて、顔だけ出して全身さらしでグルグル巻き、だるまさん状態です。
おむつを取り替えるなんてことは考慮されてなく、
えんちこの底には灰を入れてオシッコが沁み込むようにして使います。
作業をしてる大人にとっては動きまわるようになった赤ちゃんを
いちいち見てなくていいし、毎回おむつを交換しなくていい便利モノですが、
赤ちゃんにとっては体の自由は全く無く、拷問のようなものじゃないかと…。
自分の実家は農家じゃないので実物を見たことはないんですが、
自分の世代のちょっと前までは使っていたそうです。