ノンフィクション作家の最相葉月(さいしょうはづき)さんが書いた労作「星新一 一〇〇一話をつくった人」を読み終えました。
単行本「星新一 一〇〇一話をつくった人」は序章、12章の本体、終章、あとがきの15章で構成されています。総ページ数は574ページです。
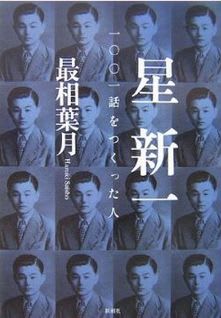
星新一さんがショートショートという形式のある種の実験小説を書き始め、父親の星一が創業した星製薬の経営陣から離れて、小説家として別の人生を歩み始めるのが、第5章以降です(当然、星製薬の経営建て直しと経営陣の入れ替えの話と、星新一が小説家になっていく話が交錯しています)。
「星新一 一〇〇一話をつくった人」を読み始め、父親の星一が星製薬を創業し、突然倒れた結果、長男の星新一が星製薬の次期社長になり、経営再建に苦労するなどの過程は、弊ブログの2014年10月29日編をご参照ください。
星新一がショートショート「セキストラ」を書いて、新しいSF(空想科学)小説として成功し、短編小説の依頼が続き、小説家として成功していきます。昭和32年(1957年)の話です。当時の日本の小説は、純文学と呼ばれる小説(芥川賞の審査対象の小説など)が小説と考えられていたころだったために、星新一のショートショートは日本のSF小説の起点として、出版会社の編集者は歓迎します。当時の出版界では、SF小説に手を出せば、必ず失敗する(売れずに、赤字になる)という“伝説”があったそうです。
その一方で、星新一の登場は当時一部の熱烈なファンが支持していた日本のSF小説の起爆剤になると歓迎されます。
当時のSF小説を商業的に成功させたいと考えていた編集者の都筑道夫や矢野徹などの出版社の編集者や評論家は、星新一を起点に商業的な成功を図ります。
同人誌「宇宙塵」に掲載したショートショート「ボッコちゃん」が商業誌に転載されると、その評判は好評で、小説家として星新一は生計を立てるようになります。当時は、ショートショートを書いているか、寝ているかの日常が多く、執筆時に構想を練ることはかなり厳しかったようです。眠るために、睡眠薬や酒を用いていたと書かれています。
後半部の第11章「カウントダウン1001編」に、星新一が用いた「要素分解共鳴結合」という小説の骨子のアイデアを産み出す手法が解説されています。書き損じの原稿用紙を切ったメモ帳に単語などが書かれていて、それを組み合わせて新しい発想を生み出していく過程が説明されています。この手法は真似は簡単ですが、このメモ用紙の組み合わせから独創的な構成内容を産み出す着想は、星新一の頭脳だからできた業(わざ)です。
星新一は原稿執筆には苦しみましたら、出版社と約束した締め切りは破らず、清書した原稿を編集者に毎回、手渡したそうです。これは簡単にはできないことです。
星新一と当時の編集者たちが開拓した日本のSF小説では、小松左京や筒井康隆などが売れっ子になり始め、豊田有恒、平井和正、光瀬龍、広瀬正、半村良などのSF小説家(SF小説プラスアルファ)が育ち始めます。星新一のショートショートのイラスト(挿絵)を担当した真鍋博や和田誠との交流、当時の商業誌の編集者との交流は、とにかく面白いです。
星新一がショートショート小説家として、世に出る時には江戸川乱歩が好意的に動いたなどのエピソードも面白いです。
日本が戦後の高度成長を始める昭和30年代から40年代に、面白い小説(現在の直木賞の対象となる小説)が市民権を得るまでの過程がよく描かれています。実に多彩な方が登場します。
この単行本の著者の最相葉月さんが、実に多くの参考文献を読んでいることに感心しました。
単行本「星新一 一〇〇一話をつくった人」は序章、12章の本体、終章、あとがきの15章で構成されています。総ページ数は574ページです。
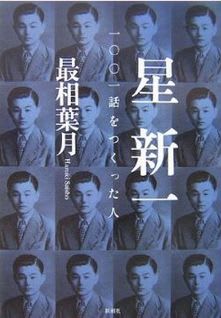
星新一さんがショートショートという形式のある種の実験小説を書き始め、父親の星一が創業した星製薬の経営陣から離れて、小説家として別の人生を歩み始めるのが、第5章以降です(当然、星製薬の経営建て直しと経営陣の入れ替えの話と、星新一が小説家になっていく話が交錯しています)。
「星新一 一〇〇一話をつくった人」を読み始め、父親の星一が星製薬を創業し、突然倒れた結果、長男の星新一が星製薬の次期社長になり、経営再建に苦労するなどの過程は、弊ブログの2014年10月29日編をご参照ください。
星新一がショートショート「セキストラ」を書いて、新しいSF(空想科学)小説として成功し、短編小説の依頼が続き、小説家として成功していきます。昭和32年(1957年)の話です。当時の日本の小説は、純文学と呼ばれる小説(芥川賞の審査対象の小説など)が小説と考えられていたころだったために、星新一のショートショートは日本のSF小説の起点として、出版会社の編集者は歓迎します。当時の出版界では、SF小説に手を出せば、必ず失敗する(売れずに、赤字になる)という“伝説”があったそうです。
その一方で、星新一の登場は当時一部の熱烈なファンが支持していた日本のSF小説の起爆剤になると歓迎されます。
当時のSF小説を商業的に成功させたいと考えていた編集者の都筑道夫や矢野徹などの出版社の編集者や評論家は、星新一を起点に商業的な成功を図ります。
同人誌「宇宙塵」に掲載したショートショート「ボッコちゃん」が商業誌に転載されると、その評判は好評で、小説家として星新一は生計を立てるようになります。当時は、ショートショートを書いているか、寝ているかの日常が多く、執筆時に構想を練ることはかなり厳しかったようです。眠るために、睡眠薬や酒を用いていたと書かれています。
後半部の第11章「カウントダウン1001編」に、星新一が用いた「要素分解共鳴結合」という小説の骨子のアイデアを産み出す手法が解説されています。書き損じの原稿用紙を切ったメモ帳に単語などが書かれていて、それを組み合わせて新しい発想を生み出していく過程が説明されています。この手法は真似は簡単ですが、このメモ用紙の組み合わせから独創的な構成内容を産み出す着想は、星新一の頭脳だからできた業(わざ)です。
星新一は原稿執筆には苦しみましたら、出版社と約束した締め切りは破らず、清書した原稿を編集者に毎回、手渡したそうです。これは簡単にはできないことです。
星新一と当時の編集者たちが開拓した日本のSF小説では、小松左京や筒井康隆などが売れっ子になり始め、豊田有恒、平井和正、光瀬龍、広瀬正、半村良などのSF小説家(SF小説プラスアルファ)が育ち始めます。星新一のショートショートのイラスト(挿絵)を担当した真鍋博や和田誠との交流、当時の商業誌の編集者との交流は、とにかく面白いです。
星新一がショートショート小説家として、世に出る時には江戸川乱歩が好意的に動いたなどのエピソードも面白いです。
日本が戦後の高度成長を始める昭和30年代から40年代に、面白い小説(現在の直木賞の対象となる小説)が市民権を得るまでの過程がよく描かれています。実に多彩な方が登場します。
この単行本の著者の最相葉月さんが、実に多くの参考文献を読んでいることに感心しました。




















