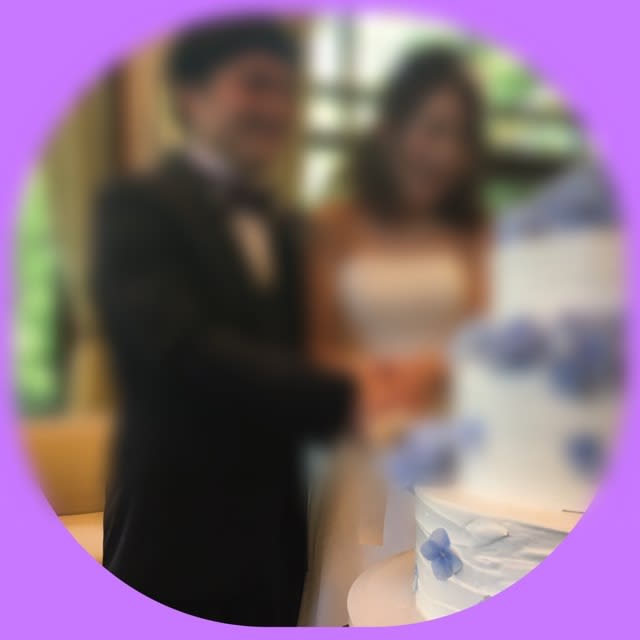
教育では、生徒の感情にはたらきかけることは大切です。
たとえば、友だちにいやがらせをした子を指導するとき、いやがらせをされた子のつらかったという感情、傷ついたという感情を、いやがらせをした子が聞き、ひどいことをしたと、自らの行いを反省する。
また、職場で同僚が結婚すると聞いて、「おめでとう」と言いながら、本人がうれしそうにしている感情を受け、同僚までがうれしくなる。
このように、人は相手の感情に触れることで、心が動きます。
ただし、感情にはマイナス面もあります。感情だけで出ている言葉は、それを受ける人の感情を刺激して、いわゆる「感情的」にしてしまいます。
激昂した人が放つ言葉は、受けとる側も激昂させることがあるのです。
感情は動きやすいものです。根拠がなかったり論理的でない場合もあります。
だから、教育の分野でも、仕事の分野でも、人間関係では、感情に流されず、理性を働かせて、ものごとを見て、考えていく習慣もつけたいのです。









