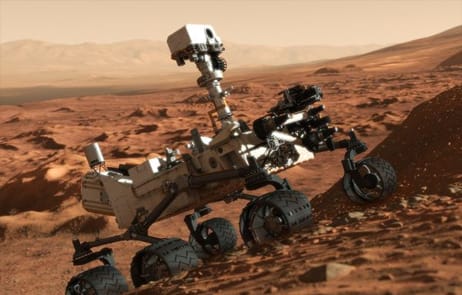引退したスペースシャトルの後継機はどうなるのか?
NASAは後継機となる有人宇宙船の開発を、アメリカの民間3社に委託したんですねー
3社は2014年までに設計と試験を終えて、17年までに有人宇宙飛行を目指すことになります。
委託先は大手航空宇宙メーカーのボーイング社と、新興宇宙企業スペースX社、宇宙関連企業シエラネバダ社の3社です。
NASAはボーイング社に4億6000万ドル(約360億円)、スペースX社に4億4000万ドル(約350億円)、そしてシエラネバダ社に2億1250万ドル(約170億円)を提供します。
候補の宇宙船は、カプセル型の“CST-100”と“ドラゴン”、有翼型の“ドリームチェイサー”
これらを打ち上げるロケットは、“ファルコン”と“アトラスV”になります。
ボーイング社は“CST-100”、スペースX社は“ドラゴン”、シエラネバダ社は“ドリームチェイサー”を開発中なんですねー
“CST-100(Crew Space Transportation-100)”は、ボーイング社がビゲロー・エアロスペース社と共同でNASAに提案した宇宙船です。
想定される任務は国際宇宙ステーションや、ビゲロー社が検討中の商業用宇宙ステーションへ乗員を輸送することなんですねー
アトラスVやデルタIV、ファルコン9を含む様々なロケットに合うように設計されているのですが、当面はアトラスVでの打ち上げを予定しています。
“ドラゴン”はNASAの商業軌道輸送サービスの契約により、スペースX社が開発している宇宙船です。
国際宇宙ステーションへの物資補給を目的としていて、ファルコン9ロケットで打ち上げられます。
すでに今年の5月に無人で打ち上げられ、国際宇宙ステーションへの物資輸送に成功しているんですねー
商業的に開発され運用された宇宙船として、初めて大気圏に再突入し回収されました。
実運用に一番近い宇宙船かもしれません。
“ドリームチェイサー”はシエラネバダ社の子会社であるSpaceDev社によって開発中の宇宙船。
2人~7人の乗員を国際宇宙ステーションへ輸送し、帰還させるために計画されました。
スペースシャトルを小さくしたような機体なんですが、他の宇宙船と同じくロケットで打ち上げられます。
もちろん帰りは滑空して通常の滑走路に着陸するんですねー
アトラスVによる打ち上げが予定されています。
全マイルストーンの最後には、製造着手可否を判断する詳細設計審査会(CDR)があります。
ボーイング社とスペースX社はCDRに移行するのですが、シエラネバダ社はそこまで達していないんですねー
まぁー いずれは宇宙ステーションへの乗員と物資輸送に使われる事になるんでしょうね。
もう低軌道への飛行は民間に任せても大丈夫ということでしょー (^_^)
運用コストも民間の方が有利なので、NASAには地球外軌道への飛行で頑張って欲しいですねー
NASAは後継機となる有人宇宙船の開発を、アメリカの民間3社に委託したんですねー
3社は2014年までに設計と試験を終えて、17年までに有人宇宙飛行を目指すことになります。
委託先は大手航空宇宙メーカーのボーイング社と、新興宇宙企業スペースX社、宇宙関連企業シエラネバダ社の3社です。
NASAはボーイング社に4億6000万ドル(約360億円)、スペースX社に4億4000万ドル(約350億円)、そしてシエラネバダ社に2億1250万ドル(約170億円)を提供します。
候補の宇宙船は、カプセル型の“CST-100”と“ドラゴン”、有翼型の“ドリームチェイサー”
これらを打ち上げるロケットは、“ファルコン”と“アトラスV”になります。
ボーイング社は“CST-100”、スペースX社は“ドラゴン”、シエラネバダ社は“ドリームチェイサー”を開発中なんですねー
 |
| ボーイング社“CST-100(Crew Space Transportation-100)” |
想定される任務は国際宇宙ステーションや、ビゲロー社が検討中の商業用宇宙ステーションへ乗員を輸送することなんですねー
アトラスVやデルタIV、ファルコン9を含む様々なロケットに合うように設計されているのですが、当面はアトラスVでの打ち上げを予定しています。
 |
| スペースX社“ドラゴン”補給船 |
国際宇宙ステーションへの物資補給を目的としていて、ファルコン9ロケットで打ち上げられます。
すでに今年の5月に無人で打ち上げられ、国際宇宙ステーションへの物資輸送に成功しているんですねー
商業的に開発され運用された宇宙船として、初めて大気圏に再突入し回収されました。
実運用に一番近い宇宙船かもしれません。
 |
| シエラネバダ社“ドリームチェイサー” |
2人~7人の乗員を国際宇宙ステーションへ輸送し、帰還させるために計画されました。
スペースシャトルを小さくしたような機体なんですが、他の宇宙船と同じくロケットで打ち上げられます。
もちろん帰りは滑空して通常の滑走路に着陸するんですねー
アトラスVによる打ち上げが予定されています。
全マイルストーンの最後には、製造着手可否を判断する詳細設計審査会(CDR)があります。
ボーイング社とスペースX社はCDRに移行するのですが、シエラネバダ社はそこまで達していないんですねー
まぁー いずれは宇宙ステーションへの乗員と物資輸送に使われる事になるんでしょうね。
もう低軌道への飛行は民間に任せても大丈夫ということでしょー (^_^)
運用コストも民間の方が有利なので、NASAには地球外軌道への飛行で頑張って欲しいですねー