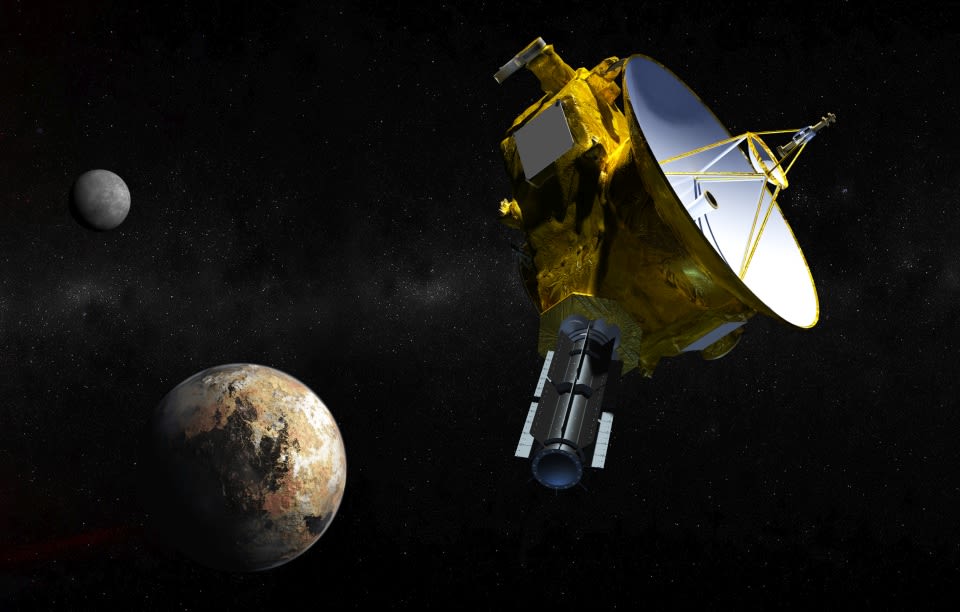“X-37B”はアメリカ空軍の無人宇宙往還機。
今回が4回目のミッションになり、
5月20日にアトラスVロケットに搭載され、無事に打ち上げられたんですねー
今回は、電気推進エンジンの試験や新素材の実験などが行われるようです。
アトラスVロケットは、ケープ・カナベラル空軍ステーションから離昇。

“X-37B”は軍事衛星になるため、飛行経路や投入された軌道は不明…
ただ、打ち上げが成功したことだけが発表されました。
ボーイング社が開発した“X-37B”は、
無人の宇宙往還機で、完全な自律飛行が可能。
また、スペースシャトルのように、
整備した上で再使用ができるように造られています。
これまでに同型機は2機が製造され、
1号機が2回、2号機が1回の飛行を行っているんですねー
今回のミッション“OTV-4”は、2号機の2回目のミッションになります。
1号機の1回目のミッション“OTV-1”は、
2010年4月22日に打ち上げられ、同年の12月3日に着陸。
2号機の1回目のミッション“OTV-2”は、
2011年3月5日に打ち上げられ、2012年6月16日に着陸しています。

そして2012年に12月11日から2014年10月17日にかけては、
1号機の2回目のミッション“OTV-3”が行われています。
“X-37B”の軌道上での滞在可能期間は、カタログスペックで270日でした。
でも“OTV-2”では469日間…
“OTV-3”では、さらに上回る674日間(約22か月間)にもわたて、
飛行し続けているんですねー

この長い滞在期間に“X-37B”が宇宙空間で何を行っているのか?
は、やっぱり不明。
なので、新しい機器や素材の実験から、宇宙兵器の試験といった説まで、
さまざまな憶測がされています。
ただ、今回の“OTV-4”に関しては、
電気推進システムの一種であるホール・スラスターの試験を行うことと、
NASAによる材料実験装置が搭載されることが発表されていたりします。
もちろん、それ以外にも何らかの試験や実験が計画されているはずですがね ^^;
今回が4回目のミッションになり、
5月20日にアトラスVロケットに搭載され、無事に打ち上げられたんですねー
今回は、電気推進エンジンの試験や新素材の実験などが行われるようです。
アトラスVロケットは、ケープ・カナベラル空軍ステーションから離昇。

“X-37B”は軍事衛星になるため、飛行経路や投入された軌道は不明…
ただ、打ち上げが成功したことだけが発表されました。
ボーイング社が開発した“X-37B”は、
無人の宇宙往還機で、完全な自律飛行が可能。
また、スペースシャトルのように、
整備した上で再使用ができるように造られています。
これまでに同型機は2機が製造され、
1号機が2回、2号機が1回の飛行を行っているんですねー
今回のミッション“OTV-4”は、2号機の2回目のミッションになります。
1号機の1回目のミッション“OTV-1”は、
2010年4月22日に打ち上げられ、同年の12月3日に着陸。
2号機の1回目のミッション“OTV-2”は、
2011年3月5日に打ち上げられ、2012年6月16日に着陸しています。

そして2012年に12月11日から2014年10月17日にかけては、
1号機の2回目のミッション“OTV-3”が行われています。
“X-37B”の軌道上での滞在可能期間は、カタログスペックで270日でした。
でも“OTV-2”では469日間…
“OTV-3”では、さらに上回る674日間(約22か月間)にもわたて、
飛行し続けているんですねー

この長い滞在期間に“X-37B”が宇宙空間で何を行っているのか?
は、やっぱり不明。
なので、新しい機器や素材の実験から、宇宙兵器の試験といった説まで、
さまざまな憶測がされています。
ただ、今回の“OTV-4”に関しては、
電気推進システムの一種であるホール・スラスターの試験を行うことと、
NASAによる材料実験装置が搭載されることが発表されていたりします。
もちろん、それ以外にも何らかの試験や実験が計画されているはずですがね ^^;