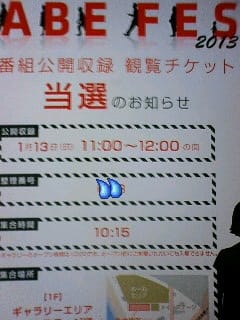先日の総選挙は「反原発」が一大ムーブメントになると思っていました。しかし、自民党が返り咲き、昔の日本がまたやって来そうです…。
本日の昼間、フォーラム福島で映画「希望の国」を鑑賞しました。
あらすじは「goo映画」さんから引用します。
***引用ここから***
東日本大震災から数年後の長島県を舞台とする。酪農を営む小野泰彦(夏八木勲)は、妻・智恵子(大谷直子)と息子・洋一(村上淳)、その妻・いずみ(神楽坂恵)と、平凡ではあるが満ち足りた暮らしを営んでいた。隣に住む鈴木健(でんでん)と妻・めい子(筒井真理子)も、恋人・ヨーコ(梶原ひかり)と遊んでばかりいる息子・ミツル(清水優)に文句を言うことはあるが、仲良く生活していた。しかしある日、長島県に大地震が発生し、続いて原発事故が起きた。そのような事態が人々の生活を一変させた。警戒区域が指定され、鈴木家は強制退避が命じられたが、道一本隔てた小野家は非難区域外だった。泰彦は、洋一夫婦を自主的に避難させるが、自らは住み慣れた家に留まった。その後、泰彦の家も避難区域に指定され、強制退避の日が迫る中、泰彦は家を出ようとはしない。その頃、避難所で暮らしていた鈴木家の息子・ミツルと恋人のヨーコは、瓦礫だらけの海沿いの街で、消息のつかめないヨーコの家族を探して歩き続けていた。果たして、原発に翻弄される人々に明るい未来は訪れるのか……。
***引用ここまで***
東日本大震災の数年後に、東電福島第1原発の事故級の原発事故が再び起きた…という設定の落ち着いたテンポの映画です。園子温監督といったらエキセントリックというか不条理ものっぽい映画の監督だとの印象があります。事故後、すぐに小野家の庭に原発から20km圏内と20km圏外の境目のバリケードが築かれたり、地震と津波に襲われたゴーストタウンを野生の牛やヤギが散歩していたり、おなかに子どもを宿していることが分かったいずみが防護服を着たりと、もしかしたら観客はそんなオーバーなと思うかも知れません。でも、これは不条理劇でも何でもなく、福島の現実なのです。事故当時そうだったし、今も解決されずに残っている問題も数多くあります。普通、「おなかに赤ちゃんがいますよ。」と言われたらおめでたいことなのですが、これが不安の始まりになります。「放射線の影響はないのかしら?」「将来、結婚できるのかしら? そして、子どもを産めるのかしら?」と母親たちの悩みは今もふくらみ続けています。いずみの悩みは福島の母親たちの悩みです。夏でも汗だくでマスクをしたり、どんなに暑くても長袖のコートみたいな厚手の服を着たりと、次世代を守ろうとしている母性を見てきました。
フィクションという形でありながら、この映画に描かれるエピソード一つ一つ(例えば、車が「福島」ナンバーなのでガソリンスタンドが被曝を恐れて給油してくれないとか、マスコミが何も伝えていない時期に防護服姿の警察官や自衛隊がやってきたこととか、作物や家畜が放射線で汚染されて自殺してしまう農家や酪農家がいたこととか。)が震災当時に口コミで流れてきたこと、地元新聞で報じられていたことそのまんまで、あの苦しかった時期を思い出し、涙ぐんでしまいました。福島の住民にとって、これはノンフィクションなのです。はっきり言って、園監督らしさが、現実に起きてしまった不条理にすっかり食われています。それだけに何故に「『第2の』東電福島第1原発事故」と半端な設定にしたのだろうと思いました。「長島県」などという架空の県を作らずに、今回の事故を真っ正面に描いて欲しかったです。映画を見ていると、事故を起こした原発に近い「楢葉町」などの実在の土地が出てきます。描き方の半端さが悔やまれます。
物語のラスト近く、若夫婦が放射線を恐れて遠くの町へ避難し、安堵の表情を浮かべます。しかし、それも束の間、洋一の線量計が警報音を鳴らし始めます。映画タイトルに反して「希望なき祖国」。「いざというときは国も県も市も町も村も信じられない。」これが現実なのです。
☆ 総合得点 85点
本日の昼間、フォーラム福島で映画「希望の国」を鑑賞しました。
あらすじは「goo映画」さんから引用します。
***引用ここから***
東日本大震災から数年後の長島県を舞台とする。酪農を営む小野泰彦(夏八木勲)は、妻・智恵子(大谷直子)と息子・洋一(村上淳)、その妻・いずみ(神楽坂恵)と、平凡ではあるが満ち足りた暮らしを営んでいた。隣に住む鈴木健(でんでん)と妻・めい子(筒井真理子)も、恋人・ヨーコ(梶原ひかり)と遊んでばかりいる息子・ミツル(清水優)に文句を言うことはあるが、仲良く生活していた。しかしある日、長島県に大地震が発生し、続いて原発事故が起きた。そのような事態が人々の生活を一変させた。警戒区域が指定され、鈴木家は強制退避が命じられたが、道一本隔てた小野家は非難区域外だった。泰彦は、洋一夫婦を自主的に避難させるが、自らは住み慣れた家に留まった。その後、泰彦の家も避難区域に指定され、強制退避の日が迫る中、泰彦は家を出ようとはしない。その頃、避難所で暮らしていた鈴木家の息子・ミツルと恋人のヨーコは、瓦礫だらけの海沿いの街で、消息のつかめないヨーコの家族を探して歩き続けていた。果たして、原発に翻弄される人々に明るい未来は訪れるのか……。
***引用ここまで***
東日本大震災の数年後に、東電福島第1原発の事故級の原発事故が再び起きた…という設定の落ち着いたテンポの映画です。園子温監督といったらエキセントリックというか不条理ものっぽい映画の監督だとの印象があります。事故後、すぐに小野家の庭に原発から20km圏内と20km圏外の境目のバリケードが築かれたり、地震と津波に襲われたゴーストタウンを野生の牛やヤギが散歩していたり、おなかに子どもを宿していることが分かったいずみが防護服を着たりと、もしかしたら観客はそんなオーバーなと思うかも知れません。でも、これは不条理劇でも何でもなく、福島の現実なのです。事故当時そうだったし、今も解決されずに残っている問題も数多くあります。普通、「おなかに赤ちゃんがいますよ。」と言われたらおめでたいことなのですが、これが不安の始まりになります。「放射線の影響はないのかしら?」「将来、結婚できるのかしら? そして、子どもを産めるのかしら?」と母親たちの悩みは今もふくらみ続けています。いずみの悩みは福島の母親たちの悩みです。夏でも汗だくでマスクをしたり、どんなに暑くても長袖のコートみたいな厚手の服を着たりと、次世代を守ろうとしている母性を見てきました。
フィクションという形でありながら、この映画に描かれるエピソード一つ一つ(例えば、車が「福島」ナンバーなのでガソリンスタンドが被曝を恐れて給油してくれないとか、マスコミが何も伝えていない時期に防護服姿の警察官や自衛隊がやってきたこととか、作物や家畜が放射線で汚染されて自殺してしまう農家や酪農家がいたこととか。)が震災当時に口コミで流れてきたこと、地元新聞で報じられていたことそのまんまで、あの苦しかった時期を思い出し、涙ぐんでしまいました。福島の住民にとって、これはノンフィクションなのです。はっきり言って、園監督らしさが、現実に起きてしまった不条理にすっかり食われています。それだけに何故に「『第2の』東電福島第1原発事故」と半端な設定にしたのだろうと思いました。「長島県」などという架空の県を作らずに、今回の事故を真っ正面に描いて欲しかったです。映画を見ていると、事故を起こした原発に近い「楢葉町」などの実在の土地が出てきます。描き方の半端さが悔やまれます。
物語のラスト近く、若夫婦が放射線を恐れて遠くの町へ避難し、安堵の表情を浮かべます。しかし、それも束の間、洋一の線量計が警報音を鳴らし始めます。映画タイトルに反して「希望なき祖国」。「いざというときは国も県も市も町も村も信じられない。」これが現実なのです。
☆ 総合得点 85点