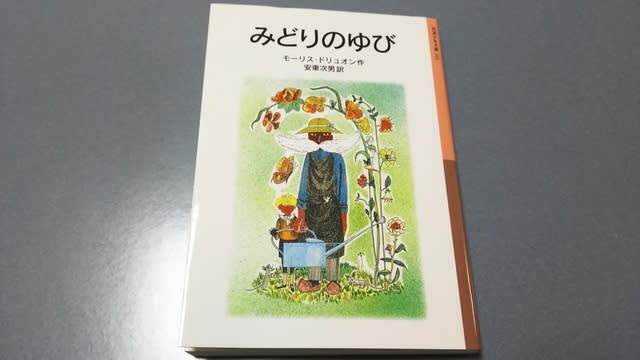
今回ご紹介するのは「みどりのゆび」(著:モーリス・ドリュオン 訳:安東次男)です。
-----内容-----
裕福に暮らすチト少年は、お父さんが兵器を作る人だったことを知り、驚きました。
じぶんが不思議な〈みどりのゆび〉をもっていることに気づいた少年は、町じゅうに花を咲かせます。
チトって、だれだったのでしょう?
-----感想-----
フランスの児童文学を読んでみました。
小学校4~5年以上向けで、イラストがたくさんあり西洋の人や町の雰囲気を掴みやすいです。
チトという男の子が生まれたところから物語は始まります。
男の子は最初、キリスト教の教会でフランソワ=バチストという名前をつけてもらいます。
ところが名前をつけた人達が何という名前をつけたか忘れてしまい、新たに「チト」という名前で呼ばれることになります。
チトのお父さんとお母さんは物凄い美男美女でさらにお金持ちで、家には雇っている掃除係、料理係、庭師などがいます。
お金持ちの家でチトは何不自由なく幸せに暮らしています。
序盤を読んでいて、主人公がこんなに恵まれた環境で暮らす児童文学は珍しいなと思いました。
チトはミルポワルという町で生まれました。
世界中に名の知れた町で、鉄砲や大砲などを作っています。
そしてチトのお父さんは鉄砲や大砲などの商人で、ミルポワルで工場を運営しています。
当初お父さんとお母さんはチトを学校に行かせず家で教育をしていましたが、チトが8歳になった時、お母さんが学校に行かせることにします。
しかしチトは授業で掛け算を見るとなぜか眠くなって眠てしまい、何度やっても寝てしまう状態が続き、三日目には「この子は学校では面倒を見られない」と言われ家に帰されてしまいます。
「チトは他の子どもと同じではない」ということにお父さんもお母さんも戸惑います。
やがてお父さんが同じでないのなら新しいやり方で教育をしようと決断します。
チトはまず庭師のムスターシュおじいさんのところに行き庭作りのことを教えてもらうことになります。
冒頭の写真の人物で「ひげさん」とも呼ばれ、風になびく長いひげを生やしています。
チトはムスターシュおじいさんのもとで植木鉢に腐植土を入れ、そこに植物の種を蒔く作業をすることになります。
ムスターシュおじいさんは普段人間とほとんど話さない人で、作業しながら様子を見ていたチトはムスターシュおじいさんがなぜ人間とほとんど話さないのかに気づきます。
この日チトは、この年よりが人間たちにほとんど口をきかないわけが、わかりました。
ひげさんは花と話をしていたのです。
「花と話をしていた」というのはムスターシュおじいさんの花への愛情が分かる良い言葉だと思いました。
ムスターシュおじいさんは毎日丹念に花と向き合い、花が順調に育つように手助けしていました。
チトが土をつめた植木鉢全部に、たった5分で花が咲くという事件が起こります。
するとムスターシュおじいさんは「チトは緑の親指」を持っていると言います。
緑の親指を持っていると、親指が花の種に触れるだけであっという間に花を咲かせることができます。
特殊な力のため、緑の親指のことはムスターシュおじいさんとチトだけの秘密になります。
チトは次に「かみなりおじさん」と呼ばれる、何にでもすぐにかっかとなる人のところに行きます。
かみなりおじさんはお父さんからとても信頼され、工場で働く人達を監督する立場にあります。
かみなりおじさんは「町で一番大切なものは規律だ」と言います。
「規律がなければ、町も、国も、社会も、風と同じことで、長持ちしません」と言っていて、これはそのとおりだと思います。
もしみんな中が規律(法律)を無視して好き放題するようになれば、犯罪だらけの荒れた町や国になってしまいます。
かみなりおじさんとチトは規律を乱し犯罪を犯した人達が収容されている刑務所を見に行きます。
刑務所は雰囲気が暗く、収容されている人達(囚人)はチトにはとても不幸そうに見えました。
チトは囚人達が不幸でなくなるにはどうすれば良いのか考えます。
そして緑の指を使って刑務所中に花を咲かせます。
すると刑務所は明るく幸せな雰囲気になり、花がたくさん咲いて扉が閉まらなくなっても、囚人達は誰一人脱獄することなく明るく幸せな気持ちで過ごせるようになりました。
こうしてミルポワルの刑務所は世界中のお手本として引き合いに出されるようになりました。
ただしこれは理想での話で、現実には扉が開けば脱獄する囚人が現れると思います。
次にチトは貧乏な町を花でいっぱいにして明るい雰囲気にします。
町の人達は花に満ちた町を観光資源にすることにし、管理人、案内人、絵葉書売り、写真屋など、今まではなかった色々な仕事が考え出されました。
チトのおかげで貧乏だった町が活性化しました。
医者のモディベール先生を訪れた時には、凄く良いことに気がつきます。
「病気が良くなるためには、生きる望みを持つことが大切だって、分かったんです」
これはそのとおりだと思います。
病気から回復するには、本人の生きる望みが何より大事だと思います。
訪れた先で花を咲かせたりこういったことに気づいたりし、チトの活躍が次々と続いていきました。
ミルポワルで戦争の話をよく聞くようになります。
バジー国とバタン国が石油を巡って戦争を始めようとしています。
ミルポワルは両方の国に鉄砲や大砲を輸出していて、ミルポワルが作った鉄砲や大砲を使って両国が争うことにチトは驚きます。
どうしたらバジー国とバタン国の戦争が起こらないようにできるかチトは考え、緑の指を使って、バジー国とバタン国に輸出する武器に花を咲かせます。
バジー国もバタン国も届いた兵器箱を開けると鉄砲も大砲も花だらけになっていて使い物にならなくなっていることに驚きます。
おかげで両国は戦争を取り止めることになりました。
ただし輸出した兵器が使い物にならなかったことでミルポワルの評判が一気に悪くなってしまいます。
チトは対応を協議するお父さんとかみなりおじさんに、大砲の中に花を咲かせたのは僕だと打ち明けます。
ついにチトの特殊な力の秘密が大人達に知られることになりました。
何となく「魔法使いサリー」の最終回でサリーがみんなの見ている前で魔法を使ってしまう場面が思い浮かびました。
お父さんは「鉄砲や大砲を作って他国の子ども達を孤児(みなしご)にさせておきながら、自分達はチトを幸せな子どもに育てている」という今までやってきたことが間違っていたと悟ります。
お父さんとお母さんはチトの将来をどうするか考えます。
そして園芸が好きなチトがその力を生かせるように、鉄砲や大砲を作っていた工場を花作りの工場に変えることを決断します。
こうしてミルポワルは「花の町ミルポワル」と名前を変え、再び繁栄を取り戻しました。
さらにチトの身に予想外の事態が起こり、意外な形で、そして悲しくはない形で物語は幕を閉じました。
最後、「花で戦争を無くそう」という考え方について、子ども向けと大人向けにそれぞれ私の感想を記します。
日本では選挙権が18歳からなので、「17歳までの子ども向け」と「18歳からの大人向け」に分けることにします。
「17歳までの子ども向け」
もし花で戦争を無くすことができれば、とても良いことだと思います。
花を眺めていると穏やかな気持ちになります。
世界中に花が咲き、どこにも戦争が起きなくなれば嬉しいです。
「18歳からの大人向け」
大人の場合、子どもが安心して「花で戦争を無くすことができれば嬉しい」と言っていられる平和な社会を守るためにはどうするか、具体的な方策を立てることが必要です。
こちらがどんなに「兵器なんていらないから、代わりに花を咲かせましょう。争いはやめましょう」と言っても、相手が問答無用で次々と兵器を投入してきて攻撃されれば、あっという間にやられてしまいます。
このことから、「花で戦争を無くすことができれば嬉しい」という理想自体は心の中に持っていても良いと思いますが、実際には自分の国を守るために防衛力が必要です。
それは自衛隊と在日アメリカ軍となります。
私は「花で戦争を無くすことができれば嬉しい」という理想だけで突っ走って防衛力をも拒否し、その状態で戦争を仕掛けられて皆殺しにされてしまうのでは本末転倒だと思います。
しっかりとした防衛力を備え、子どもが安心して「花で戦争を無くすことができれば嬉しい」と言っていられる平和な社会を守ることが重要だと思います。
あっという間に花を咲かせることができる緑の指という発想が児童文学らしくて良いなと思いました。
また著者のモーリス・ドリュオンさんは第2次世界大戦を経験していて、その時の辛い経験が「花による反戦」という形で物語に現れていたような気もします。
最初は植木鉢に花を咲かせるところから最後は戦争にまで、上手く話が繋がっていて面白かったです。
※図書レビュー館(レビュー記事の作家ごとの一覧)を見る方はこちらをどうぞ。
※図書ランキングはこちらをどうぞ。









