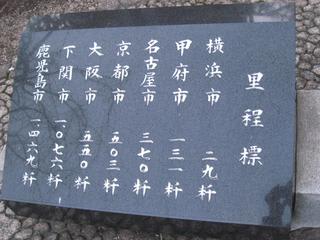今回ご紹介するのは「となり町戦争」(著:三崎亜記)です。
-----内容-----
ある日、突然にとなり町との戦争がはじまった。
だが、銃声も聞こえず、目に見える流血もなく、人々は平穏な日常を送っていた。
それでも、町の広報紙に発表される戦死者数は静かに増え続ける。
そんな戦争に現実感を抱けずにいた「僕」に、町役場から一通の任命書が届いた……。
見えない戦争を描き、第17回小説すばる新人賞を受賞した傑作。
-----感想-----
この作品は不思議なものでした。
ある日、主人公の北原修路が町の広報紙を見たら、そこには「となり町との戦争のお知らせ」という記載がありました。
どんなことになるのだろう…と思った主人公ですが、意外にも今までと同じ日常が過ぎていきました。
しかし、その次の号の広報紙で、戦死者数12人と記載されていて、戦争が確実に始まっていることを思い知らされました。
町は平穏そのものに見えるのに、水面下では既に死者が出ていたのです。
そんなある日、「戦時特別偵察業務従事者」の任命書が届いて、ついに主人公もとなり町との戦争に関わっていくことになります。
任命式を終えて、偵察業務を開始する主人公ですが、それほど日常が変わった気配はありません。
それなのに広報紙に記載される戦死者数は着々と増えていきます。
一見すると平和そのものの町のどこで戦闘が繰り広げられているのか、とても気になりました。
また、となり町との戦争に関わる一連の専門用語も面白かったです。
戦時特別会計、となり町戦争推進室、となり町戦争推進に関する条例施行規則、財団法人隣接町戦争公社などの言葉が出てきます。
これらが会話の中で使われるので、読んでいてすごく難しい会話のように思いました
いかにも戦争をしている雰囲気が出ていたと思います。
興味深かったのは、町が戦争を「事業」として推進していたことです。
予算などもあり、当たり前のように戦争が推し進められていました。
戦争をするのが利益になるというのは、おかしなことだと思います。
町の人たちも戦争を拒否しているわけではなく、戦争が行われるのは仕方ないことと思っていて、どう戦争と付き合っていくかを考えていました。
そんな世の中にはなってほしくないなと思いました。
あまり類のない、珍しいタイプの小説だったと思います。
以前読んだ「バスジャック」もそうでしたが、三崎亜記さんはこういった作風のようですね。
なかなか個性的で良いのではないでしょうか。
機会があったら他の作品も読んでみたいと思います
※図書レビュー館を見る方はこちらをどうぞ。
-----内容-----
ある日、突然にとなり町との戦争がはじまった。
だが、銃声も聞こえず、目に見える流血もなく、人々は平穏な日常を送っていた。
それでも、町の広報紙に発表される戦死者数は静かに増え続ける。
そんな戦争に現実感を抱けずにいた「僕」に、町役場から一通の任命書が届いた……。
見えない戦争を描き、第17回小説すばる新人賞を受賞した傑作。
-----感想-----
この作品は不思議なものでした。
ある日、主人公の北原修路が町の広報紙を見たら、そこには「となり町との戦争のお知らせ」という記載がありました。
どんなことになるのだろう…と思った主人公ですが、意外にも今までと同じ日常が過ぎていきました。
しかし、その次の号の広報紙で、戦死者数12人と記載されていて、戦争が確実に始まっていることを思い知らされました。
町は平穏そのものに見えるのに、水面下では既に死者が出ていたのです。
そんなある日、「戦時特別偵察業務従事者」の任命書が届いて、ついに主人公もとなり町との戦争に関わっていくことになります。
任命式を終えて、偵察業務を開始する主人公ですが、それほど日常が変わった気配はありません。
それなのに広報紙に記載される戦死者数は着々と増えていきます。
一見すると平和そのものの町のどこで戦闘が繰り広げられているのか、とても気になりました。
また、となり町との戦争に関わる一連の専門用語も面白かったです。
戦時特別会計、となり町戦争推進室、となり町戦争推進に関する条例施行規則、財団法人隣接町戦争公社などの言葉が出てきます。
これらが会話の中で使われるので、読んでいてすごく難しい会話のように思いました

いかにも戦争をしている雰囲気が出ていたと思います。
興味深かったのは、町が戦争を「事業」として推進していたことです。
予算などもあり、当たり前のように戦争が推し進められていました。
戦争をするのが利益になるというのは、おかしなことだと思います。
町の人たちも戦争を拒否しているわけではなく、戦争が行われるのは仕方ないことと思っていて、どう戦争と付き合っていくかを考えていました。
そんな世の中にはなってほしくないなと思いました。
あまり類のない、珍しいタイプの小説だったと思います。
以前読んだ「バスジャック」もそうでしたが、三崎亜記さんはこういった作風のようですね。
なかなか個性的で良いのではないでしょうか。
機会があったら他の作品も読んでみたいと思います

※図書レビュー館を見る方はこちらをどうぞ。