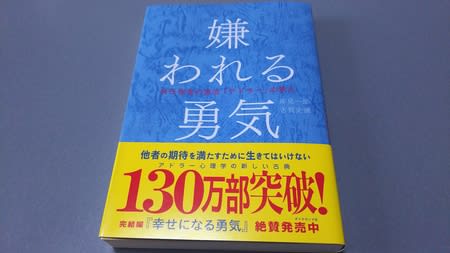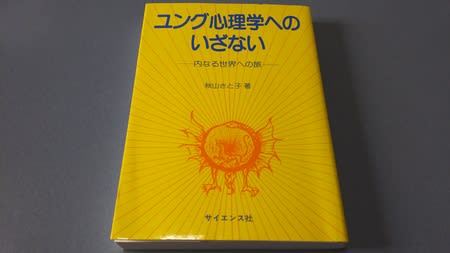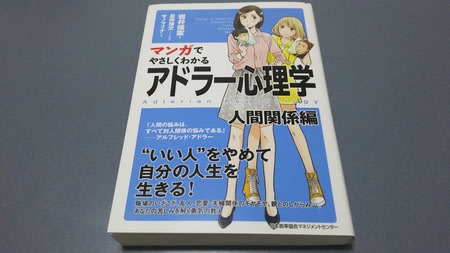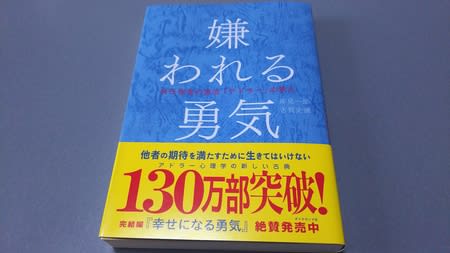
今回ご紹介するのは「嫌われる勇気」(著:岸見一郎 古賀史健)です。
-----内容-----
フロイト、ユングと並び「心理学の三大巨頭」と称され、世界的名著『人を動かす』の著者・D.カーネギーなど自己啓発のメンターたちに多大な影響を与えたアルフレッド・アドラーの思想を、1冊に凝縮!!
悩みを消し去り、幸福に生きるための具体的な「処方箋」が、この本にはすべて書かれている。
「人生が複雑なのではない。あなたが人生を複雑にし、それゆえ幸福に生きることを困難にしているのだ」
「『変われない』のではない。『変わらない』という決断を常に行っているだけだ」
「自由とは、他者から嫌われることである」
他者の期待を満たすために生きてはいけない。
アドラー心理学の新しい古典。
-----感想-----
この本は人生に悩む「青年」と、アドラー心理学を修得した哲学者「哲人」の対話という形で物語が進んでいきます。
物語の舞台は京都で、青年はこの地に一風変わった哲学者が住んで「人は変われる、世界はシンプルである、誰もが幸福になれる」という看過しがたい理想論を唱えているという噂を聞いてやってきました。
青年は実際に自分の目で哲学者の主張を確かめて、おかしな点があればその誤りを正してあげようとしていました。
世界について「誰がどう見ても矛盾に満ちた混沌ではありませんか!」という青年に対し、哲人は「それは「世界」が複雑なのではなく、ひとえに「あなた」が世界を複雑なものとしているのです」と言います。
そして「あなた自身が変われば、世界はシンプルな姿を取り戻します。問題は世界がどうであるかではなく、あなたがどうであるかです」と言っていました。
世界が複雑になるかシンプルになるかはその人の考え方次第だということのようです。
反論する青年の語り口が面白く、「ははっ、大きく出ましたね!おもしろいじゃありませんか、先生。いますぐ論破してさしあげますよ!」というような台詞をよく言っていました。
そしてことごとく哲人に論破されることになります。
哲人の専門はギリシア哲学ですが、「もうひとつの哲学」としてオーストリア出身の精神科医、アルフレッド・アドラーが20世紀初頭に創設した「アドラー心理学」も修得していました。
フロイト、ユング、アドラーは最初は一緒に精神分析学を研究していましたが、後に考え方の違いからアドラーとユングはフロイトから分派し、アドラーは個人心理学(アドラー心理学)を、ユングは分析心理学(ユング心理学)を確立します。
そして哲人にとって「アドラー心理学はギリシア哲学と同一線上にある思想であり哲学」とのことです。
哲人は過去について、「過去など関係ないというのがアドラー心理学の立場」と言っていました。
アドラー心理学では過去の「原因」ではなく、いまの「目的」を考えるとのことです。
青年には外に出た時の不安感から引きこもりになっている友人がいるのですが、哲人によると「アドラー心理学では友人は不安だから外に出られないのではなく、外に出たくないから不安という感情を作り出している」と考えるとのことです。
外に出ないという目的が先にあって、その目的を達成する手段として不安や恐怖といった感情をこしらえており、アドラー心理学ではこれを「目的論」と呼ぶとのことです。
「不安だから外に出られない」という原因論とは違いがあり、我々は原因論の住人であり続けるかぎり、一歩も前に進めませんとありました。
この目的論の考えに青年は猛反発していて、私も違和感を持ちました。
全ての事例を目的論で片付けるのは無理があるのではと思います。
哲人は「アドラー心理学では、トラウマを明確に否定します」と言っていました。
フロイト的な原因論ではトラウマを重視しますが、アドラー心理学ではトラウマは存在しないと考えるとのことです。
また、アドラーはトラウマの議論をする中で次のように語っていたとのことです。
「いかなる経験も、それ自体では成功の原因でも失敗の原因でもない。我々は自分の経験によるショックーーいわゆるトラウマーーに苦しむのではなく、経験の中から目的にかなうものを見つけ出す。自分の経験によって決定されるのではなく、経験に与える意味によって自らを決定するのである」
経験に与える意味によって自らを決定するとありますが、これは例えば、女性が男性から酷い目に遭わされて激しい精神的ショックを受けて男性不信になっている場合にもこの言葉を言うつもりなのでしょうか。
私はそういうのこそ「トラウマ」と言うのだと思いますし、トラウマの全てを「存在しない」と否定することはできないと思います。
哲人は「変わることの第一歩は知ることにある」と言っていました。
また、自分のことを好きかどうかについて、「少なくとも別人になりたいとは思いませんし、自分が「この私」であることを受け入れている」と言っていました。
自分が「この私」であることを受け入れているというのは良い考え方だと思います。
自分自身と向き合い、長所も短所も受け入れてあげるのが一番良いと思います。
哲人がアドラーの言葉で印象的なものを紹介していました。
「大切なのはなにが与えられているかではなく、与えられたものをどう使うかである」
これは良い言葉だと思います。
「この力がない」とないことを悔やむより、「今あるもの」に目を向けたほうが良いです。
不幸についての話で、哲人は「いまのあなたが不幸なのは自らの手で不幸であることを選んだからなのです」と言っていました。
これも極端な考え方だなと思います。
哲人は次のようにも言っていました。
「アドラー心理学は、勇気の心理学です。あなたが不幸なのは、過去や環境のせいではありません。ましてや能力が足りないのでもない。あなたには、ただ“勇気”が足りない。いうなれば「幸せになる勇気」が足りていないのです」
アドラー心理学の本では「勇気」という言葉が何度も出てきます。
そしてこの「勇気を持て」という考えは企業が社員への研修で好むであろうと思います。
手っ取り早く「変わるためには勇気を持て。心理学三大巨頭のアドラーもそう言っている」と言うことができるからで、何だかアドラー心理学が研修で都合よく使われるのではという懸念を持ちました。
対人関係で悩んだり傷ついたりすることについてのアドラーの言葉は興味深かったです。
「悩みを消し去るには宇宙の中にただひとりで生きるしかない」
これは良い言葉だと思いました。
実際にはそんなのは無理であり、それぞれ悩みを持ちながら生きています。
「優越コンプレックス」という言葉も興味を惹きました。
例として権力者(学級のリーダーから著名人まで)と懇意であることをアピールし、それによって自分が特別な存在であるかのように見せる人が挙げられていて、このタイプの人は見たことがあります。
一番印象的だったのが歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが不祥事を起こした際、電車の中で「私のお母さんが芸能界にコネがあってさ。海老蔵の家の詳しい情報も入ってくるの。海老蔵も馬鹿だよねー」と友達に話していた女の人でした。
かなり大きな声で話していて、それが聞こえていた私は「たぶんこの人は母親が芸能界にコネがあるのを周りに見せつけたいんだろうな」と思いました。
哲人によるとそういう人は「わたし」と権威を結びつけることによって、あたかも「わたし」が優れているかのように見せかけ偽りの優越感に浸っていて、その根底には強烈な劣等感があるとのことです。
「優越性の追求」について、哲人は「自らの足を一歩前に踏み出す意思であって、他者よりも上を目指さんとする競争の意思ではない。誰とも競争することなく、ただ前を向いて歩いていけばいい」と言っていました。
人は人、自分は自分ということで、とても良い考えだと思います。
ただし変な解釈をして「小学校の運動会の徒競走などで順位付けをするのは他者との競争になり良くない。アドラー心理学も誰とも競争することなく前を向いて歩いていけば良いと言っている。順位付けは撤廃すべきだ」というような妙な主張になりかねないので注意が必要だと思います。
この辺り、アドラー心理学は言っていることが非常に具体的であるだけに、変な解釈をして悪用する人が出るのではと懸念しています。
アドラー心理学では人間の行動面と心理面のあり方について次のように目標を掲げているとのことです。
行動面の目標
1.自立すること
2.社会と調和して暮らせること
この行動を支える心理面の目標
3.わたしには能力がある、という意識
4.人々はわたしの仲間である、という意識
また、アドラー心理学は「承認欲求」を否定するとのことです。
承認欲求とは他者から認められたいという思いのことで、この気持ちがあると自分ではなく他者の人生を生きることになるので良くないとありました。
承認欲求があるのは「適切な行動を取ったらほめてもらえる、不適切な行動を取ったら罰せられる」という賞罰教育の影響とのことです。
そしてアドラーはこうした賞罰教育を厳しく批判していたとありました。
親が子を誉めたり怒ったりして育てようとするのは間違っているとあり、なるほどと思いました。
ただ一切誉めてはいけないというのは極端ではと思います。
哲人によると、ある国に「馬を水辺に連れていくことはできるが、水を呑ませることはできない」ということわざがあり、アドラー心理学におけるカウンセリングや他者への援助全般も、そういうスタンスとのことです。
そこから哲人が言っていた「自分を変えることができるのは自分しかいない」というのはそのとおりだと思います。
自分の強い意思によって初めて変われるものだと思います。
哲人は「自由とは他者から嫌われることである」と言っていました。
「あなたが誰かに嫌われているということは、あなたが自由を公使し、自由に生きている証であり、自らの方針に従って生きていることのしるしなのです」とありました。
さらに「幸せになる勇気には、「嫌われる勇気」も含まれる」とありました。
周りから好かれるために周りの目ばかり気にしていたのではとても自由とは呼べないということであり、良い考えではあると思います。
ただし受け取り方を間違えると何でもかんでも自分勝手に振る舞って周りを凄く不快にさせる存在になりかねないので注意が必要です。
この辺り、やはりアドラー心理学は「勇気を持て」と体育会系な面があったり、極端なことを言う原理主義的な面もあり、解釈の仕方に気を付けるべきと感じています。
物語の最後、「いま、ここを真剣に生きること」について哲人と青年が熱く語り合っていました。
例えば遠い将来の受験に向けて勉強をしている「いま、ここ」も準備期間ではなくすでに本番という考え方で、これは良い考え方だと思います。
毎日少しでも良いから数式を解いたり単語を覚えたりするとそこには必ず「今日できたこと」があり、今日という一日はそのためにあったと考えるようです。
決して遠い将来の受験のために今日があるのではないとありました。
「いま、ここを真剣に生きる」とはそういった意味です。
私はこの本を読む前にユング心理学の本を読んでいるので、ユング心理学との違いを感じながら読み進めていきました。
ユング心理学は抽象的なのであまり具体的な批判はないですが、アドラー心理学は具体的なので批判点も明確になるなと思いました。
ユング心理学もアドラー心理学も心理学として目指す方向は「自分自身を生きやすくする」で同じだと思います。
その方法がユング心理学ではしなやかに、アドラー心理学では力技でという印象を持ちました。
私の感性にはユング心理学のほうが合うのでユング心理学をベースに、アドラー心理学も良い面は取り入れ、自分自身を生きやすくすることに役立てていければと思います。
※図書レビュー館(レビュー記事の作家ごとの一覧)を見る方は
こちらをどうぞ。
※図書ランキングは
こちらをどうぞ。