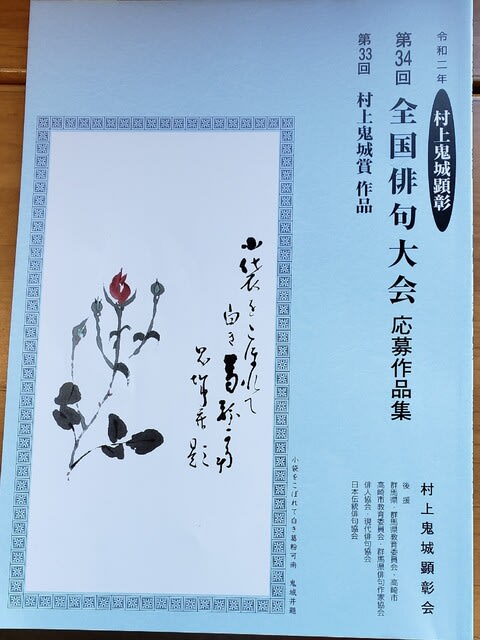寒風に声かけゆくは亡父ならむ 寺田京子
亡父の強さ逞しさをふと思う出す作者が浮かぶ
そこからつぎつぎと亡父とのさまざまな事象
いまだに亡父に励まされている自分を発見した
(小林たけし)
【冬の風】 ふゆのかぜ
◇「寒風」
冬に吹く風全般を指すが、とりわけ太平洋岸では北西や西からの季節風に代表される。しかし、語感のやわらかさは冷たさ厳しさを必要以上に強調してはおらず、むしろやさしさの窺えることさえある。
例句 作者
寒風の荷役の船尾沖に向け 右城暮石
寒風と魚のやうにすれちがふ 大木あまり
寒風に芹摘む少女見失ふ 沢木欣一
風寒し不二にもそぶく小窓かな 一茶
冬の風人生誤算なからんや 飯田蛇笏
青空に寒風おのれはためけり 中村草田男
中空に月吹上げよ冬の風 阿部次郎
寒風の荷役の船尾沖に向け 右城暮石
寒風と魚のやうにすれちがふ 大木あまり
寒風に芹摘む少女見失ふ 沢木欣一
風寒し不二にもそぶく小窓かな 一茶
冬の風人生誤算なからんや 飯田蛇笏
青空に寒風おのれはためけり 中村草田男
中空に月吹上げよ冬の風 阿部次郎