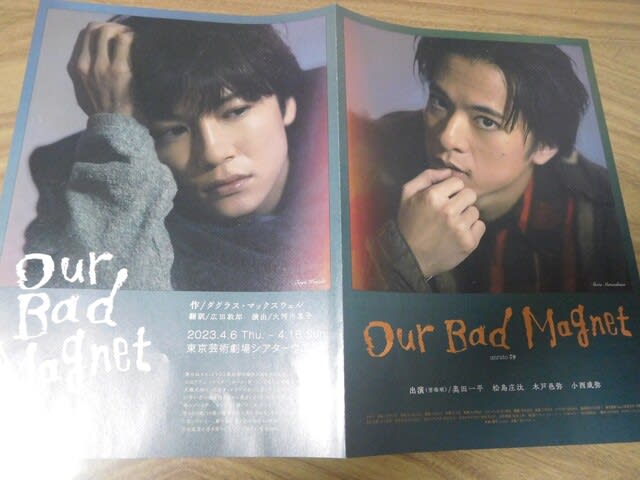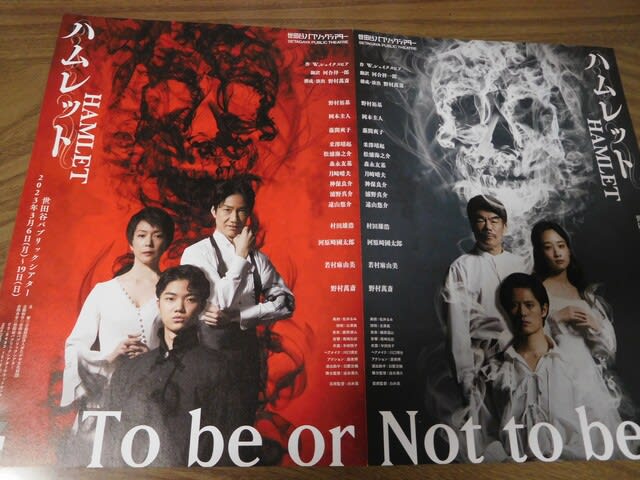6月22日パルコ劇場で、太宰治作「新ハムレット」を見た(上演台本・演出:五戸真理枝)。


太宰治が初めて書き下ろした長編小説は、『ハムレット』のパロディだった・・・。
共感度100%の日本人的な”新しい”ハムレットがここに誕生!(チラシより)。
太宰治が昭和16年(1941年)に戯曲形式の小説として書いた作品の舞台化。
舞台右奥から左手前にかけて、灰白色の大きな石の床と何段かの階段。
始めに全員で、原作の「はしがき」を輪読。
あらかじめ読んで臨んだ者としては余計だったが、観客に知っておいてほしいという気持ちはわかる。
驚いたことに、ハムレットは薄いピンク色のジャージの上下。途中で黒い上着を上から羽織るが。
全体に、衣装がいけない。おふざけなのか、という感じ。
オフィーリアは中学校の制服のような丈の短いジャンパースカート。袖が異様に長く、先にフリルが一杯ついている。
王と王妃は妙な金の冠をかぶり、服は白と赤でちゃちな感じ。
これはシェイクスピアではありません、ということを視覚的にも伝えたいのだろうが、何だか安っぽい。
台本は原作に忠実で好感が持てる。
ガートルード役の松下由樹が好演。
ポローニアス役の池田成志は、まさにはまり役。
そもそもこの作品ではポローニアスが主役を食うくらい大活躍するから、このキャスティングで大正解。
ハムレット役の木村達成もいい。初めて見たが、熱演で好感が持てる。
クローディアス役の平田満は、途中までよかったのに、珍しく何度かセリフが出て来ず、ハラハラさせられた。
コント集団「ザ・ニュースペーパー」の言う「セリハラ」だ。
ガートルードとオフィーリアが二人だけで語り合うシーンで、王妃ガーティは裸足になって草の上(と見なした床)を歩く。
オフィーリアは妊娠中なのに、階段をピョンピョン飛び降りるのは変だ。
劇中劇に出演する3人(ハムレット・ホレイショー・ポローニアス)は、平安時代風の着物をまとう。
その時、オフィーリアは首から太鼓を下げ、亡霊(ハムレットが演じる)が語る間、ドロドロという風に、化け物的な効果音を出す。
音楽はちゃち。ラスト近くでポローニアスが殺された後、押しつけがましいドラマチックでセンチな曲が流れる。
途中、天井から赤くて丸いものがたくさん落下。
これは何?血でしょうかねえ。
蜷川幸雄演出で上空から落下したハンバーグのタネみたいなものを思い出した。
彼はこれを、戦闘シーンでよく使ったものだった。
いろいろいちゃもんをつけたが、総じて面白かった。
新聞の評は辛口で否定的だったが、評論家の評は意外と当てにならないものだと改めて思った。


太宰治が初めて書き下ろした長編小説は、『ハムレット』のパロディだった・・・。
共感度100%の日本人的な”新しい”ハムレットがここに誕生!(チラシより)。
太宰治が昭和16年(1941年)に戯曲形式の小説として書いた作品の舞台化。
舞台右奥から左手前にかけて、灰白色の大きな石の床と何段かの階段。
始めに全員で、原作の「はしがき」を輪読。
あらかじめ読んで臨んだ者としては余計だったが、観客に知っておいてほしいという気持ちはわかる。
驚いたことに、ハムレットは薄いピンク色のジャージの上下。途中で黒い上着を上から羽織るが。
全体に、衣装がいけない。おふざけなのか、という感じ。
オフィーリアは中学校の制服のような丈の短いジャンパースカート。袖が異様に長く、先にフリルが一杯ついている。
王と王妃は妙な金の冠をかぶり、服は白と赤でちゃちな感じ。
これはシェイクスピアではありません、ということを視覚的にも伝えたいのだろうが、何だか安っぽい。
台本は原作に忠実で好感が持てる。
ガートルード役の松下由樹が好演。
ポローニアス役の池田成志は、まさにはまり役。
そもそもこの作品ではポローニアスが主役を食うくらい大活躍するから、このキャスティングで大正解。
ハムレット役の木村達成もいい。初めて見たが、熱演で好感が持てる。
クローディアス役の平田満は、途中までよかったのに、珍しく何度かセリフが出て来ず、ハラハラさせられた。
コント集団「ザ・ニュースペーパー」の言う「セリハラ」だ。
ガートルードとオフィーリアが二人だけで語り合うシーンで、王妃ガーティは裸足になって草の上(と見なした床)を歩く。
オフィーリアは妊娠中なのに、階段をピョンピョン飛び降りるのは変だ。
劇中劇に出演する3人(ハムレット・ホレイショー・ポローニアス)は、平安時代風の着物をまとう。
その時、オフィーリアは首から太鼓を下げ、亡霊(ハムレットが演じる)が語る間、ドロドロという風に、化け物的な効果音を出す。
音楽はちゃち。ラスト近くでポローニアスが殺された後、押しつけがましいドラマチックでセンチな曲が流れる。
途中、天井から赤くて丸いものがたくさん落下。
これは何?血でしょうかねえ。
蜷川幸雄演出で上空から落下したハンバーグのタネみたいなものを思い出した。
彼はこれを、戦闘シーンでよく使ったものだった。
いろいろいちゃもんをつけたが、総じて面白かった。
新聞の評は辛口で否定的だったが、評論家の評は意外と当てにならないものだと改めて思った。