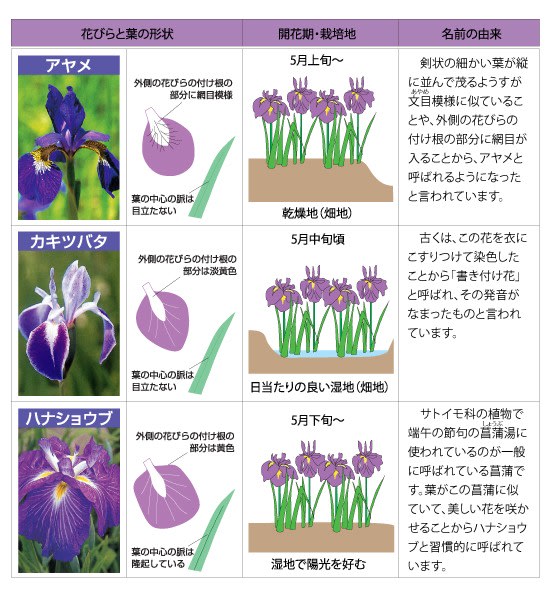令和4年5月24日(火)
万 緑

濃淡の様々な緑が、見渡す限り一面の深い緑色となり
真夏の草木が生い茂る季節へとむかう。
自然が最も生命力を示し、見るからに輝いてみえる。
中国の王安石の漢詩の「石榴詩」に、「万緑叢中紅一点」
の句があり、ここか万緑」の語が生まれた。
万緑を季語として定着させたのは俳人中村草田男と言われ
「万緑の中や吾子の歯生え初むる」の句の中で詠まれたる
万緑は「万緑の中でみどり子のまっ白なかわいい歯が生え
る。 すなわち万緑を背景としてみどり子の口中に生えた
白い歯は、生命力が凝集したものにほかならない。そこに
は作者の血が脈打っていることを、読者は感じとっている
のである。(新日本俳句大歳時記・俳人伊藤敬子句評より)
中村公園(名古屋市中村区)

地下鉄東山線「中村公園駅」を降りると、大通りに真っ赤
で大きな鳥居がある。

潜りけ真直ぐ北へ進むと中村公園に出る。

公園の前にも鳥居があり、右手には、「日吉とその仲間達」
という像が在る。

豊臣秀吉の幼名(日吉丸)は貧しい農民の子で、その頃の像
と思われる。

其処から更に北へ進むと正面に「豊国神社」がある。
この地の英傑「豊臣秀吉」を祀る神社で、1833年(明
治16年)に建てられた。

中村公園は1901年(明治34年)に開園し、この敷地
内の神社を囲むように配置される。

毎年5月に「太閤まつり」が催しされ、秀吉の旗印「千成
瓢箪」を象った神輿が境内を練り歩く。

豊国神社の左手に「ひょうたん池」があり、この池も秀吉
に肖って名付けたようである。
その北側奥には、歌舞伎役者の初代中村勘三郎の生誕像が
が建てられた。 初代勘三郎は1598年(慶長3年)に
当地(中村)に生まれ後に江戸に出て、猿若勘三郎を名乗
り、猿若座(中村座)を立ちあげた。

2017年(平成29年)に、中村勘九郎、七之助兄弟を
迎え、初代の像の「お披露目式」が行われた。
ひょうたん池の西側には「中村公園文化プラザ」がある。

1階に図書館、2階に秀吉記念館、3階には文化小劇場が
在る。 毎年「歌声サロン」(喫茶)が開演されたが、
コロナ過で、中止となってしまった。
中村公園は木々の緑に包まれ、都会の喧騒を暫し忘れて、
清々しい気分となる、ホット出来る空間である。
今日の1句
万緑の中ためらはず深呼吸 ヤギ爺