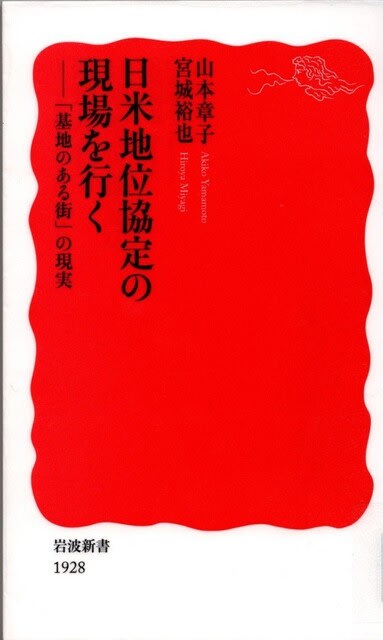米軍基地があるゆえの様々な問題、特に国内法規が適用されないことによる市民生活への影響や人権問題の存在が指摘され続けてきた。基地が集中している沖縄に目が行きがちだが、本を手にして驚くのは全国に点在する在日米軍施設・区域の数の多さ。面積の大小や共同使用施設も多く含まれるものの日本各地、132ヶ所にも。そこには<占領期からの米軍の特権が現在に至るまで引き継がれている>と問題提起する。日米地位協定の問題は、マスコミに取り上げられることの多い事故、事件に関わる警察捜査権や裁判権だけではない。著者は問題点を四つに整理。まず米軍の民間空港・港の使用や米軍基地の環境汚染、沖縄のコロナ感染拡大にも関係した検疫の問題など条文上の規定の問題。次いで条文の規定が守られていない問題、さらに条文に規定が無いために起きている問題、そして協定上の規定と実際の運用が異なっているために起きている問題と指摘。それらについて具体例を示す。基地外の訓練に関する制限が無いために基地間移動として飛行訓練を常態化、騒音問題や市街地での部品落下など住民生活を脅かす。そうした例を地方や首都圏の基地をめぐって深掘り、アメとムチに揺れる住民の本音をもレポートする。基地との共存共栄、国の交付金依存体質の影、街づくりのはずが人口減の引き金など複雑な事情が垣間見える。特に印象に残ったのは国防と言いながら<住民保護の欠落した南西防衛>、そして嘉手納基地に代表される沖縄の実相をあらためて知る。著者は最後に、日米地位協定が改訂されてこなかった根源として<(地方、辺境に押し付けられた米軍基地に)考える必要性も無く、関心を持たなかった我々にあるのでは>と問う。ウクライナ以降、防衛力増強とともに日米同盟の強化が声高に言われ、基地周辺住民の訴えもかき消されがちになる。この本を機会として目に触れた「日米地位協定の改定を求めて-日弁連からの提言」も読んで、深く考えてみたい。