
ちょっと雑然としておりますが、工程は順調。

先日レポートいたしました、古池改修のその後。
撮影前日に排水ポンプ止めて、一晩おいた翌朝。
湧水ポイントからの水は温かいようで、マイナス6度の下でも凍結せず。

一方の下流側は、薄氷ありました。
滝石基礎下の仮設パイプ経由で浸透したものですので、水温が失われるのでしょうね。
そして、さらに水位が下がったところで、ちょっとサプライズ。

底から出てきたのは、なんともう一層の厚めの氷。
夜間に急速に冷えて表面が厚く凍った上に、脇から湧水が漏れ出し。
氷の上に水が溜まって、その上に薄氷が出来たらしいプロセスだったと納得。

ややこしい話になりましたが、とにかく次は水止めの部。
遮水材には、池底の泥をそのまんま充填します。
これまで、現場で適当に棚田状の泥の段差を作って実験しましたので、性能には少々の自信あり。

とは申しますものの、やはり責任ある工事とするためには、要所は締めねばなりますまい。
一番の漏水ポイントは、これも現地資材ですが、粘土で丁寧に突きました。
滝というものは、水辺の華ではありますが、このような地道が作業があってこそ。

まったくもって地道そのものの、土と木で水を治めるという国造りの原点を思います。
この原点あればこそ、豊葦原の瑞穂の国の田んぼも広がり。
元気で明るい日本の歴史を、今に伝えることが出来た次第。

ちょっと既視感あるなと思ったら、登呂遺跡の畔もこんな感じでしたね。
こちらは少しトロトロですが、トロトロの泥が、しっかり支えて池となる。
水を止めたら、湧水ポイントが上流側に移動したようです。

二時間後、水位が上がってきました。
上澄みは、すっかり清らかな湧水モード。

最上流部からも、湧水が浸み出したようです。
さて、一晩明けてその結果は。
続きは、次回にレポートさせて頂きます。
☆人気ブログランキング☆ついでの一押し↓オン願い申し上げます↓↓。
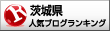


先日レポートいたしました、古池改修のその後。
撮影前日に排水ポンプ止めて、一晩おいた翌朝。
湧水ポイントからの水は温かいようで、マイナス6度の下でも凍結せず。

一方の下流側は、薄氷ありました。
滝石基礎下の仮設パイプ経由で浸透したものですので、水温が失われるのでしょうね。
そして、さらに水位が下がったところで、ちょっとサプライズ。

底から出てきたのは、なんともう一層の厚めの氷。
夜間に急速に冷えて表面が厚く凍った上に、脇から湧水が漏れ出し。
氷の上に水が溜まって、その上に薄氷が出来たらしいプロセスだったと納得。

ややこしい話になりましたが、とにかく次は水止めの部。
遮水材には、池底の泥をそのまんま充填します。
これまで、現場で適当に棚田状の泥の段差を作って実験しましたので、性能には少々の自信あり。

とは申しますものの、やはり責任ある工事とするためには、要所は締めねばなりますまい。
一番の漏水ポイントは、これも現地資材ですが、粘土で丁寧に突きました。
滝というものは、水辺の華ではありますが、このような地道が作業があってこそ。

まったくもって地道そのものの、土と木で水を治めるという国造りの原点を思います。
この原点あればこそ、豊葦原の瑞穂の国の田んぼも広がり。
元気で明るい日本の歴史を、今に伝えることが出来た次第。

ちょっと既視感あるなと思ったら、登呂遺跡の畔もこんな感じでしたね。
こちらは少しトロトロですが、トロトロの泥が、しっかり支えて池となる。
水を止めたら、湧水ポイントが上流側に移動したようです。

二時間後、水位が上がってきました。
上澄みは、すっかり清らかな湧水モード。

最上流部からも、湧水が浸み出したようです。
さて、一晩明けてその結果は。
続きは、次回にレポートさせて頂きます。
☆人気ブログランキング☆ついでの一押し↓オン願い申し上げます↓↓。





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます