伊勢崎賢治の『国際貢献のウソ』を読んだ。
NGOに所属して、東ティモールやシエラレネオ、アフガニスタンで武装解除を指揮してきた、国際貢献の第一線で活動していた筆者が、日本の国際貢献の現実と問題点、そして提言を記している。
これまで、僕はどうも一部の国際貢献という活動に対してもやもやした疑問を持っていた。
日本人が発展途上国へ出かけて行って、豊かになる方法を教える。
うーん…
日本人って、そんなに豊かになる方法を知っているのか?
効率のいい生活を送る方法は教えられても、豊かな人生を送る方法を教えられるのか?
もちろん、乳児死亡率を減らすための医療活動や、食糧危機に対する支援、エイズを防ぐ啓蒙活動など、直接命に関わる活動は大切だと思う。
でも、これまで聞いてきた活動の中には、必ずしもそれなしでも途上国の人は生活していくことができ、それでも日本人が現地へ行って、手取り足取り教えている、そんなものがある。
本書は、そんなもやもやした疑問を、雲が晴れるようにクリアにしてくれた。
一つ目。
農業にせよ、教育にせよ、医療保健にせよ、開発援助に必要な専門家は現地に十分いるということ。
問題なのは、彼らがその国の発展のために必要な場所で働くことができず、職にあぶれていることなのだ。
だから、日本人(というより、世界のNGO)に求められるのは、一人の有能なマネージャーを派遣し、それらの専門家を集め、必要な場所で力が発揮できるようにマネージすることである。
日本人が何人も現場へ赴き、各地方で技術を教えて回るというのは、日本人に求められていることではない。
二つ目。
NGOの産業構造は、そのNGOの活動に賛同する先進国の寄付者からお金をもらい、そこから自分たちの取り分を引いたものを途上国に落とすことである。
またNGOは、お金をもらった見返りに、寄付者へプロジェクトの成果を情報として渡すことも必要である。
これによって、寄付者はお金と引き替えにその情報で満足感を得る。
つまり、NGOは情報を売買するサービス業とさえ言えるのである。
そして、その商品である情報の源は途上国の貧困なのだ。
よって、NGOはこの貧困という商品を情報として寄付者へ発信する中間業者とも言えるのだ。
これまでもやもやしていたNGOの構造。
まるで、国際貢献に身をささげた聖人たちの集まりのようだったNGOが、ようやく身近な地に足の着いた組織に見えてきた。
(ただし、上記のような構造で存続しているNGOは日本ではわずかで、多くが国や国連からの補助金で活動している、という問題はある)
欧米では、NGOが人気の就職先で、寄付者も大勢いる。だから立派な産業として成り立っている。
それに対して、日本ではNGOが人気の就職先とはとても言えず、また寄付者も非常に少ない。
これは、NGOという組織の産業構造が一般に理解されておらず、僕のように奇特な聖人の集まりと思っている人が大勢いるからではないだろうか。
また、「青年海外協力隊へ行く前に、青年国内協力隊として、国内の被災地復興や過疎化した村に住んで村おこしをすべき」という筆者の提言も印象に残った。
ともすれば、過激で極端な意見に聞こえる本書は、それでも国際貢献の第一線で活躍していた筆者の言葉であることに意味があると思う。
少なくとも、危機に瀕している日本のNGOが今後も存続、発展していくためにはいろいろな改革が必要であるようだ。
NGOに所属して、東ティモールやシエラレネオ、アフガニスタンで武装解除を指揮してきた、国際貢献の第一線で活動していた筆者が、日本の国際貢献の現実と問題点、そして提言を記している。
これまで、僕はどうも一部の国際貢献という活動に対してもやもやした疑問を持っていた。
日本人が発展途上国へ出かけて行って、豊かになる方法を教える。
うーん…
日本人って、そんなに豊かになる方法を知っているのか?
効率のいい生活を送る方法は教えられても、豊かな人生を送る方法を教えられるのか?
もちろん、乳児死亡率を減らすための医療活動や、食糧危機に対する支援、エイズを防ぐ啓蒙活動など、直接命に関わる活動は大切だと思う。
でも、これまで聞いてきた活動の中には、必ずしもそれなしでも途上国の人は生活していくことができ、それでも日本人が現地へ行って、手取り足取り教えている、そんなものがある。
本書は、そんなもやもやした疑問を、雲が晴れるようにクリアにしてくれた。
一つ目。
農業にせよ、教育にせよ、医療保健にせよ、開発援助に必要な専門家は現地に十分いるということ。
問題なのは、彼らがその国の発展のために必要な場所で働くことができず、職にあぶれていることなのだ。
だから、日本人(というより、世界のNGO)に求められるのは、一人の有能なマネージャーを派遣し、それらの専門家を集め、必要な場所で力が発揮できるようにマネージすることである。
日本人が何人も現場へ赴き、各地方で技術を教えて回るというのは、日本人に求められていることではない。
二つ目。
NGOの産業構造は、そのNGOの活動に賛同する先進国の寄付者からお金をもらい、そこから自分たちの取り分を引いたものを途上国に落とすことである。
またNGOは、お金をもらった見返りに、寄付者へプロジェクトの成果を情報として渡すことも必要である。
これによって、寄付者はお金と引き替えにその情報で満足感を得る。
つまり、NGOは情報を売買するサービス業とさえ言えるのである。
そして、その商品である情報の源は途上国の貧困なのだ。
よって、NGOはこの貧困という商品を情報として寄付者へ発信する中間業者とも言えるのだ。
これまでもやもやしていたNGOの構造。
まるで、国際貢献に身をささげた聖人たちの集まりのようだったNGOが、ようやく身近な地に足の着いた組織に見えてきた。
(ただし、上記のような構造で存続しているNGOは日本ではわずかで、多くが国や国連からの補助金で活動している、という問題はある)
欧米では、NGOが人気の就職先で、寄付者も大勢いる。だから立派な産業として成り立っている。
それに対して、日本ではNGOが人気の就職先とはとても言えず、また寄付者も非常に少ない。
これは、NGOという組織の産業構造が一般に理解されておらず、僕のように奇特な聖人の集まりと思っている人が大勢いるからではないだろうか。
また、「青年海外協力隊へ行く前に、青年国内協力隊として、国内の被災地復興や過疎化した村に住んで村おこしをすべき」という筆者の提言も印象に残った。
ともすれば、過激で極端な意見に聞こえる本書は、それでも国際貢献の第一線で活躍していた筆者の言葉であることに意味があると思う。
少なくとも、危機に瀕している日本のNGOが今後も存続、発展していくためにはいろいろな改革が必要であるようだ。













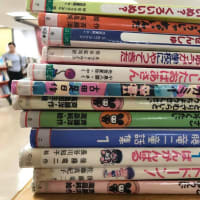






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます