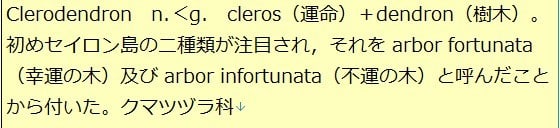意外に思われるかもしれませんが、アオイ科の、それもインドから来たらしい花を2つ紹介します。
ワタ

西尾市憩の農園の畑にて。
畑のワタは いい写真が撮れなかったので、以下、バックナンバーより

去年11月、Sさんの菜園にて。

かつては「三河木綿」というブランドがあって、関連ブログ記事に「 799年に現在の愛知県西尾市の辺りに漂着したインド人が、日本に初めて綿を伝授した」という記述があります。
三河地方も早くから綿作が行われていた有力な産地であったことは間違いないとしても、実際はそれと平行して広く各地でほぼ時期を同じくして栽培が行われるようになったのではないかと考えられます。

風船みたいなワタの実

立派な「綿毛」が…
イチビ

こちらは 幸田町の憩いの農園にて。
イチビの「切り花」を売ってました。

少しですが、まだ花も咲いていました。

イチビは アオイ科でも イチビ属(アブチロン)の花で、フヨウ属(ハイビスカス)のような独特の花シベ構造はしてないようです。

イチビもインドが原産地です。

日本でも平安時代には既に繊維をとるために広く栽培され、江戸時代まで利用されていた。かつて栽培されたものは山村などで野生化しているのが見られるが、果実は黄白色に熟する。(wiki 「イチビ」)

この果実が面白い。(ので、切り花に?)

あの花から、こんな実ができるなんて、想像できないですよね
「近年畑や空き地の雑草として急に増えてきたが、これは果実が黒くなり、遺伝的にも在来種と異なることが示されている。アメリカから飼料などに混って最近侵入し、繁殖力が強いため短期間で増えたと考えられている」(同上)
「日本の侵略的外来種ワースト100に選定されている。また、外来生物法により要注意外来生物に指定されている。」(同上)
インドというと今は コロナウィルス変異株の代名詞ですけど。。。
ワタ

西尾市憩の農園の畑にて。
畑のワタは いい写真が撮れなかったので、以下、バックナンバーより

去年11月、Sさんの菜園にて。

かつては「三河木綿」というブランドがあって、関連ブログ記事に「 799年に現在の愛知県西尾市の辺りに漂着したインド人が、日本に初めて綿を伝授した」という記述があります。
三河地方も早くから綿作が行われていた有力な産地であったことは間違いないとしても、実際はそれと平行して広く各地でほぼ時期を同じくして栽培が行われるようになったのではないかと考えられます。

風船みたいなワタの実

立派な「綿毛」が…
イチビ

こちらは 幸田町の憩いの農園にて。
イチビの「切り花」を売ってました。

少しですが、まだ花も咲いていました。

イチビは アオイ科でも イチビ属(アブチロン)の花で、フヨウ属(ハイビスカス)のような独特の花シベ構造はしてないようです。

イチビもインドが原産地です。

日本でも平安時代には既に繊維をとるために広く栽培され、江戸時代まで利用されていた。かつて栽培されたものは山村などで野生化しているのが見られるが、果実は黄白色に熟する。(wiki 「イチビ」)

この果実が面白い。(ので、切り花に?)

あの花から、こんな実ができるなんて、想像できないですよね
「近年畑や空き地の雑草として急に増えてきたが、これは果実が黒くなり、遺伝的にも在来種と異なることが示されている。アメリカから飼料などに混って最近侵入し、繁殖力が強いため短期間で増えたと考えられている」(同上)
「日本の侵略的外来種ワースト100に選定されている。また、外来生物法により要注意外来生物に指定されている。」(同上)
インドというと今は コロナウィルス変異株の代名詞ですけど。。。