★耳鼻科の検査★・・・(私の場合)
<1>標準純音聴力検査(2種類)
① 気導聴力・・・外耳道から鼓膜、耳小骨を通って内耳に伝わる検査。
② 骨導聴力・・・頭部から骨を伝わって内耳を振動させる検査。
◆骨導聴力が正常で、気導聴力が低下している・・・伝音性難聴
◆骨導聴力と気導聴力が同じように低下している・・・感音性難聴
私の場合は、感音性難聴だった。
<2>鼓膜検査
初診のときは、<1><2>の検査をするが、
鼓膜に異常が認められない限り、
再診からの検査は、標準純音聴力検査のみとなる。
<3>MRI検査
投薬で改善が見られない場合は、MRI検査をして、
頭の検査をする。
≪標準純音聴力検査とは?≫
検査は、聴覚検査室の無響室にて、
ヘッドホンをつけ、行われる。
音が聴こえたら、自分でボタンを押す。
痛みはないけれど、緊張の時間。
所要時間は、両耳で10分くらい。
日常生活の中で聞こえてくる音は、
ホントに様々な周波数が混じった音だが、
この検査で使われる純音は、
ハ調のドの音に近い規則的な周波数の音。
オージーオメータという機械を使って、純音を発し、
125、250、500、1000、2000、4000、8000Hz(ヘルツ)の
7周波数ごとに、患者の聞きとり検査を行う。
そして、その後、
聴力図(オージオグラム)を示し、
聴覚曲線ができる。
患者がどのくらい音の大きさで聴こえ始めるか、
最小可聴域値を調べることができる。
≪正常な人の聴覚曲線≫(↓)(イメージだけでも・・)
【縦軸・・dB(デシベル) 横軸・・Hz(ヘルツ)】
【青線・・気導曲線 赤線・・骨導曲線】
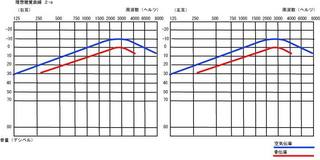
≪ヘルツ(Hz)とは?≫
振動する周波数のSI単位で、
1秒間に1周期の振動数を一ヘルツとする。
正常な聴力で聞き取ることができる音域は1000~20000Hzの間。
≪デシベル(dB)とは?≫
聞こえ始めの音の大きさ(聴覚レベル)の単位をデシベル(dB)という。
数字が大きくなればなるほど、悪い状態。
正常聴力の場合は、0~30dB近辺で、
難聴の程度が強くなるほど、この値が大きくなる。
通常、30~50dB以上が軽度難聴、
50~70dB以上が中度難聴、
70~90dB以上が高度難聴、
専門家はその曲線の特徴をみて、
聴力はどのくらいの値か、
何が原因で難聴になっているのか診断する。
4000Hzの気導聴力、骨導聴力が特に低下し、
聴力曲線がV字型の場合は、騒音性難聴の可能性が高く、
また、4000Hzや8000Hzの高い周波数に聴力低下を示すときは、薬物性難聴。
2000Hz以上でゆるやかに低下する場合は、老人性難聴など・・・。
しかし、なかなか原因がわからない場合が多く、
私の、この1ヶ月余りの聴覚検査をみても、
最初は聴覚レベルもよくて、「軽度の突発性難聴」と診断され、
次に、内耳性難聴と変わり、
その後、変動性難聴と診断された。
ステロイドにより、一時、少し改善されていたのに、
投薬を中止してからが悪くなってきて、
2週間、他の治療後、
再びステロイド治療を開始しても、副作用ばかりで、効き目がない。
ここ数回は、どんどん悪くなる一方・・・。
「標準純音聴力検査」は、
耳鼻科の診断には欠かせない検査だと思います。
★お知らせ★
今日の耳鼻科の診察については、今夜、書きます。
最新の画像[もっと見る]
-
 武者小路実篤「尊敬すべき幸福な人」
8時間前
武者小路実篤「尊敬すべき幸福な人」
8時間前
-
 武者小路実篤「尊敬すべき幸福な人」
8時間前
武者小路実篤「尊敬すべき幸福な人」
8時間前
-
 ☆2025年2月1日⚾カープキャンプイン☆
2日前
☆2025年2月1日⚾カープキャンプイン☆
2日前
-
 ☆2025年2月1日⚾カープキャンプイン☆
2日前
☆2025年2月1日⚾カープキャンプイン☆
2日前
-
 ☆2025年2月1日⚾カープキャンプイン☆
2日前
☆2025年2月1日⚾カープキャンプイン☆
2日前
-
 ☆2025年2月1日⚾カープキャンプイン☆
2日前
☆2025年2月1日⚾カープキャンプイン☆
2日前
-
 斎藤茂太「自分をあきらめない」
4日前
斎藤茂太「自分をあきらめない」
4日前
-
 斎藤茂太「自分をあきらめない」
4日前
斎藤茂太「自分をあきらめない」
4日前
-
 ココ・シャネル「生き生きと・・・」
6日前
ココ・シャネル「生き生きと・・・」
6日前
-
 瀬戸内寂聴「にっこり ♪♪」
1週間前
瀬戸内寂聴「にっこり ♪♪」
1週間前















