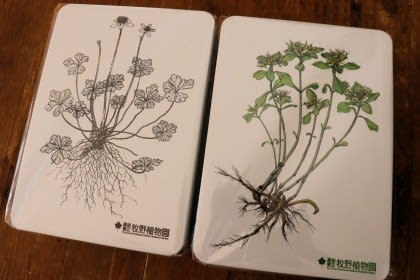オニクルミ。今年は7つ。

ノイバラの赤い実。

外に出ると必ずついてくるトビツカミ(ひっつき虫)の類。
上はエプロンについたヌスビトハギの実。表面にかぎ状の毛が生えていて、マジックテープのようにくっつく。払ったくらいではなかなか落ちないので、ひとつひとつ指でつまみ取るしかない。

猫がつけてくるチヂミザサの種は、さらっとした見かけによらず、粘液でぺたぺたくっつく。粒が小さいので取るのが面倒だけれど、乾けば自然に落ちるので、猫が寝ていたあとによく残っている。
あの手この手で遠くへ行こうとする植物たち。

これ、これ! これが見たかったのだ。キツネササゲ(ノササゲ)の実。
ヤブマメほどどこにでもある草ではないし、花や実のつく率も高くない気がする。

まだ半分緑色。これからもっといい色になるので、忘れずにまた来てみましょう。

センリョウ。ちょっとびっくりするほど実が多い。
いまごろ赤くなってしまって、お正月までもつかしら。

咲き始めたヒメツルソバと、左はギンレイカ(たぶん)。ギンレイカは、この夏は花をつけなかったけれど、ちゃんといてくれて嬉しい。
銀鈴花という名前はこの植物を正しくあらわしているとは言えないと、牧野富太郎先生は書いておられるけれど、わたしもそう思います。鈴に見立てるなら花より実のほうではないかしら。命名した人は、どうして銀鈴草にしなかったのか。ギンリョウソウとまぎらわしいから?

そして名前がまぎらわしい、こちらはミゾソバ。別名コンペイトウグサ。
以前はたくさんあったが、いつのまにか減って、気がついたら残りわずかになっていた。
恐竜が絶滅したのは、地球に小惑星が衝突したことによる環境の激変に適応できなかったため、とする説が有力だけれど、そうでない説もいろいろある。
ミゾソバがたくさん生えていた場所に、小惑星の衝突に相当するような大きな変化は起こらなかったし、他の植物に場所を取られたというふうにも見えない。意図的に駆除したわけでもない。それでもミゾソバにとっては、何らかの理由があって、居心地がわるくなったということだろう。
見かけなくなった植物は他にもある。ツルカノコソウ、アケボノソウ、センブリ、ベニバナノボロギク、ヒヨドリジョウゴなどは、わたしたちがここに住み始めた当初の先住民で、その後数年のうちに姿を消したものたちだ。
さまざまな名前を知らないキノコ類も、この10年であきらかに減った。リュウノウギク、ヒヨドリバナのように、庭の中に保護したものだけぎりぎり残っているものもある。逆に、増えたものもいろいろある。
温暖化のせいにするまでもなく、自然環境は(動植物すべてを含め)つねに流動的で、複雑に変化し、入れ替わっている。まるでヒトの細胞のように。それが生きているということ。
さてさて、コシオガマとコウヤボウキは、今年は見られるかな、どうかな。

ジョウビタキの声がにぎやか。
数日前にオスを見かけたのだが、あとから来たメスがやたらと挑発的で、窓の外の物干し竿に来たかと思えば、コマ吉のすぐ目の前に「ぱっ」と止まってみせたりする。
小さくても、飛べるというのは、すごいな。(と、コマとわたしは顔を見合わせて思ったのでした)
ジョウビタキは冬鳥で、暖かい日本で冬を過ごし、春になると北へ帰っていく。ところが近年、信州や北海道などで、春夏も日本に残って繁殖するジョウビタキが増えているそうだ。
これはなぜなのか。「温暖化の影響」では説明がつかない。猛暑の日本にとどまるより、シベリアやモンゴルの広大な原野のほうが子育てに良さそうに思えるけど、そういうわけではないのかしら。
野鳥の中ではあまり人を恐れない性格でもあり、意外と適応力が高い…というより、こだわりがないのかもしれない。それにしても「渡り」という大切な本能を、そう簡単になくしてしまえるものなのか。謎です。

早々と、越冬モードのパチ子ちゃん。鉢植えにするのは2年ぶり。
もう入院とかないので(ないよね?)ちゃんとお世話ができます。

ボクもにゅういんとかはもうヤダ。
本日の「びっくり」
いつものフェイクニュースではありませんよ。ほんとの話。
しかし、こういうのは年2回くらいバージョンアップしていかなければたちまち「過去」になってしまうのでは?
って、わたしが心配してもしょうがないけれど。
そして、この辞典を買う人はすくなくともオタクではない、と思う。(一種の「言葉オタク」ではあるかもしれない)