高校生の頃「倫理」という選択科目があり、私はそれを選ばなかったけれど、今更その内容が気になっている。
わざわざ高校の授業で学ぶ倫理とはなんだったのだろうか。
大人になって年を重ねれば重ねるほど世界のいろんなことがわかっていくのだろうと思っていたが、
少しずつ年を重ねてたくさんの知識と思しきそれらに触れれば触れるほど益々わからなくなっていく。
自分でも信じられないくらい何にもわからない。
荒れた大海で思考の渦にはまってしまったとでもいうのか。
それとも灼熱の砂漠で方向が定められた直線上をおぼつかない足取りで歩いているのだろうか。
どちらにしても嫌だな。
昼のワイド番組で弁護士が「あなたはそれが正義だと思っているのですか?」と誰かを問い詰めていた。
セ、せ、正義!?
勝手にその言葉はもう効力を持たない過去の遺物だと思っていたから、不意をつかれた。
言葉とは意味を辿っても終着地点がない不思議な生き物だ。
それをみんな無自覚に理性をもって、最大公約数として認識された意味を意味として認定してる。
もちろん「意味」は時間を経て変化もするし認識に多少のズレはあるだろうけど、修正可能な範囲内だ。
しかし倫理を扱う言葉は非常に繊細で取り扱いが特に難しい。
最大公約数がないといっても過言ではない。
それだけに皆使うのを避ける。
そういう意味ではあの弁護士はすごいのかもしれない。
自分の中にある正義を信じている。
正しいかそうでないかは横に置いて結局はそれしかないのかもしれない。
システムを理解する能力ばかりが上達して、その代わりに自分の考えが薄れていき、無機質になっていく。
そしてぼんやりと大きな何かに同化していく感覚だけが残る。
私の倫理観は多分結構崩壊している。
家のトイレに私の好きな押井守監督の『凡人として生きるということ(2008、幻冬舎新書)』という本を置いている。
トイレでしか読まないからまだ半分くらいしか進んでいないけれど、結構面白い。
内容が面白いというよりは、押井守の頑固おやじ感が面白い。
うたい文句はこうだ。
ーーーー
世の中は95%の凡人と5%の支配層で構成されている。
が、5%のために世の中はあるわけではない。
平凡な人々の日々の営みが社会であり経済なのだ。
しかし、その社会には支配層が流す「若さこそ価値がある」「友情は無欲なものだ」といったさまざまな“嘘”が“常識”としてまかり通っている。
嘘を見抜けるかどうかで僕たちは自由な凡人にも不自由な凡人にもなる。
自由な凡人人生が最も幸福で刺激的だと知る、押井哲学の真髄。
ーーーー
彼は若さこそ価値があるなんてデタラメだ!そんなデマに扇動されるな!と言い切る。
独断も独断で、明確な根拠がないのが斬新だ。
強いて言えば、理屈の根底には押井守の人生がある。
だから読んでいてとても人間臭い。
最近の傾向として何でもかんでも条理をわきまえ過ぎているのかもしれないと思う。
現実的であろうとするし、中立的であろうとする。
それは物事をより正確に捉えようとする努めだが、そのせいで「正しく」なりすぎる。
「根拠ある正しさ」を武装した戦士は一見強いが、鎧のクッション性が足りず思わぬ攻撃にあい一瞬で粉砕してしまう。
案外強いのは理不尽な人間臭さだったりして。
今こそ救世主頑固おやじ戦隊の活躍どころだ。

道端の花。
わざわざ高校の授業で学ぶ倫理とはなんだったのだろうか。
大人になって年を重ねれば重ねるほど世界のいろんなことがわかっていくのだろうと思っていたが、
少しずつ年を重ねてたくさんの知識と思しきそれらに触れれば触れるほど益々わからなくなっていく。
自分でも信じられないくらい何にもわからない。
荒れた大海で思考の渦にはまってしまったとでもいうのか。
それとも灼熱の砂漠で方向が定められた直線上をおぼつかない足取りで歩いているのだろうか。
どちらにしても嫌だな。
昼のワイド番組で弁護士が「あなたはそれが正義だと思っているのですか?」と誰かを問い詰めていた。
セ、せ、正義!?
勝手にその言葉はもう効力を持たない過去の遺物だと思っていたから、不意をつかれた。
言葉とは意味を辿っても終着地点がない不思議な生き物だ。
それをみんな無自覚に理性をもって、最大公約数として認識された意味を意味として認定してる。
もちろん「意味」は時間を経て変化もするし認識に多少のズレはあるだろうけど、修正可能な範囲内だ。
しかし倫理を扱う言葉は非常に繊細で取り扱いが特に難しい。
最大公約数がないといっても過言ではない。
それだけに皆使うのを避ける。
そういう意味ではあの弁護士はすごいのかもしれない。
自分の中にある正義を信じている。
正しいかそうでないかは横に置いて結局はそれしかないのかもしれない。
システムを理解する能力ばかりが上達して、その代わりに自分の考えが薄れていき、無機質になっていく。
そしてぼんやりと大きな何かに同化していく感覚だけが残る。
私の倫理観は多分結構崩壊している。
家のトイレに私の好きな押井守監督の『凡人として生きるということ(2008、幻冬舎新書)』という本を置いている。
トイレでしか読まないからまだ半分くらいしか進んでいないけれど、結構面白い。
内容が面白いというよりは、押井守の頑固おやじ感が面白い。
うたい文句はこうだ。
ーーーー
世の中は95%の凡人と5%の支配層で構成されている。
が、5%のために世の中はあるわけではない。
平凡な人々の日々の営みが社会であり経済なのだ。
しかし、その社会には支配層が流す「若さこそ価値がある」「友情は無欲なものだ」といったさまざまな“嘘”が“常識”としてまかり通っている。
嘘を見抜けるかどうかで僕たちは自由な凡人にも不自由な凡人にもなる。
自由な凡人人生が最も幸福で刺激的だと知る、押井哲学の真髄。
ーーーー
彼は若さこそ価値があるなんてデタラメだ!そんなデマに扇動されるな!と言い切る。
独断も独断で、明確な根拠がないのが斬新だ。
強いて言えば、理屈の根底には押井守の人生がある。
だから読んでいてとても人間臭い。
最近の傾向として何でもかんでも条理をわきまえ過ぎているのかもしれないと思う。
現実的であろうとするし、中立的であろうとする。
それは物事をより正確に捉えようとする努めだが、そのせいで「正しく」なりすぎる。
「根拠ある正しさ」を武装した戦士は一見強いが、鎧のクッション性が足りず思わぬ攻撃にあい一瞬で粉砕してしまう。
案外強いのは理不尽な人間臭さだったりして。
今こそ救世主頑固おやじ戦隊の活躍どころだ。

道端の花。












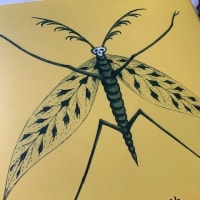
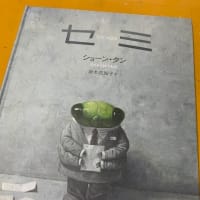



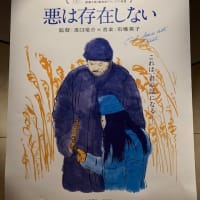








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます