










自分が長年慣れ親しんだ駅前の光景ほど、記憶に残る景色は無いと思います。通勤・通学・買い物・・いつも通る駅前の景色。高架工事や駅前再開発で、昔と随分変わってしまった駅も多い中、阪急宝塚線の「石橋駅」、現在の「石橋阪大前駅」は、今も昔の面影を残しています。

これは昭和30年(1955年)頃の石橋駅東口の景色です。現在と比べてみると・・・

何となく面影が残っているでしょう?
左端の駐車禁止の標識の左手は今も、僕が学生時代だった70年代もタクシー乗り場です。写真右側のオレンジの建物は、現在2階が学習塾になっていますが、1978年頃に当時この北摂でも大きな書店として建てられました。映画「赤穂城断絶」や「病院坂の首縊りの家」の、公開前に発売された原作のハードカバー本をここで買ったのを覚えています。また、コピー機が最初に置かれたお店もここでした。1枚30円~50円で高価でした。80年代に入ると値引き競争が始まり、1枚10円~20円に落ち着きましたが、現在と大差が無い値段というのに驚きます。今ではトナーの質が良くなり、コピーの出来上がりも当時と比較にならない程綺麗で、カラーコピーも普通となりましたが。
写真中央、日通のトラックが停まっていますが、その後ろの壁の部分は70~80年代は長く、新聞や宝くじを販売している駅の売店でした。僕は70年代、ここで大阪スポーツを買い、前夜のプロレスの結果に一喜一憂していました。また、宝くじ1枚100円を生まれて初めて「1枚だけ」買ったのもここで、それが1万円の当選!これは嬉しかった!今でも忘れることが出来ません。

1枚目と同じ日の昭和30年頃の改札のアップですが、改札左におばちゃんが座っているのが、駅の売店の初期。新聞と雑誌を当初は販売していましたが、徐々にタバコや飲料、ガムと品数が増えて行き、駅舎の1部を使ったきちんとした売店に変わって行きました。今ではローソンが駅に入って、こういう売店は消え去りました。大阪梅田の阪神百貨店前の地下通路には、こういう屋台が沢山あり、そこで新聞や雑誌、飲み物等を売っている光景が80年代まで見られました。
当時の朝のラッシュ時、サラリーマンが次々と新聞や雑誌、タバコなど複数の品物を買う中、瞬時に金額を計算して品物を渡しているおばちゃんの仕事ぶりは、今と比較すると人間業ではありませんでした。今はレジがあって自動の読み取り機までもあるのに、どれだけ待たされることか!当時はテレビで時々、駅のおばちゃんが何秒でお客を捌いているか、特集していましたね。早く捌くために、お釣りのコインを何枚単位でどのように予め積み上げて置いておくとか。
今の駅の売店の人に、当時のおばちゃんの真似をするのは絶対に不可能。あれだけ早く暗算が出来て、瞬時に手が動いて品物とお金を交換してお釣りも渡す。一流企業のオフィスで働く人でも、あんなに早く暗算をしてパソコンをタイプする人はいません。そういう優秀な人が、駅の売店で働いていたのです。昭和の人々の働きぶりは、現在とは異次元でした。
昔のスーパーのレジのおばさんも、自分の指で品物の値段を1点1点打っていたのに、今の読み取りレジよりどれだけ早かったか!レジに並んで、その遅さにイライラしたことが昔は無かった。働き方改革と言われますが、人の能力が低下しているのに、更に楽をして賃金だけが上がって行くのは如何なものでしょう。
もう1つ書いておきますと・・最近のレジはバーコードの読み取りでレジ係が、同じものを10個買っても「×10」とはせず、1個1個握って読み取る。例えばアイスクリームが溶けようとも・・。魚のお刺身でも、調理したお惣菜でも、カップ麺でも、中身があっちこっちに動こうとも、バーコードの位置を探して360度どの方向にでも品物を向ける。レジ係の賃金は上がっても、質は落ちることはあっても上がらない。買い物をするのが楽しくなく、面倒な・・・不幸な世の中になりました。
最近、本当に日本が腐っていると感じます。日本は少し前まで現在のような国ではありませんでした。僕は高齢者になりましたが、今の日本であれば可能であっても、もう1度人生をやり直したいとは思わない。あと数年で人生が終わることを、むしろ良かったと感じています。
政治に目を向けると、石破内閣・・完全な親中親韓でした。日本人を勝手に言いがかりで逮捕したり、日本人の子供を惨殺したり、日本の領土を平気で脅かす独裁国家中国に気を使う?あり得ない。皆さんの家の隣に反社組織の人が住んでいたら、ご近所さんだから仲良くしようと考えて行動しますか?

家を1歩外に出ると、歩きながら、自転車を運転しながら、車を運転しながらスマホの画面を見たり、通話をしていたり。こういう馬鹿な人間のせいで、実際にはどれだけ多くの人が交通事故に毎日巻き込まれているのでしょう。
道徳心も何もない薄汚れた人間が政治家になるから、多くの人も自分勝手な行動を取る。そういう大人を見て子供が真似をする。僕が若かったころ、成人して働いていない人間なんて、極論すれば働くことに身体的精神的に支障があって働けない人だけでした。今は犯罪を起こした人間のほとんどが若いのにまともに働いていない。だから闇バイトだとか訳の分からないことに手を染める。なんで会社勤めも企業もしていない若者が、町に溢れているのか?親は何をしているのか?
スマホを使いながら自動車を運転するのも、自転車だからと出鱈目に道路を走行し、信号も守らず人にぶつかっているのも、闇バイトに応募するのも、人の命を危険に晒す行為であり、そういう行為を考えも無しに行っている人間は馬鹿です。
こういう人が増え過ぎたのが日本という国です。そして、働かない権利だとか、結婚しないのも自由だとか言いながら、いい歳をして会社に勤めない、働いていないので車も買えないしデートも出来ない、給料が安いから結婚も出来ない。それは社会にも責任があるかも知れないけれど、そもそもは個人の責任です。それで楽しいのか?というような生活を送る若者が多い。それどころが犯罪に走る若者がどんどん増えている。
こういう若者を減らすのが地域においては大人の役目、広い意味では政治です。その政治を行う政治家が汚いことしかやっていないのだから、もうどうしようもありません。岸田元総理が外遊でどれほどの莫大なお金を世界中で無意味にばら撒いたか?あのお金があれば日本中の地震や災害の被災者が、どれほど救われるか!そのお金を結婚した男女のカップルに祝い金として渡せば、どれだけの男女が一緒に住むか。一緒に住めば子供も生まれる。
子供を持てるのは今やお金に余裕のある家です。そこに子供がいるからとお金を配っても子供は増えない。結婚して一緒に住みたいけれどお金がなくて・・と躊躇しているカップルにお金を渡すから、男女が一緒に住めて、一緒に生活していれば子供が出来る。子供手当なんか渡さなくても子供を作って育てて行く経済力のあるところには、実はお金を配る必要なんて無い。誰にでも平等?そういう考えはもう終わりにしてもらいたいものです。
最後に国営であるNHKです。テレビという受信機が無くても、インターネット環境がある者からも受信料を略奪しようと企んでいます。スクランブルかけるなりしてお金を払わない人には見せない。その上で、魅力ある番組を制作し、スポンサーを獲得したり受信料を得るべきです。それをしないばかりか、日本の国益を損なうような親中親韓の立ち位置から、事実に反する報道を繰り返す。
それどころか「報道しない自由」を誇示し始めました。何を報道するかはNHKが決める・・・国益を無視し、報道の基本姿勢を踏み外しながら、受信料支払いを義務化する。いい加減に勝手な振る舞いを慎めよ、日本人!
今の日本人、国籍は日本でも心はどれだけ民度が低いんだという人が多過ぎます。滅びたくないなら、自分のを見つめ直す。どうでもいいよなんて言う人は、日本から出て行けとまで言いたくなります。
前回からの続きです。映画のチラシが少年マガジンの巻頭特集によって大ブームになり、少年マガジンは捨てても、巻頭のチラシ特集のページだけはそのままファイルして保存する。僕も友人たちも映画好きはそういうことをしていました。DVDどころか家庭用ビデオの姿も形も無かった1974年、映画を所有する方法は、映画館で鑑賞した時に購入するパンフレットくらいのもの。
そんな時代にこの映画チラシの収集なら、映画を観ていなくても、お金が無くてもコレクション出来る。映画の所有欲を満たせる。そういう点からも、映画チラシがブームになったのかも知れません。そして、ブームになれば映画チラシだけを掲載した本が欲しくなるというか、そういう本の発売が待たれます。ここでも先頭を切ったのは講談社の少年マガジンでした。
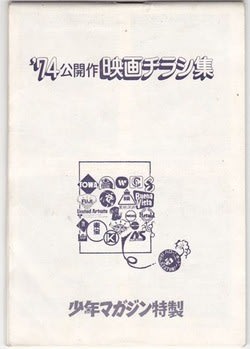
これが少年マガジンが出した、初の映画チラシ集です。ほぼ文庫本のサイズで、オール白黒44ページの小冊子です。裏表紙には値段も印刷されていません。


僕の記憶が正しければ(正しいと思うのですが)、この冊子は、チラシ特集を掲載した号の少年マガジンに付いていた応募券と、送料に当たる切手数百円を同封して講談社に送れば、この冊子が貰えるというものでした。書店に並べられて売られたものではありませんでした。
書店に並んだ初の「チラシ集」は、こちら。

「ロードショー」が発売した増刊号で、専門誌の威信に掛けて?編集しただけあって、実物大のチラシを折り込んだり、「太陽がいっぱい」の縮小パンフを綴じこんだり。主要作品のチラシは1ページの表裏を使ってチラシを再現するという優れものでした。

ロードショーに負けるなと後を追いかけたのが少年マガジンの講談社。こちらはチラシの表だけではあるものの、膨大な数のチラシを集めたオールカラーで、ブームの火付け役のプライドを感じる渾身の1冊でした。ちなみに続編も発売されました。

最後に発売したのが近代映画社スクリーンの増刊号。こちらはA3よりは小さいけれど、雑誌サイズより大きい、コンサートパンフのサイズで発売。しかも中身は日本が作成した映画のチラシは最小限に、名作映画の海外オリジナルポスターを1ページに1作品印刷したものでした。先行した2誌に比べると、かなり通好みの書籍で、少年達が買ったとは思えないのですが、これも続編が発売されました。
少年マガジンが火をつけた映画のチラシブームで、どれだけ観客動員数が上がったのかは分かりませんが、70年代後半から80年代に、高校生・大学生のデートと言えば映画館が定番だったのは事実。そして、洋画のおかげで中国や韓国ではない、欧米への海外旅行にも行く若者が多かったし、ブームは海の向こうからやって来る・・・そんな時代が確かにありました。