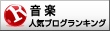カンタベリー・ロック特集、久々に再開です。
で、今回はギルガメッシュ。
還暦前後の方なら、「ギルガメッシュないと」というテレビ番組を思い出す人もいるかもしれませんが、全く関係ありません。
さて、ギルガメッシュというバンドは故Alan Gowenを中心に結成されたジャズ・ロック・バンドで、1972年にロンドンで結成されました。2枚のスタジオアルバムを残していますが、今回は1975年発表のファーストアルバムから、何曲か紹介いたします。
この作品のメンバーはAlan Gowen(k)、Phil Lee(g)、Michael Trais(d)、Jeff Clyne(b)。
ハットフィールド・アンド・ザ・ノースのデイブ・スチュアートが共同プロデューサーということで、なんか雰囲気が似ています。
フュージョンのような、ロックのような、ジャズのようなという感じが共通しているのでしょう。
でも、こっちの方が遊び心が強い感じがします。
予想がつかない展開はちょっとスリリング。シリアスだったり、コミカルだったりして、その辺が個性ですね。
組曲である「One end More/Phil's Little Dance/Worlds of Zin」は聴いていて、日本の四人囃子の「ゴールデン・ピクニックス」を思い出しました。不思議なことに同じころの作品です。へんてこりんな曲なんですが、後半のギターソロの部分は日本人が好きな叙情性に溢れていてけっこう聴き入っちゃいますね。
Gilgamesh - One end More/Phil's Little Dance/Worlds of Zin
VIDEO
Notwithstanding VIDEO
「Notwithstanding」はかなりジャズっぽい。ポップではないし、アヴァンギャルドでもない。でも、冒険的なサウンド。遊び心のあるジャズ・ロック。
Gilgamesh - i. We Are All ii. Someone Else's Food iii. Jamo And Other... [320kbps, best pressing] VIDEO
この組曲「i. We Are All ii. Someone Else's Food iii. Jamo And Other...」はまさにカンタベリー・ロック。演奏が凝っている。
ジャジーだったり、ポップだったり、けっこう楽しい。
その中でも、ロバート・フィリップ的ギターが主張するところが結構強烈。
こういうギターが入ると、混沌とした雰囲気になる。
クリムゾンと違うのはリズムセクションやキーボードが軽い。アンサンブル重視なんですね。
このファーストアルバム。ハットフィールドの作品のように、決め手にかけるところはあるけど、奇妙な個性が魅力です。