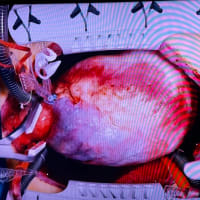心臓血管外科領域における再手術について、6月14日に神奈川心臓血管外科研究会において、熊本大学の福井教授からご講演を賜り、拝聴いたしました。福井教授は前任地である榊原記念病院において、非常に緻密でスピーディーな手術で定評があり、胸腹部大動脈置換術という心臓血管外科におけるもっとも大きな手術を驚くほどのスピードで終わらせる、という評判を聞いております。実際に福井先生の手術を目にした、手術が速いという評判のかつての榊原の同僚が「胸腹部置換を本当に三時間で終わらせて、レベルが違う!」と驚いておりました。
その福井教授、筆者と医師同学年の心臓血管外科医の中で間違いなく最も腕のいい外科医の一人であり、非常に興味深く拝聴しました。
心臓血管外科の再手術で多いのはやはり生体弁移植患者の生体弁機能不全や弁周囲逆流、人工弁感染、僧帽弁形成術後の再発などの弁膜症手術です。副損傷なく丁寧に再開胸し、適切なアプローチをする、これにつきます。
一方、胸部大血管手術後の再手術は、拡張した大動脈が胸骨に癒着していることもおおく、剥離の途中で大動脈を損傷して大出血するリスクの高い症例が多いのが事実です。現に大動脈損傷を起こし、大出血している患者には人工心肺で冷却して、循環停止した状態で胸骨を正中切開して視野を確保し、いち早く損傷した大動脈を広げて、内部から頸部分枝に脳分離送血を開始する、という手技が必要です。福井教授の提示した症例でも、循環停止として、胸骨切開を完成させ脳分離を開始するまで実に3分と、驚くべきスピードでした。
冠動脈バイパス術に関しては、初回手術の時に、若い患者さんの場合は再手術も考慮して、フラフトの走行を工夫している、とのことでした。
いくつかのコツが語られた非常に勉強になる講演で、共感する部分がたくさんある内容でしたので、多くの共感するコメントがフロアからありました。
再手術にならないような初回手術がベストなことは間違いありませんが、外科医としては、再手術をきっちりこなすことで循環器内科医からの信頼も初めて得られるのであり、低侵襲手術のこの時代だからこそ重要な課題である、と、座長をしておられた、横浜市大の増田教授からの締めくくりの一言は非常に重い言葉だと思われました。
その福井教授、筆者と医師同学年の心臓血管外科医の中で間違いなく最も腕のいい外科医の一人であり、非常に興味深く拝聴しました。
心臓血管外科の再手術で多いのはやはり生体弁移植患者の生体弁機能不全や弁周囲逆流、人工弁感染、僧帽弁形成術後の再発などの弁膜症手術です。副損傷なく丁寧に再開胸し、適切なアプローチをする、これにつきます。
一方、胸部大血管手術後の再手術は、拡張した大動脈が胸骨に癒着していることもおおく、剥離の途中で大動脈を損傷して大出血するリスクの高い症例が多いのが事実です。現に大動脈損傷を起こし、大出血している患者には人工心肺で冷却して、循環停止した状態で胸骨を正中切開して視野を確保し、いち早く損傷した大動脈を広げて、内部から頸部分枝に脳分離送血を開始する、という手技が必要です。福井教授の提示した症例でも、循環停止として、胸骨切開を完成させ脳分離を開始するまで実に3分と、驚くべきスピードでした。
冠動脈バイパス術に関しては、初回手術の時に、若い患者さんの場合は再手術も考慮して、フラフトの走行を工夫している、とのことでした。
いくつかのコツが語られた非常に勉強になる講演で、共感する部分がたくさんある内容でしたので、多くの共感するコメントがフロアからありました。
再手術にならないような初回手術がベストなことは間違いありませんが、外科医としては、再手術をきっちりこなすことで循環器内科医からの信頼も初めて得られるのであり、低侵襲手術のこの時代だからこそ重要な課題である、と、座長をしておられた、横浜市大の増田教授からの締めくくりの一言は非常に重い言葉だと思われました。