楽器博物館は浜松にあります。
浜松は「楽器の都」ですからね。
日本のピアノの2大メーカー、ヤマハもカワイも、そして電子楽器のトップともいえるローランドも、本社は浜松にあるんだから。
楽器博物館、10年前くらいに初めて行って、面白かったので、今回は 長年のデュオパートナー・おゆみを誘って、「おゆみとピーコ楽器博物館ツアー」を催行したわけです。

↑ちっちゃなシンバルみたいなのがいっぱい並んだ、アジアの楽器。

↑モンゴルの「馬頭琴(ばとうきん)」。いろんな馬や動物の頭をかたどっている。教科書の「スーホの白い馬」に出てくるよね。

↑韓国の楽器には、動物をかたどったものが多い。獅子、虎、龍などの他、アヒルやガチョウなどの形をした楽器もいっぱいあって、どれもカラフルでかわいい。

↑これはヨーロッパの管楽器だけど、なんかギョッとするよね。

↑こんなウツボみたいな楽器やだ💦

↑両側から二人の人が弾けるピアノ。これ1台で「2台ピアノデュオ」ができる。(笑)

↑こちらは、2段鍵盤のピアノ。これも「2台分を1台で弾ける」ってこと?

↑モンゴルの「馬頭琴(ばとうきん)」。いろんな馬や動物の頭をかたどっている。教科書の「スーホの白い馬」に出てくるよね。

↑韓国の楽器には、動物をかたどったものが多い。獅子、虎、龍などの他、アヒルやガチョウなどの形をした楽器もいっぱいあって、どれもカラフルでかわいい。

↑これはヨーロッパの管楽器だけど、なんかギョッとするよね。

↑こんなウツボみたいな楽器やだ💦

↑両側から二人の人が弾けるピアノ。これ1台で「2台ピアノデュオ」ができる。(笑)

↑こちらは、2段鍵盤のピアノ。これも「2台分を1台で弾ける」ってこと?
これらはヨーロッパで考えられた楽器なんだけど、コスパがいいかと思って作ってみたら、デカすぎ・重すぎで移動にものすごく費用がかかったり、メンテが大変だったりで、結局コスパ悪くて存続はしなかったということです。そりゃそうだね。

↑ペダルのところにちっちゃなハープが。かわいい♡

↑キハーダという、昔のラテン楽器です。これがのちに、みんなの大好きなビブラスラップへと発展したのです。

↑ペダルのところにちっちゃなハープが。かわいい♡

↑キハーダという、昔のラテン楽器です。これがのちに、みんなの大好きなビブラスラップへと発展したのです。
なんか動物の骨みたい?そうです。ロバのあごの骨そのものなのです。

↑初期の「リズムボックス」です。商品名は「ドンカマチック」といって、これをピアノの横に置いてリズムを鳴らしながら、ポピュラー曲を弾いたのです。ギョーカイでは「ドンカマ」って言ってた。

近くには、ハーモニカの形したホテルや、浜松城の見える展望台もあります。
楽器博物館、すごーくおもしろいので、みんなもぜひ行ってみてね。
HP HIBARIピアノ教室
Youtube HIBARI PIANO CLASS


















 まずはアルペンホルン。
まずはアルペンホルン。 きれいな絵が描いてある。
きれいな絵が描いてある。 アコーディオン。
アコーディオン。 クーグロッケン。
クーグロッケン。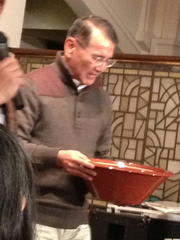 ターラーシュビンゲン。
ターラーシュビンゲン。 ヨーデル。
ヨーデル。


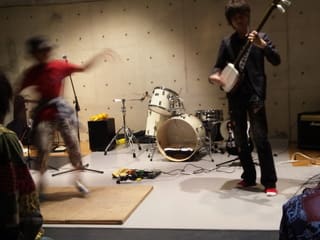


 古庄さん。
古庄さん。
















 撥(ばち)・右から順に象牙・木製。それに指かけと撥袋です
撥(ばち)・右から順に象牙・木製。それに指かけと撥袋です





