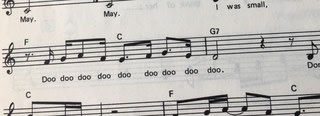(Mちゃん(中3):
ひょんなことから 発表会に弾く曲が早く決まり、ある程度練習したので、これをキープとし、何だかんだでまだ残っていた「ブルクミュラー」を どんどんやって終わらせよう、ということになりました。
今日は20番「タランテラ」です。
「タランテラ」についてはこのブログでも何度か書いているので、読んでみていただけるとわかりますが、タランテラというのは固有名詞ではなく、「曲のスタイル」を表す用語です。
8分の6拍子の急速なリズムを持つダンス音楽。それがタランテラです。
名前の由来には、有力な説が2つあり、
1.タランチュラという毒グモに刺された人は、死ぬまで踊り狂う
2.タランチュラに刺された人は 倒れるまで激しく踊り続けると、汗によって毒が抜け、命をとりとめる
というものです。
いずれにしても、毒グモ・タランチュラに由来している。
「どっちにしても、倒れるまでは踊るんだね・・・」
「そうだね・・・」
タランチュラ、恐るべし。
「タランテラって、どんな踊りなんだろうね。見てみようよ」
先生がYOUTUBE画面を開いて、「tarantella 」と入れると、すかさず「talantella ballet」と出たので、その画面を開き、Mちゃんと二人で見てみたら・・・
イタリアの民族衣装っぽい服装の踊り手たちが、軽やかにステップを踏んでいるダンス。
「なんか、あんまり激しくないね」
「楽しそうに踊ってるね」
という印象でした・・・
多分、バレエ画面を出してしまったので、あんまり激しくはなかったのかも?
普通の「ダンス」って入れれば、きっと本格的な激しいのが観れるよ。
そう思って、Mちゃんが帰った後「ballet」なしの「dance」で 再度探してみました。
ヒバリの期待した「タランテラ」は、フラメンコ風の真赤なドレープに包まれた衣装のダンサーが、苦悶(くもん)の表情で 狂ったように急速回転しながら、バッタリ倒れ伏すまで踊る、という感じだったんですが・・・
本物のタランテラはそんなんじゃなく、輪になって和やかに踊る民族舞踊、って感じでした。(^^;
そして、リズムは「スキップ」でした (^^;(^^;
確かに、スキップは8分の6拍子だよね。
タランテラなんだよね。
でもちょっとがっかり・・・明るく軽快すぎ。
そして、もっと驚いたことには、イタリア本場の「タランテラ」ダンスを次々と見て行ったら、途中、曲として「おにのパンツ」までが使われてたことだよ!
た、たしかにこの曲はイタリアの歌だ。
「おにのパンツ」というのは日本の替え歌で、ほんとはイタリアのヴェスヴィオス火山へ観光にいく登山電車のCMソング、「フニクリ・フニクラ」なんだから。
イタリアのご当地ソング。
そして8分の6拍子。
たしかに。タランテラだ。
タランテラの条件をすべて満たしてる。
でもな~
情熱的で深刻な踊りかと思ってた「タランテラ」なのに、本場演奏は「おにのパンツ」だったとは。
見なきゃよかったカモ・・・(*_*;
HP HIBARIピアノ教室
Youtube HIBARI PIANO CLASS