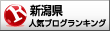昨夜は臨時総会でした。
63年前の 「堀之内町花卉園芸組合」 から 「ほりのうち花き園芸組合」 へ。
そしてこのたび、「魚沼花き園芸組合」 と組織名を変更しました。

6町村が合併して「魚沼市」が誕生したのは中越大震災から1週間後。
今回も東北関東大震災から1週間後。因縁めいたものを感じるのは考えすぎですね。
今回の地震で思い知らされたのは、地方に大きな災害があれば都会もダメだということ。
日本中は物や金、経済の流れだけでなく支援体制や感情面でも深くつながってることがお解りだと思う。
豪雪地で園芸を営む我々は毎年のようにいろいろな気象災害にあいながらもなんとかやれている。
これは、大都市を中心とした大きなマーケットに支えられているおかげで、都会がだめなら地方もダメ、地方がダメなら都会もダメ、両方がしっかりした経済基盤を維持できなきゃいけない訳です。
最近は地方経済が衰退気味。都会と地方のバランスが悪くなってます。地方の産業はもっと地域ぐるみの産業として頑張らなきゃいけないですね。
開会のあいさつで引用させてもらったのは、中村修二さんの文章でした。原文はこちら。
「自然の所与は、課せられた圧倒的な問いであり、米の収穫は、それへの回答である。問われては答え、問われては答える。問いは、毎年異なる。いや、あらゆる時に異なってくると言えるだろう。水、土、光、空気の流れは、刻々に変化している。生育する稲は、それらの変化に刻々と応じる。それらの性質を分離させては、新しく束ね、また拡散させる。それらの性質の限りない差異に入り込み、選り分け、結びつけ、流れの中に驚異的な統合の線を創り出す。そうして、米ができる。農村の父達が、ほんとうに信じているものは、都会人が教える効率でも、利潤でもない。この働きだけである」
漁業や農業は、自然からの「問い」の連続である。その変化に刻々と答え、問いの向こうに未来を信じ続けてきたのが、私達・日本人なのである。だから、何度も、天変地異に遭いながらも、その村で、農業や漁業を営んできた。利潤をあげる計算に口先で賛成しながら、決して従わない。そうして、何度も津波が押し寄せる街に暮らし続けてきたのだ。
そういう日本人は、どんなに苦しい時でも、みんなが整列してものを買う。なぜなら、これも大きな自然からの「問い」であると無意識に思っているからである。この「問い」の先に、きっと未来があることを知っている。それが身体に染みついているから、みんなが整列して、身を携えるのだ。
この東北大震災を機に、日本人の倫理や道徳のルーツである「漁業や農業」に、人々は、もう一度、目を向けて貰いたい。
東北の取引市場さん向けに募金活動をしました。でも、仙台市場さんはじめ各市場との連絡が付きません。どなたか状況をご存知の方はコメントください。