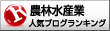日記によると7日からこの猛暑は続いている。

平成6年にも同じような猛暑の年があってユリが育たない夏だった。
今年から山の上の村も灌漑設備が稼働、ユリは毎日水をもらっている。

問題は他の作物、ウルイが黄色くなってしまった。昨日から手動での潅水を開始したけどなかなかはかどらない。
今日は日曜日返上だ。ファイト!

草は全然負けていないようだ、、、、、ファイト!

野菜畑にカラスよけのおもちゃをつるしたところ、、、、

逆に反感を買ったらしく、仕返しされるようになった。

やっと実り出したトマトまで。

犯人の足跡、、、、、

カサブランカ1作目が終わって2作目が始まった。今年は人並みのマイウエディングも。

赤いドレスもまじっている。新婦友人か?

夏の風物詩。


今日もファイト!
あーさー。。。。

農産物には旬がある。
農業では旬の先取りがもてはやされる。
でも、ユリは周年出荷されていて旬なんてないと思われているかもね。
オリエンタルユリの旬は、原種である山ユリの咲く時期。つまり夏なのだ。
秋に植えて今咲くユリ、もしくは春一番に植えて今咲くユリ。一番ボリュームの出る時期が旬なのだ。
旬スペシャルと銘打ったユリが出荷されます。特徴はでかいこと。

まずはバリスタから。身長2m弱の私と比べてみるとデカさがわかるでしょう。

続いてカサブランカもすぐに始まります。

輪数多すぎた時はいろいろな楽しみ方もあるのだ。無駄なく咲かせて楽しんでください。
大きな花はお得です。
簡単!お花の飾り方♪ 『新潟県魚沼花き園芸組合さん オリエンタルユリ』
夏野菜も旬。変なナスが採れたぞい。

山喜農園の展示ハウスも終盤を迎えている。
もちろん興味深い品種や目新しい品種はたくさんある。

終盤、つまり晩成品種にこそ夏向きの品種は多い。
これなんかそうとう楽しみな品種だ。

夏のユリでとても大切なのは先っちょから開かない開花特性。
咲いてますとクレームの来る品種の大半は口割れ。咲いてるのではなくて割れてるだけなのだが、、、、
その点、胴から割れる品種はクレームが来にくい。これはとても重要です。

今回の展示シーズン中、いつも以上に山喜社長が声を荒げるほどに力説していたのがユリの立ち位置についてだ。
ユリは主役にしかなれない花。
主役を務める品質のものにしかお客さんは金を払わないはず。
品質確保に無理の有る作型や消費動向を考えない物量本位の生産は控えなければならない時代なのだ。
球根が売れなくなることを前提にした球根屋の説明には説得力がある。
我々と前後十歳くらいの範囲の経営者はバブル時代の恩恵に浸って経営をしてきた。
平成の初め、世の中はバブル景気に踊っていた。
同時期に広まったオリエンタルユリブーム。ユリバブルは平成11年くらいまで続いた。
さらにヒートポンプの普及が作期を長くさせた。
大きくなった経営の後やってきた花産業全体の縮小。まだ対応しきれていないのだ。
昨今は花農家の複合化が全国的に進んでいる。
魚沼では山菜等の導入で通年農業が可能になった。無理な作型をしなくても良くなってきている。
主役を張れる品質のユリだけで全国の産地リレーが出来ればユリの価格維持は可能なはずではないのか。

ユリ展示の主役は露地作のセレクションリリーの方に移ります。

雨風にあたった状態での丈の伸び、蕾の角度、枝のボリュームなどが視点になります。
もちろん興味深い品種も多数。

この日は房州4人組が来訪。3月からの価格低迷をぼやきながらも積極的な品種ミーティングをしていった。

明日オランダに帰ると言うエバートと久しぶりに飲んだ。
立ち位置的には光頭三人衆みたいになっちまった。

大雨と台風の被害にあわれた皆様にはお見舞い申し上げます。

1週間ほど続いた酷暑が終わって一気に梅雨空になった。新潟県はまだ梅雨明け宣言していないのだ。
気温が落ち着くのを待って一気に球根植え、9月後半の採花予定なので球数も多くて一度に15a位は植えてしまう。

ハウス建てと追っかけっ子で進める作業。
去年は我が家周辺が大雨続きでまったく畑作りが出来ていなかった状態。
春以降に大急ぎで堆肥撒いたり土壌消毒したりと泥縄式だったがここに来てようやく追いついた感じがしている。

うちのメイン圃場は去年の雨で痛めつけられて今年は暗渠排水からやり直した。
キルパーのマルチを剥いだら緑肥を作って秋うちかけて土作りをします。

緑肥には毎朝Qちゃんが追肥をします。

雨が降るので連日の山喜展示圃場通い。従業員も全員連れて見に行きます。
あれを作りたいこれを作りたいと言う気持ちの高まりが大事なのです。





ブライアーノとベルビアーノとルビアーノがあります。頭が、、、、、、
日曜日、7時の新幹線で出かけて9時半にはもうスカイツリー。


前回登りつめなかった夫婦は今回こそはと一気に登りつめる。

朝4時起きして稼いでから出かけた夫婦はもう汗まみれ。顔が照かってる。

今一つクリアではない視界だったのでまた冬にリベンジを誓う。
今回は上野を起点に京成線あたりを散策。
柴又駅前では寅さんが迎えてくれた。

心配そうに見送る、さくら~

レトロな参道を行くと、、、、

あの有名な柴又帝釈天だ。

フ―テンの寅さんで有名だが実は大変な彫刻の寺なのだ。

関東大震災の後、当時の彫師によって再建されたのだそうだ。


本堂の背面ぐるりと、もちろん本堂の中も。すごい数の彫り物。
彫師の中には石川の姓の人も数名いる。ひょっとして雲長ゆかりの彫師かも。
大正末期から昭和初期の作品。戦火は幸運にも免れたのだろう。見ごたえあります。

裏には立派な庭園が続く。

親分、庭園だ、庭園だ、、、、

竹垣で囲まれた茶室では茶室さされつ、、、、

噛まないカメがのんびりと、、、、

ほんとうは経栄山 題経寺(きょうえいざん だいきょうじ)と言います。
帝釈天とは門の中の帝釈天。天は戦士、ファイターなのだ。

娘と合流。相変わらず同じような出で立ち、、、、遺伝子か。

お昼はやっぱりココですね。

映画と同じような気さくで大声のおばちゃんが迎えてくれました。

京成線を少し戻って青砥。何故か芸術の町っぽい。

本当の目的はココ。ヒカラビ君の演奏会でPTA。

看板が、、、なんか、、、もうちょっと、、、、
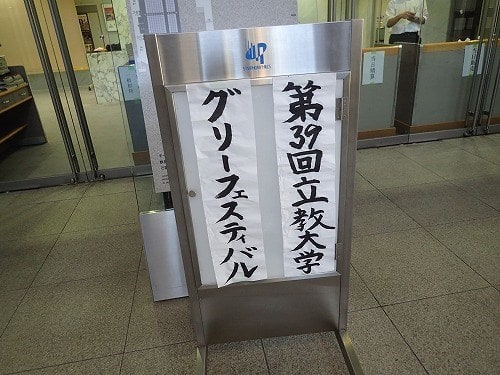
会場はそんなに大きくはないけど天井高い。クラシック向きのホールかな。

何度かある演奏会の中でもグリーフェスティバルは何となく身内っぽい。
普段一緒に演奏しない女性コーラスとの混声合唱が聴けるしOB、OGたちも加わっての大人数のステージも面白い。
OB、OGたちは年配の方がほとんど。中には80歳を超えても現役の方も。
歌い続けることが長生きの秘訣なのかも。(画像はパンフレットから)
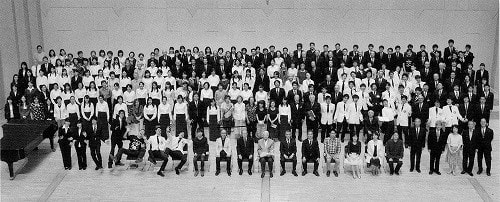
上野に帰ってもまだ明るい、上野と言えば当然ここによって帰ります。

歩いてる人はほぼアジア系の外国人。このギャグが分かるだろうか。

楽勝に日帰り。東京はすぐそこ、近すぎかも。
どうやら今年は梅雨に入らないうちの梅雨が明けたようだ。真夏日、、、、

午前中は猛暑、午後からは夕立と強風、、、、、、

防除のタイミングが、、、、無い。まったく B 級の天気だ。

熱くてぐったりしているユリに雨風、、、ベントネックになっちゃう。
でもこの段階ですぐに曲がりを直してやると真っ直ぐになります。 これを2日連続でやってますW。

露地作のバリスタ、すごい剣幕でボリューム出て来てます。

北海道産カサブランカ、だいぶつぼみが膨らみだした。

さらにでかい春一番植えのカサブランカ、ちょっと色が濃すぎるかもしれない。

以上旬スペシャルです。
春のハウスが終わったのでハウス内に密造していた枝豆の収穫。
暑い日の締めはこれとロング缶。真夏 A