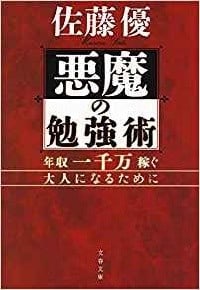<豆腐や豆乳、納豆などの大豆製品(★★★★★)も日本人の健康長寿に大きく貢献してきた食品です。
ポリフェノールの一種である大豆イソフラボンは、AGEの生成を抑えてくれます。女性ホルモンに近い作用もありますから、肌のくすみ防止や美白効果も期待できる。さらには、細胞や脳の若返り効果があるレシチンも含まれ、理想的なアンチエイジング食品といえるのです。
特に大豆イソフラボンを多く含むのが納豆です。発酵食品ですからビタミン類やアミノ酸なども豊富。できれば毎日1パック食べてほしい。
豆腐に含まれる良質なタンパク質は、血圧を下げる効果もあります。豆腐は朝食のお味噌汁にたっぷり入れれば、それだけで十分な量の栄養分が摂れます。1日で豆腐半丁が摂取の目安です。
牛乳を毎日飲んでいる方は豆乳に代えることをオススメします。ただ、糖分が添加されている商品も多いので購入時には成分に注意を。必ず無調整の豆乳を選んでください。
夕食時の適量のお酒は身体にいいのでオススメします。なかでもポリフェノールを豊富に含むワイン(★★★)の健康作用は、既に一流の医学雑誌に数々の研究が発表されており、もはやお墨付きです。
赤ワインにはレスペラトロールやケルセチン、カテキンといった成分が含まれ、AGEを抑えて動脈硬化を防いでくれます。
白ワインも健康効果では負けていません。1日に120cc、つまりグラス1杯程度の白ワインを3ヵ月飲み続けると、体重減少に加え、体脂肪や血圧の値が改善されたという研究があります。これは白ワインに多く含まれる酒石酸というミネラルの影響だと考えられます。また、血糖値を下げるという研究もあります。
私は夕食の際には妻と一緒に白ワインを飲むことにしています。翌朝、血糖値を測ってみるとたしかに下がっているのです。ただし、要注意は甘味が強いワイン。糖質の少ない辛口がオススメです。
いくら「百薬の長」とはいえ、飲み過ぎは禁物です。適量はどのくらいなのでしょうか。
それを教えてくれるのが、今年4月に「ランセット」に掲載された飲酒量と死亡率との関係を示す研究です。約60万人を対象とした83の研究を分析したところ、最も死亡率が低かったのは、純アルコールの摂取量が1週間に100g未満のグループでした。これはワインのアルコール度数で計算するとボトル1本程度。一方、摂取量が200gを超えると、脳卒中や心不全のリスクは直線的に上昇しました。
日本人は欧米人と比べると脳卒中が多いので、ワインなら週にボトル2本を超えないように。週に一度は肝休日を設けて、1日にグラスワイン1、2杯程度です。
晩酌のおつまみにも健康に良い食品があります。
まずオススメできるのはチョコレート(★★★★)。チョコレートに含まれるカカオポリフェノールは、強力な抗酸化作用があります。
1997年に人類史上最高齢の122歳で亡くなったジャンヌ・カルマンさんというフランス人女性は、ワインとチョコレートが大好物で多いときは1週間で約1kgもチョコレートやカカオ成分を多く含むショコラショーというドリンクを飲んでいたそうです。
ただし、チョコレートで注意すべきは糖分。甘いものは血糖値を上昇させるため逆効果になります。また、ホワイトチョコはカカオポリフェノールの含有量が少ないため、ブラックの方がいい。健康にいいと言えるのは、カカオ成分が70%以上のビターチョコです。目安は1日に25g、個包装になっている小さな板チョコであれば5枚程度食べても構いません。
地中海食でよく食べられるナッツ類(★★)もいい。クルミやアーモンド、カシューナッツにはビタミンやミネラル、食物繊維などが豊富に含まれ、心疾患や糖尿病など様々な病気を予防してくれます。
ただし、市販のナッツは塩分が過剰に含まれるので、購入の際は「無塩」のものを選んでください。また輸入ものが多いナッツ類は防カビ剤が添加されているものもあります。私は国産の無添加性落花生をオススメしています。落花生は木の実であるツリーナッツではありませんが、健康に与える効果は変わりません。
添加物と健康の関係には、様々な議論がありますが、2015年に世界保健機関(WHO)がハムなどの加工肉に発がん性があると発表しました。これは加工肉に含まれる保存料が原因だと考えられています。WHOのような国際機関が注意喚起をするのですからよほどのことです。
私はパンに含まれるイーストフードに注意を払っています。これはパンを膨らませるイースト菌の働きを強める添加物です。パンを買うときは必ずイーストフードが入っていないものを選んでいます。添加物の悪影響は全てわかっているわけではありませんが、私は、少量であれば大丈夫という考え方はむしろ危険ではないかと考えているのです。>
□牧田善二(AGE牧田クリニック院長)「100%カラダにいい食品(18品目リスト付き) 世界最高峰の医学雑誌が保証する 一週間に一回は摂って欲しい」(文芸春秋 2018年9月号)から一部引用
【参考】
「【食】「老けない食品の王様」 ~100%カラダにいい食品(3)~」
「【食】「焼く、揚げる」に要注意 ~100%カラダにいい食品(2)~」
「【食】酸化・糖化・AGE ~100%カラダにいい食品(1)~」
100%カラダにいい18品目(1) (クリックして拡大)

100%カラダにいい18品目(2) (クリックして拡大)

ポリフェノールの一種である大豆イソフラボンは、AGEの生成を抑えてくれます。女性ホルモンに近い作用もありますから、肌のくすみ防止や美白効果も期待できる。さらには、細胞や脳の若返り効果があるレシチンも含まれ、理想的なアンチエイジング食品といえるのです。
特に大豆イソフラボンを多く含むのが納豆です。発酵食品ですからビタミン類やアミノ酸なども豊富。できれば毎日1パック食べてほしい。
豆腐に含まれる良質なタンパク質は、血圧を下げる効果もあります。豆腐は朝食のお味噌汁にたっぷり入れれば、それだけで十分な量の栄養分が摂れます。1日で豆腐半丁が摂取の目安です。
牛乳を毎日飲んでいる方は豆乳に代えることをオススメします。ただ、糖分が添加されている商品も多いので購入時には成分に注意を。必ず無調整の豆乳を選んでください。
夕食時の適量のお酒は身体にいいのでオススメします。なかでもポリフェノールを豊富に含むワイン(★★★)の健康作用は、既に一流の医学雑誌に数々の研究が発表されており、もはやお墨付きです。
赤ワインにはレスペラトロールやケルセチン、カテキンといった成分が含まれ、AGEを抑えて動脈硬化を防いでくれます。
白ワインも健康効果では負けていません。1日に120cc、つまりグラス1杯程度の白ワインを3ヵ月飲み続けると、体重減少に加え、体脂肪や血圧の値が改善されたという研究があります。これは白ワインに多く含まれる酒石酸というミネラルの影響だと考えられます。また、血糖値を下げるという研究もあります。
私は夕食の際には妻と一緒に白ワインを飲むことにしています。翌朝、血糖値を測ってみるとたしかに下がっているのです。ただし、要注意は甘味が強いワイン。糖質の少ない辛口がオススメです。
いくら「百薬の長」とはいえ、飲み過ぎは禁物です。適量はどのくらいなのでしょうか。
それを教えてくれるのが、今年4月に「ランセット」に掲載された飲酒量と死亡率との関係を示す研究です。約60万人を対象とした83の研究を分析したところ、最も死亡率が低かったのは、純アルコールの摂取量が1週間に100g未満のグループでした。これはワインのアルコール度数で計算するとボトル1本程度。一方、摂取量が200gを超えると、脳卒中や心不全のリスクは直線的に上昇しました。
日本人は欧米人と比べると脳卒中が多いので、ワインなら週にボトル2本を超えないように。週に一度は肝休日を設けて、1日にグラスワイン1、2杯程度です。
晩酌のおつまみにも健康に良い食品があります。
まずオススメできるのはチョコレート(★★★★)。チョコレートに含まれるカカオポリフェノールは、強力な抗酸化作用があります。
1997年に人類史上最高齢の122歳で亡くなったジャンヌ・カルマンさんというフランス人女性は、ワインとチョコレートが大好物で多いときは1週間で約1kgもチョコレートやカカオ成分を多く含むショコラショーというドリンクを飲んでいたそうです。
ただし、チョコレートで注意すべきは糖分。甘いものは血糖値を上昇させるため逆効果になります。また、ホワイトチョコはカカオポリフェノールの含有量が少ないため、ブラックの方がいい。健康にいいと言えるのは、カカオ成分が70%以上のビターチョコです。目安は1日に25g、個包装になっている小さな板チョコであれば5枚程度食べても構いません。
地中海食でよく食べられるナッツ類(★★)もいい。クルミやアーモンド、カシューナッツにはビタミンやミネラル、食物繊維などが豊富に含まれ、心疾患や糖尿病など様々な病気を予防してくれます。
ただし、市販のナッツは塩分が過剰に含まれるので、購入の際は「無塩」のものを選んでください。また輸入ものが多いナッツ類は防カビ剤が添加されているものもあります。私は国産の無添加性落花生をオススメしています。落花生は木の実であるツリーナッツではありませんが、健康に与える効果は変わりません。
添加物と健康の関係には、様々な議論がありますが、2015年に世界保健機関(WHO)がハムなどの加工肉に発がん性があると発表しました。これは加工肉に含まれる保存料が原因だと考えられています。WHOのような国際機関が注意喚起をするのですからよほどのことです。
私はパンに含まれるイーストフードに注意を払っています。これはパンを膨らませるイースト菌の働きを強める添加物です。パンを買うときは必ずイーストフードが入っていないものを選んでいます。添加物の悪影響は全てわかっているわけではありませんが、私は、少量であれば大丈夫という考え方はむしろ危険ではないかと考えているのです。>
□牧田善二(AGE牧田クリニック院長)「100%カラダにいい食品(18品目リスト付き) 世界最高峰の医学雑誌が保証する 一週間に一回は摂って欲しい」(文芸春秋 2018年9月号)から一部引用
【参考】
「【食】「老けない食品の王様」 ~100%カラダにいい食品(3)~」
「【食】「焼く、揚げる」に要注意 ~100%カラダにいい食品(2)~」
「【食】酸化・糖化・AGE ~100%カラダにいい食品(1)~」
100%カラダにいい18品目(1) (クリックして拡大)

100%カラダにいい18品目(2) (クリックして拡大)