前回のブログ「腕力で書くとは」は、タイトルがちょっと風変りだったせいか好評を博したようで・・、やはりタイトルは重要ですね(笑)。
メル友さんたちからも、「ウマさん」(南スコットランド)、「I」さん(東海地方)、「T」さんから「毎日のブログ更新たいへんですね・・」と「ねぎらい」のお便りをいただいた。
何だか催促したみたいで、ちょっと気が引けますけどね~(笑)。
で、「(文章を)腕力で書く」の言わんとするところは、頭だけじゃなくて身に付いた習慣みたいに「書く」ことを自然に身体全体に沁み込ませるということでした。上手く表現できませんけどね~。
文章を書く行為がそれなら、オーディオだって・・(笑)。
というわけで「オーディオは(頭だけで考えるのではなく)行動力にあり」といきますか~。
格好の事例を挙げてみよう。
以下、ちょっと専門的な内容になるので許してね~。とりわけ「ウマさん」には「真空管のことはさっぱりわからない」と、いつもこぼされているのでたいへん申し訳ない・・。
で、10日前のブログ「刹那主義」(1月5日付)をご記憶だろうか。
下段の左端の「LS7」(英国GEC)が、その右側の「3A/109B」(英国STC)に音質テストでアッサリ負けたという事実から話が発展した。
もちろん、単に相性が悪かったというだけで性能自体を否定するものでないのはもう言わずもがな~。
ただし、我が家ではもう出番が見込めないのでオークションに出そうかと考えたが、あまりにも「用済み=放逐」というのは冷たすぎる・・、オーディオはなるべく「ウォーム・ハート」を心掛けないとね(笑)。
そこで、方向転換して「LS7」を出力管に使えないかという相談を「アンプビルダー」のNさん(大分市)に持ち掛けていたところ、アンプの設計図まで描いて慎重に検討していただいた結果、改造は不可能と分かった。
「LS7」は直熱管なので別途「ヒーター回路」が要るし、出力トランスがプッシュプルなので4本必要とのこと・・、アッサリ断念。
しかし、そこで簡単に引き下がらないのが「熱烈なオーディオマニア」の面目躍如たるところ・・(笑)。
このアンプなら改造可能ですか、と持って行ったのが13日(土)のこと。
「71Aシングル」だけど、小出力ながら「075ツィーター」(JBL)にはもってこいのアンプなので愛用していたのだが・・。
ところが、「71A」アンプは同型のがもう1台あって立派に代役は務まるし、それに今回の改造の余波による実験の結果「075」にはもっと最適のアンプがあったんですよねえ。
いつもは「WE300B」を挿しているのだが、さすがに「4000ヘルツ以上」だけに使うのはもったいないので、「6A3」出力管に代えている。
通常はこの両者に互換性は無いのだが、製作者によると「数値を控えめにして駆動しているこのアンプに限っては使用可能です」とのこと。
そして、このアンプによってオーデイオは4000ヘルツ以上の再生がいかに大切か・・すっかり目が覚めました!
「先入観は罪、固定観念は悪」という言葉がつくづく身に沁みましたぞ(笑)。
「LS7」の起用から発展して「あれよあれよ」という間のまさかの副産物だったが、こういう副産物は大歓迎でまさに「行動力」のなせる業。
そして、アンプの改造の方もNさんからは「このアンプならLS7が挿せますね、改造してみましょう。ただし、音がよくなるかどうかは保証の限りではありませんよ。71Aはとてもいい出力管ですからね・・。LS7が上回るかどうかやってみなくちゃ皆目見当がつきません」
「ハイ、それで結構です。オーディオは博打だと割り切ってますから。それにLS7が使えるとなると、類似の球がいっぱいありますので生き返らせることができます」
はたして「吉と出るか、凶と出るか」・・(笑)。
積極的にクリック → 
昨日の1月14日は日曜日なので、読売新聞の文化欄ではいつもの「新書」の書評特集だったが、そのうちの一つがこれ。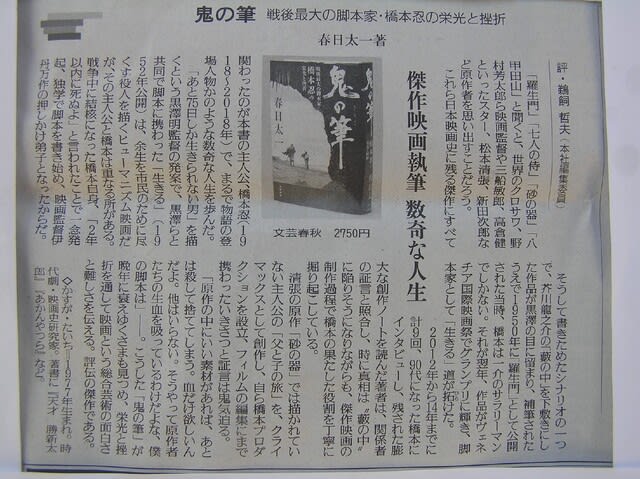
本のタイトルは「鬼の筆」、主人公は脚本家の「橋本 忍」氏。
日本映画史に残る傑作「生きる」「羅生門」「七人の侍」「砂の器」「八甲田山」とくれば、往年の映画ファンにとっては忘れられない作品ばかり。
ふっ、ふっ、ふっ・・と、つい含み笑いが出てしまった。タイミングよくちょうど読み終えたばかりなんですよねえ~(笑)。
元々「橋本氏」には興味があったので「一気読み」でした。たしかに「評伝の傑作」といっても間違いなし、機会があればぜひご一読をお薦めします。
興味深いエピソードを箇条書きしてみよう。
☆ 父親に似て博打好きで、脚本料としてもらった200万円を帰りにそのまま競輪に突っ込んで全部スッてしまった。映画の興行だって当たるかどうかの博打みたいなもので、脚本の中にいろいろ仕掛けを講じて聴衆の反応を予測するのが楽しい。
☆ 黒澤監督との軋轢(あつれき)も興味深い。脚本の出来は映画の死命を制するものといっていいが、一連の名作は橋本氏抜きでは考えられないものだったが、監督の考えは違っていた。
(橋本氏は)単なる雇人の一人に過ぎず、名声はすべて自分(監督)に帰すものと考えていた。橋本氏がやっと世間の陽の目を見たのは名作「真昼の暗黒」からだった。
☆ 「腕力で書く」
256頁に次のような記述があった。
脚本家にとって腕力が大事だということは、(師事した)伊丹(万作)さんの基本なんだ。何となしに、僕は伊丹さんに教えてもらったからね。伊丹さんに「特別な勉強の仕方があるんですか」って聞いたんだ。
そしたら伊丹さんはねえ、「いや、そんなものはない」と。「ただな、橋本君、字を書く仕事だからね。原稿用紙に20枚なり、30枚なり、字を書くことを毎日やれ。書くことがなければ、いろはにほへとでもいい。とにかく字を書くことが基本だから」と、言われてね。
それで、字さえ書きゃいいのかなという風に思って始めて、1日にペラ30枚だ、40枚だ、平然とそれを書き続けたらやっぱり書き手としての腕は太くなるよ。要するに字を書けってことだな。それは野球選手のキャッチボールみたいなものだよね。絶えずやってて、それに慣れるということだと思うんだ。
そうしてやって来たのでね。やっぱりそれをやってきた強さじゃないかな。これはなかなかできないよ。実際に実行できるかどうか。僕はそれをやってきたわけ」
というわけです。
大脚本家を引き合いにするのはまことに恐れ多いが、毎日ブログを更新している我が身にとっては、「腕力で書く」とはまさにピッタリ・・。
「毎日のブログ更新ってたいへんですねえ・・」、誰も労(ねぎら)ってくれないので自分で言うしかないが(笑)、実は頭で書くのではなくて「腕力」で書いているつもり。
たとえば、「なぜ毎日更新するんですか? 1円の得にもならないのに・・」 もし、こう問われたらどう答えようか。
「ハイ、自分の取り柄は書くことだけですからね。高レベルのものは書けないにしても、間断なく続けることに意味があると思っています。いわば腕力勝負です。それに、いったん休むとリズムが崩れますからね、次に書くときに億劫になります。まあ、自転車操業みたいなもんです」
ただし、「音楽&オーデイオ」愛好家にとって「少しでも参考になることがあれば幸い」という思いは微かにありますよ~、それに・・、「自己顕示欲」がまったく無いといえば、ウソになりますかなあ(笑)。
積極的にクリック → 
新刊の「音楽する脳」を読んでいたら、次のような箇所が印象に残った。(176頁)
「基本的に人は常に新しいものに触れ続けると脳がその情報を処理するためのエネルギーをたくさん使ってしまうため疲れてしまいます。一方、常に当たり前すぎるものに触れ続けても脳は飽きてしまい、知的好奇心や感動も生まれません。
このように、あまりにも予測からズレすぎず、当たり前すぎない「微妙なズレ」に、人はなんともいえない感動を覚えると考えられています。ある程度わかるけれど、ちょっとわかりづらい「予測や経験からの微妙なズレ」が、知的好奇心や興味をくすぐるのです。」
以上のとおりだが、人が「大きな変化」ではなくて「微妙なズレ」を好むって、なんだか分かるような気がしますね。音楽に限らず選挙だってそう。
たとえば、昨日(13日)行われた注目の「台湾総統選挙」は現在の政権「親アメリカ=中国と対立」を受け継ぐ形で、見事な保守党の勝利となった。
台湾国民は大きな変化を望まなかったわけだが、おそらく「習近平」さんが歯ぎしりをしていることだろう。
香港であんなにひどい「自由と言論の弾圧」をしたんだから、その実例を見た台湾の国民が一斉に引いたのはよくわかる。
「香港と台湾とどちらが大切か」となると、比較にならないほど後者の比重が大きいのに、あんな馬鹿なことをして・・。
結局その報いが来たわけだが、もし本気で台湾の統一を願うなら「北風と太陽」の 太陽政策で行かないとね・・。
おっと、政治の素人の「生兵法」はこのくらいにしておこう(笑)。
で、本題に戻って・・、著者はこの「微妙なズレ」を「ゆらぎ」とも称している。
モーツァルトの音楽は微妙な「ゆらぎ」に満ちているが、実はオーディオにおいてもその「ゆらぎ」を求めて毎日のように悪戦苦闘しているのではあるまいか・・、に思い至った。
音は空気の振動だがその物理現象を「音楽」に変換するのは「脳」なので、毎日同じ音ばかり聞いていても飽きてしまう、で、ちょっとした変化を求めて何かしら「システム」のどこかを弄りたがるのが我が家では常態化している。
このブログの読者ならお分かりのとおりですね(笑)。
これはけっして自慢できるような話ではなく移り気な自分の性格がなせる業だと、これまでやや否定的に思ってきたのだが、脳の働きからするとごく正常な取り組みなのかもしれないと、どうやら自信らしきものが湧いてきた。
これで「また始まったか!」と、他人の目を気にすることなく記事が書ける~(笑)。
というわけで、実践例を一つ。
我が家には6系統のスピーカー(以下「SP」)があり、「そんなに持っていてどうする」と詰められそうだが、それぞれに何かしら「いいところ」を持っているので、どうも捨てがたい。
で、理想としては6つの部屋があってそれぞれにSPを置きたいところだが、それは無理なので仕方なく一つの部屋で聴きたいSPをリスナー席の正面に移動させることになる。
それぞれのSPはある程度の重量があり、持ち上げて移動させるのはよほどの体力の持ち主でないと無理なのでSPの下に移動用の滑車を付けて移動しやすいようにしている。
で、かねてからこの「移動滑車」が無ければもっと音が良くなるかもしれないという思いがずっと捨てきれなかった。つまり、床(コンクリート)と直接に接しているこの滑車が大切な「箱」の振動に影響を与えていそうなことは経験上わかっている。
まあ、ほんのちょっとした差かもしれないが、手間を惜しむようでは「気に入った音」は永遠に得られない(笑)。
そこで、久しぶりに「AXIOM80」(オリジナル)の登場となった。
何しろ、板厚が「1.5cm」なので軽くて持ち上げやすいので、実験には最適。
下に3点支持(前方に二つ、後方に一つ)でインシュレーター(木)を噛ませてみることにした。
これで「滑車」が完全に浮いた状態になった。再度移動させるときはこの木を取り外せばいい。
そして、ワクワクドキドキしながら出てきた音に耳を傾けてみると、なんとまあ・・・。
自画自賛は「はしたない」ので、この辺で止めておいたほうが良さそうだね、読者の不興も買うしね~(笑)。
この内容に共感された方は励ましのクリックを →
このブログの恒常的な読者ならご存じのように、我が家では同じスピーカーをだいたい1週間も続けて聴いていると「飽き」がくるパタ~ンが続いている。
ところが・・、このたび1週間以上も経つのに飽きるどころかますます深みにハマってしまうスピーカーが出てきたんですよねえ、こういうことは初めて・・。
で、いつも「粗(あら)探し」ばかりして、それをネタにブログに投稿しているのだが、今回は珍しく姿勢を代えて「なぜ飽きがこないのか」・・、いわば成功事例からのアプローチといこう。
ただし、「失敗学のすすめ」(畑村陽太郎:東大教授)にある通り、人は成功事例を敬遠するのが相場で、その一方、他人の失敗事例となるとやたらに興味津々となる・・。
今回の場合は「成功話」と「自慢話」とが「紙一重」の展開になりそうなので、「気に障りそうな方」はここでストップ! これから先は読み進まないようにね~(笑)。
まずは、「箱」からアプローチ。
この箱はオークションで入手したものでユニットは「AXIOM301」(グッドマン)が入っていた。同じグッドマンといっても、マグネットによって月とスッポンほどの差がある。
この「301」はフェライトマグネットだったので早々にお引き取り願ったが、箱の方は前面のバッフル版を改造してずっと楽しませてもらっている。
板厚が「4cm」もあるので、箱の響きはまったく期待していなかったのだが、今回容れた「口径25cm」のユニットが想像以上に豊かな響きを出すので驚いた。
「バッフル」(ユニットを取り付けた板)だけは自作だが、その板厚が「1.5cm」なので、そのせいかもしれない・・。
となると「AXIOM80」だって、バッフルだけ「1cm」厚の「楓」(かえで)に代えてみるのも手かな・・、そのうち試してみよう。
次に、二つのユニットに移ろう。
まずは「~3000ヘルツ」まで受け持つ「コーン型ユニット」だが、「口径25cm」というのが大いに効いていそう。
我が家では「口径38cm」は論外としても、口径20cmと30cmのユニットの酸いも甘いも噛分けているつもりだが、その中間となる「口径25cm」に絶妙のバランスがあった・・、まさに「中庸の美徳」かな・・(笑)。
次に、「4000ヘルツ~」を受け持つツィーター「075」(JBL)。
購入当時に、当時のお師匠さんから「能率が非常に高いのでとても使いやすいです。小出力の質のいい真空管アンプが使えますからね。これに超重量級のステンレスの削り出しホーンを付けてやると、一気に澄んだ音が出ます。鬼に金棒ですよ。これを上回るツィーターはないと思います」
たしかにそのとおりでした!
ただしホーンがメチャ高くて「AXIOM80」(オリジナル)と同じくらいのお値段だったのには参った・・。
ま、今となっては十分「元」を取ったかな~(笑)。ローカット4000ヘルツ用に使った「ブラックタイプ」のコンデンサー(ウェスタン製)も効いていそう。
で、次にスピーカーと運命共同体のアンプに触れておかないと「片手落ち」というものだろう。
コーン型ユニットに使ったのは当初は「2A3シングル」で、それを上回ったのが「6AR6シングル」だった。この球を「三極管接続」にすると、名管「PX4」(英国)と同じ特性になるとの触れ込みだったが期待通りだった。
「これでいいだろう」と、思っていたのだが欲というものは恐ろしい(笑)。
そのうち、とうとう大御所「PX25シングル」の出番となった。
このアンプは「DAC」との相性が極端だったが、いちばん良かったのが「エルガー プラス」(英国:dCS)で、豊かな低音域に驚いた。
もちろん「サブウーファー」(ウェストミンスター改)の出番はまったく不要~。
以上、「飽きがこない」要因がいくつも重なっているわけだが、「プレイヤーは審判を兼ねてはいけない」という金言があるのはよく承知している。
近々、仲間にテストしてもらうことにしようかな・・、音も自尊心もズタズタにされなきゃいいんだが(笑)。
前回のブログ「近頃の若者は・・」で提案したコンポへの誘い。
言い出した以上、安価で高性能のコンポを具体的に提示する義務があるかもしれない(笑)。
そこで、「独断と偏見」交じりで、思い切ってトライしてみよう。
まず、始めから「レコード」と「CDトラポ」は除外する。お値段と手間からして割に合わない。
で、「You Tube」が手軽に選択できるテレビがあれば十分。
その「光デジタル端子」から「光ケーブル」を使ってDACと繋ぐ。
DACもピンからキリだが、「SMSL」の「D300」などはお薦めで、先日のこと仲間の家で聴かせてもらったところ、「4万5千円」程度にしてはコスパ抜群だった。評判のいい「ローム」のチップが使ってある。
次に「アンプ」だが、TR式のプリメイン・アンプがオークションでごろごろしている。3万円も出せば十分じゃないかな・・。
そして最後に、スピーカー・・。
オーディオの華だが、ユニットは口径20cmのフルレンジでいいと思う。口径の大きなユニットに比べて明らかに利点もあるので、卑屈になる必要はまったくない(笑)。
オークションで2万円前後で行けるんじゃないかなあ。
そして、最後は箱ですね~。なるべく大きめの箱で口径20cmの穴が開いた箱を調達するのも良し、あるいは簡単な図面を書いて自作するのも良し、材料代はせいぜい1万円もあれば十分。
で、ほかには「DAC」と「アンプ」を結ぶRCAコード、そして「アンプ」と「SP」を結ぶ「SPコード」は、オークションで格安で手に入るはず。
以上、(テレビを除いて)、DACが4万5千円、アンプが3万円、SP経費が3万円、そしてケーブル代が光ケーブルも併せて2万5千円とすると、〆て「13万円」なり~。
始めの内はこれで5年ほど楽しめるはず。
そのうち、もっと欲が出てくるかどうかが「オーディオの泥沼」にハマり込む境目となる~(笑)。
こうして振り返ってみると「オークション」の重要性を身に沁みて感じるが、これも「当たりはずれ」があるので、何ごとにつけやはり第三者のアドバイスが必要だろう。
つまり、良きアドバイザーを得ることが「焦眉の急」となる。
商売っ気抜きで、そういう役目を果たせる窓口があるといいんだけどねえ。
ちなみに「ブログ情報」なんかはダメですよ~、やはり身近な存在として手取り足取りして教えてもらう信頼関係が必要。
あっ、そうそう、関連して最近読んだ「熱風の編集後記」という本の73頁に次のようなことが書いてあった。
「NHKスペシャルには数々の名作がありますが、僕が個人的に印象に残っているのは「驚異の小宇宙 人体」です。その中に、短期記憶障害という数分前の出来事を覚えておくことができなくなった人のエピソードがありました。
その人がどうやって記憶をしているかというと、自分の行った行動をすべてメモに書いて記録を残しておくのです。それらを集めた分厚いノートが彼の記憶なわけです。
また、記憶には脳が憶えている記憶と身体が憶えている記憶の2種類があって、身体の記憶は忘れることはないらしいのです。人間とは? 身体とは? ということを考えさせられた番組でした」
というわけで、人間は「脳の記憶」と「身体の記憶」がクルマの両輪みたいなものだろうが、一般的に後者の方がどうも軽んじられているような気がする。
「人間は身体で憶える」 → 「実際の現場で憶える」・・、オーディオなんかまさにそうじゃないかと思うんだけどなあ(笑)。
あっ、そういえば「脳を鍛えるには運動しかない」という本をいつぞやのブログで紹介したことがありましたよねえ~。
積極的にクリック → 
冬はどうしても「日光浴」が多くなる・・、するとついでに「読書」がついてくるというわけで、日常的に(オーディオとくらべて)読書の比重が時間的に増してくる。
これは喜ぶべきことなのか、否か、本人にはわからないのがつらい(笑)。
✰ 「音響・音楽心理学」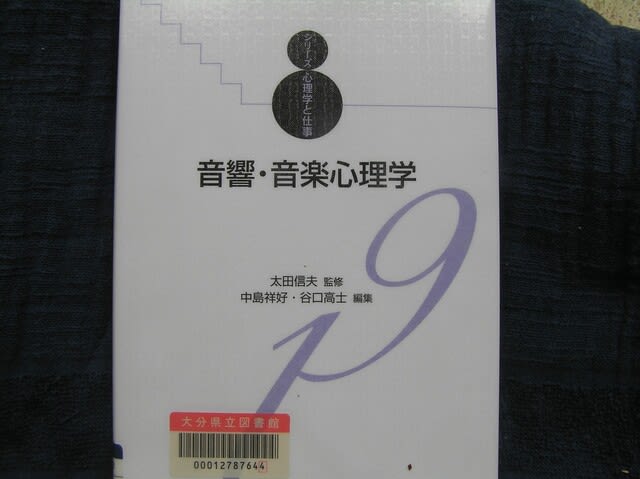
「音楽は好きだけど、大がかりなシステムで聴くのは億劫だ」という若者が増えているそうだ。
マンションや間借りなどの住宅事情もあるのだろうが、魅力あふれるオーディオを楽しむ層が減少していくのはやはり寂しい。
一介の「市井の徒」がそんなご大層なことを心配しても何の役にも立たないけれど、いずれ自宅のSPユニットや真空管などがオークション市場に出回ることになるだろうから、そのときに少しでも活気を帯びていて欲しいので満更無関係でもないだろう(笑)。
さて、このほど「音響・音楽心理学」に目を通していたら、今どきの「大学生」(平均年齢20歳)182名に対するアンケート調査の結果が記載されていた(P156)。
「音楽を毎日聴く」「ときどき聴く」を合わせて83%に上るほど、音楽の人気は高い。
その一方、「利用するオーディオ機器」の割合となるといささか寂しい結果が明らかとなった。
割合の多い順に羅列すると次のとおり。
「コンポ:34%」「カーステレオ:19%」「携帯電話15%」「パソコン:14%」「ウォークマン:11%」「iPod:5%」「その他:2%」と、いった具合。
興味深いのは「カー・・」「携帯・・」「パソコン」などで66%と半分以上を占めていること。
これらの層をいかに「コンポ」へ引きずり込むかが、オーディオ衰退の防止策となるのだろう。
たとえば低価格でも性能が良くてコスパに優れた「コンポ」をいかに普及させるか・・。
ただし、若者たちからは「パソコンの音質で十分です。なぜそんなにシステムに拘るんですか?」と、問われる可能性が高い。
そこで「システム次第で音楽から受ける感動はまるっきり違ってくるんだから・・、百見は一聴にしかず、ぜひ近くのオーディオ愛好家の情報を調べて聴きに行ってごらん」と答えるしかない。
ほんとうは「オーディオ・ショップ」にその役割を果たしてもらいたいのだが、商売気が加わるのでどうだか・・。
人間疎外の「デジタル社会」に潤いをもたらす音楽の役割は増えることはあっても減ることはないんだから、まだチャンスは残っている・・、ま、結局は要らん世話だけどね(笑)~。
✰ 「日々翻訳ざんげ~エンタメ翻訳この40年~」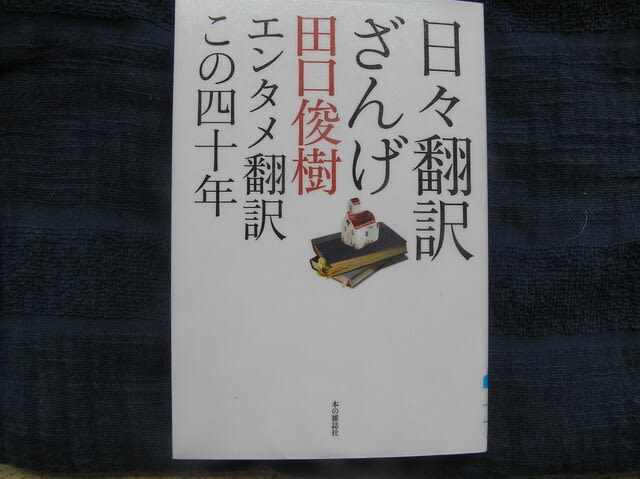
たいへん興味深く読ませてもらったが、31頁に次のような記述があったのでご紹介しよう。
「”は”と”が”の問題というのは日本語表現の永遠のテーマのように思うが、その使い分けについては私は次の二つの定義を一番のよりどころにしている。
ひとつは国語学者、大野普先生の有名な定義、未知の主語には”が”つき、既知の主語には”は”がつくというやつ。
<昔々、あるところにお爺さんとお婆さんが住んでいました。お爺さんは山へ芝刈りに、お婆さんは川へ洗濯に行きました>
という説明を初めて知ったときには軽く感動した。最初のお爺さんとお婆さんはまだ未知の存在だから”が”で、二番目のお爺さんとお婆さんは既に分かっている既知の主語だから”は”になるというわけだ。何とも明快である。
もうひとつは作家の井上ひさし氏の”は”はやさしく提示し、”が”は鋭く提示するというものだ。大作家の感性が光るこれも明解な定義である。
”は”と”が”の使い分けに迷ったときには、この二つの定義を思い出せばだいたい解決できるはずである。
ついでにもうひとつ言っておくと、”は”と”が”の使い分けに迷うのはたいてい言いたいことがハッキリしていないときである。
ということだった。
自分のケースで言わせてもらうと、たかがブログにしろ17年もやっていると、これまで「は」と「が」の使い分けについては「何となく」カンに頼ってきたものの、こうして明解に指針を提示していただくと非常に分かりやすいし、頭の訓練にもなる。
これだから、ブログは(が)止められない(笑)。
積極的にクリック → 
前回のブログ「新春早々の快ヒット」は珍しくアクセスが好調だった。
オーディオ記事は総じて「人気が無い」 のだが、いったいどこがどう読者のお気に召したのやら・・、さっぱりわからないが歓迎すべきことには違いない(笑)。
で、話題の中心はネットオークションで調達した「無銘のユニット」(口径25cm)にあり、格安(3000円)だったのはご記憶に新しいところ。
すると、さっそくメル友の「M」さん(奈良県)から以下のとおりご教示があった。ちなみに、「M」さんはバッハを筆頭に生粋のクラシック派である。


〇〇さんのブログ写真から一致します。
コロンビアデンオンですのでOEMであり多分フォステクス製か東洋スピーカー製だとおもいます。
低域の深み
優れた音響特性
従来の振動板に比べて軽量
耐久性が高い
コラーゲン振動板スピーカーは、高音質を求めるオーディオファンに人気があるそうです。
カタログの特徴なりをみますと音の良さそうな・・・・・・!
ハイ、どうもご丁寧に・・、ありがとうございます!
そうですか・・、デンオンでしたか。さっそくネットの「オーディオの足跡」を確認。
「コーンには、動物の皮に特殊な化学処理を施し、コラーゲン繊維としてコーン紙に融合したものを採用しており、適度な内部抵抗を持たせる事で、ピークやディップの共振を抑えています。」
(「適度な内部抵抗」・・、実に奥が深い言葉ですね!いろんな連想が広がります)
というわけで、「いい音」の要因が解明できました。
さらに、諸元を見てみると「クロスオーヴァー」が750ヘルツに設定されていることが判明した。
あれ~、我が家ではおよそ3000ヘルツで設定しているので大きな違いだが、取り立てて違和感はないのでその辺は図体の大きな箱の容積でカバーしていると理解させてもらおう。

それにしても、「少ない経費でオーディオを楽しむ」には「スピーカー弄り」に尽きるようですね。
とはいえ、「俺は金持ちなのでコスパなんかどうでもいい」という方もいらっしゃるだろうが、「お金」という制約があるからこそより一層切実感が増して工夫に妙味が出てくると思うけどなあ。
そして「スピーカーだけは専門業者に任せて手を出さないようにしている」という方が大半だろうが、もったいないことです。コストに妥協している業者が大半ですからね。たとえば「箱」の容積なんか最たるものです。
(スピーカー弄りは)音の変化もいちばん大きいし、お薦めですよ~。

我が家には6系統のスピーカーがあるが、「この二つがあればもう十分だなあ!」と思わせるのがグッドマンの「TRIAXIOM]と「AXIOM80」。
「またか、もうウンザリだ・・」、まあ、そういわずに(笑)。
両方とも自作の箱(板厚1.2cm)なのでちょっと見た目が悪いが、気に入った音さえ出てくれれば、それでいいと割り切っているつもり・・。
で、元旦から「TRIAXIOM」にじっくりと向き合っていたものの、さすがに1週間ほど続くと、また ”そぞろ” 浮気の虫が・・(笑)。
オーディオに限っては「即行動派」なので、昨年末(2023)から気になっていたスピーカーを引っ張り出してユニットを交換した。新年になってからの初仕事である。


画像左が改造前で、右が改造後の姿。サウンドの死命を制するコーン型ユニットの交換である。
左側のJBL「D123」(口径30cm)をフルレンジで使っていたのだが、やはりこのユニットをフルレンジで使うのは拙かった・・、2日ほど聴いていると中高音域の粗さが目立ってきた!
「LE8T」(口径20cm)の感覚で対応したのが間違いの元で、このユニットはやはりクロスオーヴァーが500ヘルツ前後で使うべきだったと素直に反省。
ただし、そうなると「200~4000ヘルツの間にマグネットの違うユニットを混ぜ合わさない」という、ささやかな我が家のポリシーに違反するのがつらい。
そこで、窮余の一策・・。
「D123」を交換して昨年のオークションで調達した「ユニット」(口径25cm)に交換してみた。
「ウーファー専用」に惹きつけられてゲットしたのだが、無銘のユニットなのでお値段は3千円(ペア)ぐらいだったかなあ・・、立派な「アルニコマグネット」付きにしては信じられないほどの超安っ(笑)。
おそらく周波数帯域は上限がせいぜい3000ヘルツくらいだろう・・、そこで「075ツィーター」を5μFの「ブラックタイプ」のコンデンサー(ウェスタン製)を使って5000ヘルツあたりに下げて使うことにした。
無銘のユニットには「2A3シングル」アンプ(出力管:VISSEAUX刻印)をあてがい、075ツィーターには定番の「71Aシングル」を~。
これで、ワクワクしながら耳を傾けてみると、驚いたねえ・・。
音に生気があるし、反応が早いし、バランスがいいし・・、それに「075ツィーター」との相性もバッチリ~。
もしかして「TRIAXIOM」よりは上ではないかしらん・・、と思えるほどのサウンドだった。
オーディオの場合、迂闊に決めつけるのは止した方が良さそうだね、特に移り気な人間には~(笑)。
そして、独特のスッキリ爽やか感は「075ツィーター」の賜物だろう。
「71A」のアンプを使うとヴァイオリンの音色がことのほか麗しく聞こえてクラシックも十分行けるし、もちろんジャズやポピュラー、歌謡曲もすべてOKで苦手なジャンルが無いのもありがたい。
それにしても、この無銘の25cmユニットにはつくづく考えさせられた。とんだ「掘り出し物」で、やっぱりオーディオはお値段ではないですねえ・・。
新年早々の快ヒットにすっかり気を良くして、今年もがんばるぞ~(笑)。
積極的にクリック → 
このところ聴く機会が多いのがフランスの作曲家「ラベル」のボレロ。
凄い別嬪さんの指揮者なので「目の保養」と「耳の保養」を兼ねているのは「言わずもがな」かな(笑)。
で、ラベルといえば、世紀の大指揮者フルトヴェングラーが「高雅で感傷的なワルツ」をこよなく愛していたことが知られているが、惜しいことに「フルトヴェングラー全集」(107枚)には収録されていない。

(ローマ教皇に「フルトヴェングラー全集」を進呈するメルケル首相)
しかし・・、おぼろげな記憶とともに、たしか持っていたはずだがと探してみるとありました!
「ドビュッシー・ラベル全集」(全8枚組)の6枚目に収録されていた。トラック番号9~16で8節に分かれ全体で16分ほどの小曲。
指揮者はジャン・マルティノンで演奏はパリ管弦楽団。さほど有名な指揮者でもないし、なぜこの全集を購入したのか今となってはさっぱり思い出せない。
強いて挙げれば、ドビュッシー・ラベルともフランスの作曲家であり、それならば指揮者もフランス人がよかろうという程度かな。
この全集ではドビュッシーの曲目が4枚、ラベルが4枚という構成になっており、折角だからこの際ラベルをすべて聴くことにした。
収録されていた曲目は次のとおり。
<5枚目>
✰ ボレロ ✰ 海原の小舟 ✰ マ・メール・ロワ ✰ スペイン狂詩曲
<6枚目>
✰ シエラザード(序曲) ✰ ラ・ヴァルス ✰ クープランの墓 ✰ 古風なメヌエット ✰ 亡き王女のためのパヴァーヌ ✰ 高雅で感傷的なワルツ
<7枚目>
✰ ダフニスとコロエ
<8枚目>
✰ 左手のためのピアノ協奏曲 ✰ ピアノ協奏曲
ボレロ以外は親しみやすい旋律も特になかったが、よく聴いているうちに何だか「精巧に出来たジグソーパズル」を見ているような感じがしてきた。
一つ一つの複雑なピース(音符)が隙間なく埋められていく印象で無駄な音符が一つもなさそう。
明らかに日頃聴き慣れたドイツの作曲家たちとは作風が違うが、これはこれで悪くない。
気になったので作曲家「ラヴェル」をググってみた。
モーリス・ラヴェル(1875~1937)。
手短に表現すると、「オーケストレーションの天才」「管弦楽の魔術師」で、ドビュッシーと同じ印象派に属する(やや微妙な色分けがあるようだが)とある。印象派とは一言でいえば、気分や雰囲気を前面に押し出す音楽のこと。
前述したように、フルトヴェングラーは演奏会のプログラムに入ってもいないのに、ベルリンフィルの楽団員にしょっちゅうこの曲目を演奏させていた。
その理由というのはラヴェルの音楽を愛していたからと言われているが、併せて「オーケストレーション」の妙味を通じて指揮者と楽団員との呼吸(いき)を合わせていたのだろう。
で、ラヴェルの精緻な音楽は数学者の複雑な数式にも通じるところがあり、ラベルの風貌にも何だか厳格な数学者を連想させるとは思いませんかね。
そういえばフランスは幾多の高名な数学者を輩出している。
ググってみると17世紀~20世紀前半で、画期的業績を残した世界的数学者を列挙すると、数ではフランスが圧勝、次はドイツとイギリスとあった。
まさに、知的なヨーロッパの代表選手であり、代表的な数学者としては「デカルト」(座標系)、「フェルマー」(最終定理)、「パスカル」(定理)、「フーリエ」(級数)、「ポアンカレ」(予想)など。
「数学は音の基礎」と言われているが、ラベルの精緻な音楽はそれを体現しているのかもしれないですね。
それにしてもかっての「栄光の国」フランスは国際社会の中で段々と影が薄くなっているような気がする、なんといっても底力があるんだからもっと存在感を高めて欲しいなあ・・、日本も同じだけどね~。
積極的にクリック → 
かなり昔の話だが「企業は人なり」という言葉をよく聞かされたものだった。
その言わんとする意味は次のとおり。
「経営の神様と讃えられた松下氏は、折に触れて「企業は人なり」と説いていました。 つまり、「事業は人を中心として発展していくものであり、その成否は適切な人を得るかどうかにかかっているといってもいいだろう」と語り、「やり方しだい、考え方しだいで、その持てる力をいくらでも引き出し、発揮させることもできる」と言うのです。
まあ、一言でいえば「人材育成の重要性」を説いたものだが、現代ともなると「AI」を使いこなす方向へと比重がかかり、もはや「死語化」しているように思えるが、ふと「音は人なり」という言葉が脳裡に浮かんでしまった。
というのも、先日の「オーデイオ愛好家のネットワークづくり」に関して横浜在住の「K」さんから次のメールをいただいたことにある。
「旅行ついでにaudio試聴」アイディアは良いと思いますが、人と人との相性はオーディオの世界も同じ、ここが難しそうと感じます。」
なるほど・・と思い、次のように返信した。
「人と人との相性は盲点でした。たしかに・・。いちばん読みづらいのが人間の心理状態ですからね。旅先で不快な思いをするぐらいなら訪問しない方がマシ・・、分かる気がします。
自惚れ混じりながら、わりかし自分は常識派と思ってますが、♪人生いろいろ、男もいろいろ♪・・ですかね~(笑)」
で、「音は人なり」について少し分け入ってみよう。
もちろん仮定の話だが「ネットワークづくり」において、「他人に聴かせてもいい」と、自ら進んで登録するぐらいの方だから相当の自信家には違いない。
ただし、それが表(態度)に出るかどうか・・。
最初から「どうだ! メチャいい音だろうが」と異論を挟ませない態度で出てこられたら、それがたとえ「いい音」であったとしても、少し怯みますよね、いや怯むどころか反発する方だっていることだろう(笑)。
で、所詮は電気回路を通した音に「生の音」の再現性は無理なんだから、いくばしかの謙虚さが必要だし、その謙虚さがその人が鳴らす音に滲み出てくる・・、というわけで「音は人なり」。
我が家で英国系サウンドを愛する理由の一つがここにある・・、おっと何も自慢しているわけではないですからね(笑)。
穏やかで控えめ、しゃしゃり出てくるような様子が微塵も無く、大向こうを唸らせる様子もない・・、それかといって噛めば噛むほど味が出てくるし、過去の幾多の失敗や悔いを「そうかそうか」と慰めてくれるような音・・。
私はそういう音を出したい(笑)。
というわけで、一事が万事である。
「音の交流=人生の交流」だとして、その人が出す音の背景に複雑な人生観が横たわっているとすると、迂闊に他人には聴かせられない、という見方も成り立つ。
たとえて言えば、赤の他人から蔵書を覗き込まれるようなもの・・かな(笑)。
そういえば、「音楽&オーディオ」の先達だった「五味康佑」さんが「単に音とはいえ他人に聴かせるのは怖いことだ」と述べられていたことを思い出した。
お互いに異文化を背負った人間同士の交流って何だか難しそう・・、とりわけKさんみたいにナイーブな方もいらっしゃるし~(笑)。
とはいいながら、その一方では「何も難しく考える必要はないだろう、たかが音だぞ!」という方もおられるだろうし~。
皆様のご意見をぜひ拝聴したいですね。
さいごに、今回のブログはいつもより2倍も時間がかかりました、すこし理屈っぽかったかなあ~(笑)。
積極的にクリック → 
日常生活の中で毎日同じパターンを繰り返すのは「良くもあり、悪くもあり」で一概に是非を決め付けられないが、ただひとつどうしても「マンネリ化」という謗りは免れない。
ほら、オーディオでも毎日同じ音ばかりでは飽きてくるでしょうが・・(笑)。
で、そういうときは何らかの気分転換を促進するグッズについ助けを求めたくなる。
たとえば・・
☆ ランニングシューズをゲット
中高年にとって健康対策の基本がウォーキングということに異論を挟む方はまずはおるまい。
我が家でもせっせと励んでいるつもりだが、昨年の後半あたりから1日当たりせいぜい5000歩前後に留まっている。せめて8000歩前後にはいきたいものだがどうも意欲が湧かない・・。
そこで気分転換を図ろうと、思い切って「ランニング・シューズ」をゲットした。この2日の早朝に到着。
これまで履いていたシューズはオーディオ以外に金を突っ込むのは嫌なので3千円前後の代物だったが、今回は思い切ってエイヤっと奮発した(笑)。
で、「ランニング・シューズ」というのがミソで、爪先の方にかけて反り上がっているので、地面からの足離れがとてもスムーズで何だか歩くのが楽しくなる。
ほら、オーディオでもスピーカーからの「音離れがいい音」ってありますよね、スカッと爽やかな音・・。
その一方では(スピーカーに)べたっと張り付いたような粘着質の音もあるが、前者の方が断然いいに決まっている!
そして、このシューズのおかげで今のところ毎日8000歩前後をキープしているのだから、メデタシ、メデタシ。
こんなことなら早く購入すればよかった・・(笑)。
☆ 日光浴のための木製椅子
以前のブログで「太陽の光は最高の栄養です」という投稿をご記憶だろうか。
念のため、かいつまんで再掲しておくと、
著者は医学博士だが、どうせ魚とか野菜とかの食べ物を紹介した「ありきたりの健康本」だろうと、手に取ってざっと立ち読みしたところ「太陽の光こそ最高の栄養です」とあって、ちょっと毛並みの違う本だと借りることにした。
ぐだぐだ書いても、どうせ読みづらいだろうから気になる部分を脈絡なしに箇条書きしてみた。
ただし、真に受ける、受けないはあなたの自由なので念のため~。
✰ 紫外線によって皮膚で作られるビタミンDは我々の免疫力を維持するために欠かすことのできない最高の栄養であり長寿ビタミンだ
✰ 日焼けした「うつ病」患者はいない
✰ 血中ビタミンD濃度が低いと動脈硬化が進み炎症が起きやすくなる
✰ コレステロールはビタミンDの原料になるのでむやみに下げない方が良い
✰ 国民病ともされる糖尿病は血中ビタミン濃度が低いと発症しやすい
✰ 食物からビタミンDを取るとすれば鮭などの魚がいい
✰ ビタミンDの最も注目すべき効果は免疫をコントロールする力にある
✰ 日光浴は週3日、「長袖長ズボン」の場合は15分以上、「半袖半ズボン」の場合は7分以上、それ以上浴びると皮膚にとって有害となる照射時間は40分が目安
✰ 最終章では平均的な数値の指標で「血中ビタミンD濃度」と「新型コロナウィルスによる死亡者数」との相関グラフが示され、前者が低い国ほど死亡者数が多いショッキングな事実が示されている。
というわけです(笑)。
で、我が家でもささやかながら日光浴を実行しておりますぞ。

7月~9月の日光浴は自殺行為だが、太陽が少ない冬のシーズンは、天気のいい日に、こまめに「二階のベランダ」に上って、折り畳み製の簡易「椅子」(画像)を使い、頭には帽子を被り、膝から下はすべて剥き出しのままにして「読書」に耽りながら日光浴~。
借りてきた図書館の本を返却期限内に処理するのにも役立つので一石二鳥ですぞ~(笑)。
積極的にクリック → 
大晦日(2023)のことだった。
この1年間の「お礼」と「来年も引き続き・・」ということで、オーディオ仲間のNさん(大分市)にご連絡。
型通りの挨拶が済んでから「何か変わったことはありませんか?」
「これまで使っていたプリアンプを全面的に見直したよ・・」
えっと、思わず生唾をごくりと飲み込んで「それで、音の方はいかがですか?」「これまでで最高の出来だと思うよ!」「それはぜひ聴かせてもらいたいですね、今日の午後はいかがですか」「ああ、いいですよ」「ついでにYさんも誘ってみます」
で、予想通りYさんは一つ返事だったので、話がバタバタとまとまった(笑)。
昼食時に「おい今日の午後からNさん宅へ行ってくるからな」「まあ、大晦日にですか・・、奥様から嫌がられますよ」と眉を顰(ひそ)めながら舌鋒鋭く家人が宣うた。
「大丈夫だろう・・、典型的な夫唱婦随のご一家だからな」「・・」。
すんでのところで「我が家と違ってな・・」という言葉を飲み込んだ(笑)。
というわけで、途中でYさんを拾いクルマで40分ほど走らせたが、さすがに大晦日とあって普段より混んでいたが溢れる熱意でかきわけて進んだ。


ここをどうしてこうして・・という技術的な話はYさんとNさんの間で大いに弾んでいたが、こちらはまったく蚊帳の外でサウンドに耳を傾けるだけ。
たしかに、これまで聴かせていただいた音とは一皮剥けた感じで、鮮度といい、勢いといいGOODの一言だった。
とはいえ・・、いかにアルテックといえども「口径38cm」のユニットにはどうしても拒否反応が起きてしまう・・、そしてクロスオーヴァーも500ヘルツだから、そもそも我が家のスタイルとはまるっきり違う。
おそらく大多数の方々は「とてもいい音だ」と拍手喝采だろうが・・。
しかし、いい耳の保養をさせてもらった。そのうち、このプリアンプを我が家に持ち込んで「AXIOM80」を聴かせてもらいたいなあ。
ただし、欲しくなるとヤバイしねえ・、やっぱり「聴かぬが花」かな~(笑)。
というわけで、一年の締めくくりは他家のサウンドの試聴だった。
そして我が家では元旦明けの2日からじっくり聴いているのが「TRIAXIOM」(グッドマン)である。
板厚「1.2cm」の箱の補強が済んでからというもの、その様変わりしたサウンドにはぞっこんである。
同じグッドマンの「AXIOM80」が「神経質な秀才」だとすると「人格円満な優等生」という感じで、妙な気を使わなくていいので長く付き合いたくなる・・。
で、改めて手持ちの9台のアンプの中でどれがいちばんマッチングがいいのか、正月早々からテストしてみた。
トップバッターは「PX25シングル」である。
当初は前段管に「LS7」(英国GEC)を使っていたのだが、相性がイマイチの感じがして「3A/109B」(英国STC)に変更した。
画像の下段、一番左が「LS7」でその右側が「3A/109B」である。μ(ミュー=増幅率)に応じてアンプに切り替えスイッチが付いているので便利~。
すると、あまりの変わり様に驚いた。
プリアンプの改造や箱の補強などのオーディオ環境の変化が功を奏したのだろうか、名管とされる「3A/109B」の面目躍如で何ら過不足のないサウンドに心の底から痺れあがった。
いわば「人格円満な優等生」に「リーダー的な資質」が加わった感じかな~(笑)。
「これで決まり~、他のアンプのテストは必要なし」と高らかに宣言!
で、不要となった「LS7」だがオークションにでも出そうかな、希少なナス管なのでいい値段がするかもねえ・・と、捕らぬ狸の皮算用~。
これまでの恩義を忘れて・・、いささかドライで冷たいかもね~、ただし人間には優しいんだけどね(笑)。
で、ミューはどのくらいかなとネットで調べていたら、この「LS7」を出力管として使っているアンプを発見。
ほう、出力管として使う手があったか・・、そこで我が家で応用できそうなアンプといえばこれかな。名門「TRIAD」の出力トランス(プッシュプル用)が使ってあるのがミソ。
さっそく大晦日に訪問したNさんに連絡した。
「電圧増幅管のLS7ですが、出力管として使いたいので6SN7の代用として使えませんかね?もちろんソケットの交換が必要ですが・・」、「ああ調べてみよう」
もしうまくいけば、2024年の「大当たり」になりそうな予感がする。
元旦早々の「2024オーディオ展望」ではこの件には全く触れなかったので、まったく移り気そのものだが、我が家では万事がこういう調子。
これを「刹那(せつな)主義」というのだろうか(笑)。
積極的にクリック → 
昨年(2023年)の29日(金)に帰省し、この3日(水)に風のように去っていった娘・・、まさに「Gone with the Wind」でした。
毎日、通勤電車(新幹線)の中で親父のブログを「無事の便り」として目を通しているそうだが、ことオーディオの話となると「サッパリわからない!」と匙を投げている(笑)。
そりゃそうだろう、かなり専門的な世界だから素人さんにはチンプンカンプンのはず。しかし、唯一の後継者がこれだから没後のオーディオ機器の運命となると・・。
いや、「血筋」よりも「熱意」優先で、愛情のある人に使ってもらえればそれでいい・・。
さて、年始の恒例となった「オーディオ・ネットワークづくり」の提唱だが、今年はありがたいことに海外から「大賛成」の激励が届いた。
お馴染みの南スコットランド在住の「ウマさん」・・。
「全国のオーディオ愛好家のネットワークづくり」…

はい、大好きなイギリスの「ご来光」を拝めるなんてとても幸運です、そして励ましに大きな勇気をいただきました。
どなたか、ビジネスチャンスとして始めないかなあ~。
もちろん根底には「落ち目のオーディオ」を盛り上げ、ひいては豊かな心と潤いのある社会づくりに貢献するという「大義名分」があるんですけどね(笑)。
で、広報はこのブログにお任せくださいな。こんな拙いブログでも1日当たり1000人前後の読者がおられますからね、アハハ~。
最後に、父娘そろって大の「ミステリファン」だが、今年も娘が「このミステリがすごい!」を持って帰ってきた。
国内編と海外編に分けて年間のベスト20までが紹介されている。
いつも上位で紹介されたミステリをチェックして大いに参考にさせてもらっているが、物事にはすべて「当たりはずれ」があるようにミステリも例外ではなく、下位の順位でも逆転現象があったりするので図書館で見かけたら借りることにしている。
とりあえず「ベスト5」を紹介しておこう。
<国内編のベスト5>
1位 「可燃物」(米澤 穂信)
2位 「鵺(ぬえ)の碑」(京極 夏彦)
3位 「あなたが誰かを殺した」(東野 圭吾)
4位 「エレファント ヘッド」 (白井 智之)
5位 「アリアドネの声」 (井上 真偽)
次に<海外編のベスト5>
1位 「頬に哀しみを刻め」 S・A・コスビー
2位 「ナイフをひねれば」 アンソニーー・ホロヴィッツ
3位 「処刑台広場の女」 マーティン・エドワーズ
4位 「愚者の街(上下)」 ロス・トーマス
5位 「トゥルー・クライム・ストーリー」 ジョセフ・ノックス
積極的にクリック → 
元旦、そして2日と九州は絶好の天気に恵まれて、今年は幸先が良さそうだと内心ほくそ笑んでいたら、なんと北陸地方で「大地震」・・、しかもよりによっておめでたい元旦に起きなくていいのに~。
被災者はじめ関係者の方々のご無事とご労苦をはるか遠方の地から偲ばせてもらいます。
さて「1年の計は元旦にあり」という言葉があるが、近年は情報が溢れるとともに世の中がハイスピード化になったせいか「そんな1年も先の悠長なことは言ってられないよ」とばかりに、かなり「死語」化しているように思う。
とはいえ、我が家の「時間軸」ではまだこの言葉が立派に生きているので、年頭にあたって今年の「音楽&オーディオ展望」を見渡してみよう。
ただし、オーディオの場合「オークション」で「掘り出し物」が見つかれば見境なくバッタのように飛びつくので「成り行き任せ」みたいなところがありますけどね~(笑)。
それでは、まずオーディオの微小電流を扱う音の入り口からいくと、
✰ 音の入り口
我が家の音の「入口」は現在「CDトラポ」と「You Tube」(「ブルーレイとテレビ」の2系統になっている。
このところ起き抜けに「ブログの投稿」作業をやっているのでシステムのスイッチを入れるのは朝食後にというパタ~ン。
2系統の内で首を傾げるほどの「音の差」はないので、どうしても便利さの方を優先して「You・・」が活躍しているかな。
たしかにハイレゾの時代に今さら「CDトラポ」でもあるまいと思うし、実際に高級な「CDトラポ」の新製品がまったく出回らなくなっている。
ただし、長年の習慣で「回りもの」が無いと寂しい気持ちがするのも事実なので(CDトラポは)新規購入はしないまでも故障したら即修理という態勢だ。
現用の「CDトラポ」はCECの「TL3 3.0」(ベルトドライブ方式)でほぼ満足している。もう1台の「ヴェルディ・ラ・スカラ」(dCS)の方は一昨年修理を終えて戻ってきたものの図体がかさばるのでスペアという感じ。
✰ DAコンバーター
周知のとおり、デジタル・オーディオの要となる機器である。
現用中の機器は4台あって「エルガー プラス」(英国:dCS) と「HD-7A192」(フェイズメーション)、2021年の夏に仲間入りした「A22」(GUSTARD)、そして昨年末に新調した「SMSL」の最新機種。
で、現在の主力となっているのは「エルガー・・」と「SMSL」で、電源コードに「ドミナス」(PAD)をあてがっているが今のところ満足しているので不変のままいくつもり。
✰ プリアンプ・パワーアンプ
音の増幅部分に当たるが、9台の中で今のところ不満なアンプはないし、性能的にもさしたる不満はないので新規購入はまったく考えてない。
むしろ、その逆でぼちぼち縮小整理する方向で考えているが、どれも愛着があってなかなか・・(笑)。
✰ スピーカー(ユニット+箱)
最後はオーディオの「華」ともいえるスピーカーで、これを代えると本質的に音が様変わりするので一番味わい深いところ。
ただし、今のところユニットは特に欲しいと思うものが無く、問題は箱である。
ぜひ、グッドマンの「AXIOM80」と「TRIAXIOM」の箱を板厚「1cm」の「楓」(カエデ)材で作ってみたい。
ほら、ヴァイオリンだって薄い板厚で共鳴させて美しい響きを出しているんだから、スピーカーも楽器の延長みたいなものだと考えれば理に適っている。
オーディオの最後に行き着くところは、「箱」であり、その「内容積」、「板厚」と「素材」そして「背圧の逃がし方」ではないかと常々考えている。
いわば「音の響き」の点において、いかなる機器を新調したり弄り回したりするのと比べて「箱の細工」を工夫する方が根源的に軽く凌駕している。もちろん「独断と偏見」ですけどね~(笑)。
いずれにしても、オーディオ機器の存在を意識させず、音楽に純粋に浸れるシステムこそが望むまれるところです。
そして、さいごに音楽展望だがもちろん「You Tube」が主体となり、膨大な音楽情報の中から我が家なりの小さな宝石を見つけていくつもり。
浜の真砂(まさご)は 尽きるとも 世に音楽&オーディオの種は 尽きまじ(笑)
積極的にクリック → 
頂いた年賀状の中で「後期」高齢者を、あえて「高貴」高齢者と表現したのがあって、思わず笑ってしまった。
75歳以上は保険の負担が割増されるので「高貴」な存在かもですねえ。
さて、ここ5年ほどのことだが年始になると「新春初夢物語」と題して同じ内容を繰り返して投稿している。
繰り返し、繰り返し・・、懲りずに継続することに意味がある(笑)。
で、今年も懲りずに以下の通り投稿させてもらおう。
大好きな音楽がより身近にそしてより魅力的な存在になるかどうか、それはひとえに「オーディオシステム」のレベルにかかっているといっても過言ではあるまい。
そういう点でシステムの責任は重いが、それは本人の熱意はもとより、ある程度「情報網」で成り立っているという事実も争えないところ。
たとえば、その源としてのオーディオ専門誌、ブログ、仲間などからの情報が挙げられるが、やはり「百見は一聴に如かず」で実際に現場で聴かせてもらうのがいちばん有効ではないかといつも思う。
そこで、少しでも現場体験を増やすためにはどうしたらいいか、その「仕組み」づくりとやらを卒爾ながら提案してみよう。
それは、一言でいえば「全国のオーディオ愛好家のネットワークづくり」である。
自分の好きな音楽を少しでも「気に入った音で聴きたい」と、オーディオシステムを熱心に弄るのが「オーディオ愛好家」だとすれば、出来るだけ自分の殻に閉じこもらず広く他人のシステムを訪ね歩いて聴かせてもらい自らの「糧」にするのが一番望ましいし、効率的ではなかろうか。
もちろん、日頃とはまったく違う音質に接することも参考になるが、システム構築のノウハウの情報交換もたいへん貴重だと思う。
つまり、国内を観光旅行する機会があればその傍ら、そういった見ず知らずのオーディオ愛好家を気軽に訪問して聴かせてもらう交流の仕組みがあってもいいのではなかろうか。
そのための「ネットワークづくり」となる。
具体的には、まず事務局を置く。オーディオ訪問を希望する側と受け入れ可能側の両方の登録(身元確認)を行う。基本的に「やり取り」はすべてメールだ。
登録料を納める。
具体的なやり取りは次のようになる。
1 事務局あてにメールが届く。「今度、〇〇方面に観光旅行に行くのですが、試聴可能の愛好家がおりますか。」
2 「ハイ、3名の方が登録されています。好きな音楽のジャンル、システムの概要、部屋の大きさなどはそれぞれ次のようになっています」と申し込み者に提示。
3 訪問者側から「検討の結果、AさんとBさん宅に訪問したいのですが」と、メール。
4 それではAさん、Bさんのメルアドを教えますので訪問日時などは具体的に双方で連絡し合って決めてください。
5 訪問終了後に双方の側から相手の印象度について「総合評価」(5点満点)を事務局あていただく。
「5点」非常に良い 「4点」良い 「3点」普通 「2点」悪い 「1点」非常に悪い
「2点」以下が2回に達した者は登録料返還のうえ抹消とする。
とまあ、かなりいいアイデアだと自惚れているが一番大切なことを忘れていた。
誰がこんな「1円の得にもならない」仕組みの勧進元になるんだろうか(笑)。
ヤル気のある「メーカー」さんか「オーディオショップ」さんとか、どっかいないかな~。機器の売り上げにも貢献できると思うんだけどなあ。
ちなみに、過去4年間の「反響」はまったくありませんでした(笑)。
そして、さらに ”グレードアップ” すると・・、
まず「音楽&オーディオ協会」を設立する。目的は音楽&オーディオを通じて豊かな心と潤いのある社会づくりに貢献する。
仕事の内容は、前述のネットワークづくりに加えて、物故した愛好家が事前に登録(機器の説明付き)していたオーディオ機器やソフト(レコードやCD)を遺族の希望に応じて、オークションに出品する手続きを代行する・・というもので、「事前登録」「遺族の希望」「代行」というのがポイントです。
こういう協会があったら、後顧の憂いなく命尽きる間際まで「音楽&オーディオ」を愉しめるんと思うんだけどなあ~(笑)。
積極的にクリック → 
















