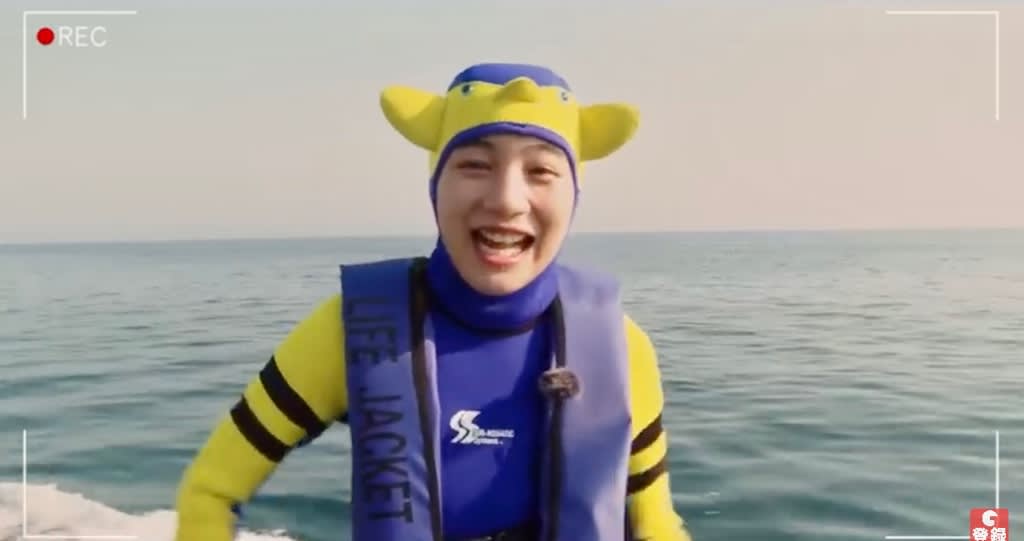

樹脂の黄ばみかと思っていたら、
本象牙の芯持ちでパティーナ
だった。
ような飴色変化だった。
う。
だが、もしかするとビッグ
ホーンの角である可能性も
ある。製造元は70年程前の
ブランズウィックだからだ。


は重量増しをしないとならない。
エンドキャップも装着する方向で。
ローズウッドの本ハギ四剣、ノー
曲がり一切無し。
そして、不思議な事にトビズレが


華台穴幅1.6-1.7玉。
トーナメントエディションよりも
かなり狭い。
ラシャもツンツルテンの速い物で
はない。
こういう環境が良い。
マスターが華台で撞かせてくれたが、
やはり本物の玉屋はいい。
チョークの手入れもきちんとして
いる稀有な店がふたつ隣り町にオー
プンした。まだ開業1ヵ月経たない。
本格派。
華台の穴の渋さはマスターの個人的
な好みで狭くセットしたらしいが、
撞球会クラブハウスの1番台よりも
狭い。良い。
華台のみは客の好みに合わせる必要
はない。全くない。
自分の店の特別台だ。オーナーが
好みのセッティングにするのが正統
だ。今の時代、主張なき迎合玉屋が
多すぎる。1台乃至2台のみは激ムズ
台にしてあったのが古くからの玉屋
のシキタリだったが、そうした店も
今では絶滅危惧種だ。
ところが、新規オープンの店で主張
ある昔ながらの本格玉屋がオープン
した。
自分に厳しくして、その華台で育て
ば道は開ける。
まず、チョークはきちんと手入れして、
タップも自分で完全適切に交換でき
るようになってからですね、玉撞き
は。自分の武具を自分で手入れでき
なくて戦いをしようなどというのが
そもそも心得違いだ。
さらに上級になると、自分で持ち台
のラシャ交換までできるようになる。
一般的には撞球者は自分の台は持っ
ていないので、できない。それは
チョークの手入れやタップの手入れ
とは大きく立ち位置が異なる。
武具は自弁。武具は己が状態を完備
させる。陣列の前に立たんとする者
にとっては当たり前のことだ。
三原のアミューズメントなどは
わけわからぬ連中がキューをこれ
まで3本折っている。店の物を。
チョークも着けずにキューを立て
て突っつき回すからラシャは摩擦
で破けまくっている。
日本語ろくに話せない東南アジア
人などは樹脂タップのブレイク
キューで玉を突くし、20代の若者
はカラーボールを集団で取り囲ん
で突っつき回している。
田舎の玉台置き場などそんなもんだ。
ゲーセンのエアホッケーやクレーン
ゲームと同じ感覚。
気に入らないと台を叩いたり蹴っ
たり、ラシャの上に飲み物のグラス
を平気で置いたりしている。
とんでもない大声で大騒ぎもする。
店の注意書きは各テーブルと壁に
貼ってある。
日本人の若い連中も日本語などは
読めやしないので文字は読まない。
躾も作法も礼儀も何もない野良犬
のような連中がそこで棒で玉を
どつきまわして大騒ぎしている
し、小さな投げ矢を投げて極限
バカ騒ぎをしている。
だが、田舎町なので、全日営業
している玉台置き場はそこにしか
ない。
本当のビリヤード場とは雲泥の
差だ。
本格玉屋に行くには、地元の町
から約40kmほど走らななければ
ならない。
東京、横浜、埼玉、名古屋、大阪、
京都、姫路、岡山、高松、徳島、
広島市、博多。
それらすべての場所で撞いて来たが、
やはり本物のビリヤード場が何軒
もある場所は良い。
Woodturning - Red goblet!!
職人技!木工旋盤で枝から真っ赤な
シャンパングラス!
電動横置きロクロを使って手作業
だけでこれを削り出してしまう。
なんざましょ。この技。
江戸時代の台所ーTime Travel Cooking Tourー
文化庁の動画。
日本には食の文化がある。
















