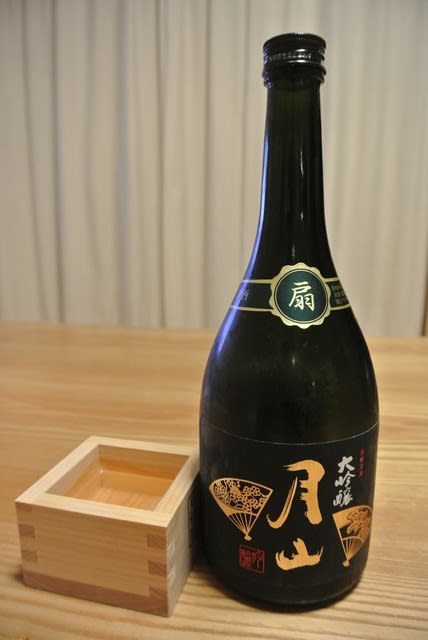15日(日)、被災地である西予市野村にボランティア活動に行った。
猛暑日で、みなさん冷たいものを求めていた。
そんなところへ、グッドタイミングで、軽トラを利用した給水車が回ってきた。
よく見ると知り合いの青木さん。
夫婦でボランティア活動をされていた。
その思いにふれ、とてもうれしくなった。

「冷たい飲み物はいかがですか?」
その言葉に誘われ、地元の人もボランティアも集まってくる。

「冷たい」
「おいしい」
「生まれ変わるー」
などありがたい言葉が、自然と出てくる。
そんな時、私の横を一人の迷彩色の服を着られた自衛隊員が通りかかった。
思わず、冷たい飲み物を軽トラから取り上げ、自衛隊員さんに駆け寄った。
「自衛隊員さん、お疲れさまです。
冷たい飲み物をどうぞ。」
するとその自衛隊員さんが言われた言葉に感激。
「いえ、私はかまいません。
みなさんでいただいてください。」
私はすかさず
「いえいえ、みなさん取られましたから、どうぞ。」
そして自衛隊員さんから返ってきた言葉は、
「私は戻ったらあります。お気遣いありがとうございます。」
この対応に胸が熱くなった。
そうして、何事もなかったように任務を続けられ、去って行った。
その後ろ姿に涙が出そうだった。

みんな、がんばっている。
みんな応援している。
私にもまだまだできることがある気がした。
岬人(はなんちゅう)
猛暑日で、みなさん冷たいものを求めていた。
そんなところへ、グッドタイミングで、軽トラを利用した給水車が回ってきた。
よく見ると知り合いの青木さん。
夫婦でボランティア活動をされていた。
その思いにふれ、とてもうれしくなった。

「冷たい飲み物はいかがですか?」
その言葉に誘われ、地元の人もボランティアも集まってくる。

「冷たい」
「おいしい」
「生まれ変わるー」
などありがたい言葉が、自然と出てくる。
そんな時、私の横を一人の迷彩色の服を着られた自衛隊員が通りかかった。
思わず、冷たい飲み物を軽トラから取り上げ、自衛隊員さんに駆け寄った。
「自衛隊員さん、お疲れさまです。
冷たい飲み物をどうぞ。」
するとその自衛隊員さんが言われた言葉に感激。
「いえ、私はかまいません。
みなさんでいただいてください。」
私はすかさず
「いえいえ、みなさん取られましたから、どうぞ。」
そして自衛隊員さんから返ってきた言葉は、
「私は戻ったらあります。お気遣いありがとうございます。」
この対応に胸が熱くなった。
そうして、何事もなかったように任務を続けられ、去って行った。
その後ろ姿に涙が出そうだった。

みんな、がんばっている。
みんな応援している。
私にもまだまだできることがある気がした。
岬人(はなんちゅう)