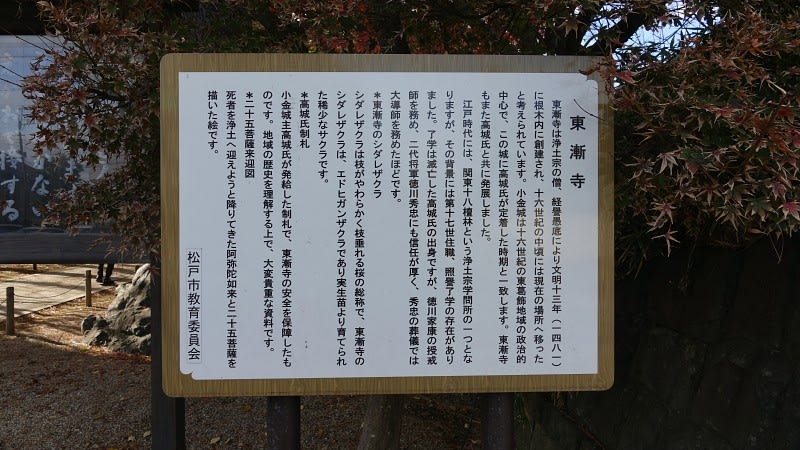4月になって桜も咲き始め、花好きにはたまらない日々ですね
その中から、ちょっとした話題をお送りします。
話題と写真が関係ないものもありますので、ご了承くださいね。
花びら
このほど、私が会員になっている尾瀬保護財団友の会から機関紙「はるかな尾瀬」が届いた
その中に面白い話が有ったので紹介します。
(ただし、著作権違反にならないように、概略のみで、あとは私が咀嚼して書きます)
その中の「尾瀬のミニ観察・総集編③」に「花びらって何?」と言う項目があり
花びらと言う言葉は、学術用語ではないので、花びらと花弁はイコールではなく
例えばニリンソウの花弁状の萼片を「花びら」と呼んでも何の問題もないという事です
ですから「花びら」と言って、「これは花弁ではなく萼片だよ」などと突っ込まれても
逆に「花びら」は「花弁」だけを意味していませんよ と逆襲できるというわけです。
花びらとは、花の目立つ部分を指し示す一般的な言葉で、植物学的に定義された
学術用語ではないとの事です。
花の種類によって舌状花冠とか、萼片とか、花被片とか、花弁とか呼ばれる部分は
みんな「花びら」でよいという事です。
最も植物用語になじんだ人には、かえって混乱するかな(笑)

田植えシーズンもまじかになり、福岡大堰の水門が閉じられ、小貝川の
水門上流が満水状態となり、まるで湖のようになった。
私が1月に撮影したキタミソウも、水底で休眠していることだろう。
(遥かに見えているのは筑波山)

福岡大堰の水門、水門の上が車道となっているが、すれ違いはできないので
対向車の有無を確認してから渡ること

福岡大堰から流れる用水路の堤防は、桜並木で桜の名所、まだ5分咲き程度

ボートに乗って桜を楽しむ親子、私は声をかけて撮影の許可を得て撮影している

庭に植えた「ユキワリコザクラ」朝の様子

ユキワリコザクラの午後の様子、花が開いた

ユキワリコザクラの葉柄に注目
「高山に咲く花」によれば葉身の基部が急に細くなって柄になるのが特徴と出ている
とは言っても、これは山新で購入したので園芸種だと思うので少し違うかも
ふちは折れ曲がらないか、わずかに曲がる と書いてあるが、これはすこし外に
曲がっているように見える。
ユキワリコザクラ、サクラソウ科サクラソウ属 分布 北海道、本州(東北地方)
日本固有種 基準標本 青森県七ノ戸山
同定のポイント 葉は薄く、卵形~楕円形。長さ1~4.5センチのはっきりした葉柄がある
低山帯~亜高山帯の岩場や乾いた草地に生える。
白花品はシロバナユキワリコザクラという。 以上山と渓谷の「高山に咲く花か」ら引用した

これは空き地に植えた「ミヤマホタルカズラ」これもポット苗で購入したもの
ようやく開花したが、土ぼこりで汚れている。私の好きな青色系だ

これは昨年植えていたイカリソウの園芸種「花吹雪」の花の表面
自分の庭なので、無理やり起こして花の表面を撮影した

上の写真の花をトリミングで拡大したもの。

以前にも紹介したタマザキサクラソウの濃色タイプ

タマザキサクラソウのシロバナ
ちょっとびっくりしたのが「イセヒカゲツツシ」蕾があるなーと思っていたら
フェンスの脇にいつの間にか花が咲いていた。
ヒカゲツツシと言えば、宇都宮市の古賀志山を思い出す。
地元の人たちは、サワテラシと呼ぶという黄色い花のつつじ
くらい沢を明るくする黄色いツツジにふさわしい名前だと私は思う。
このヒカゲツツジと霧島つつじは、キエビネの日影を作るために植えたが
あまり伸びないから、日影の役に立ってない。
考えてみたら、日影ツツジは自分も日影が好きなのかも😿
昨日、実は那珂川町のイワウチワ群生地に行ってきた。
メインはイワウチワではなく、今年の3月から開園した「うえまる花の丘庭園」の
様子見である。
ここを歩き回って気が付いたが、庭園の周りの舗装された農道の土手に
自生のアズマイチゲやアマナがびっしり生えていた。
(この舗装された農道は、
車両侵入禁止なので、歩いて登ること)
後で聞くと、キクザキイチゲもニリンソウも咲くという
ただ昨日は気温が上らず風も冷たくてアズマイチゲもアマナも開いていなかった
イワウチワの受付で聞くと、それらは全部自生だという
イワウチワの群生地に、ショウジョウバカマが植えられているが、全部植えたものではなく
植えた親株から増えて広がったものだそうである。
ショウジョウバカマは、タネだけではなく根生葉の先に不定芽ができて広がるので
増えるのが早いらしい。
ミスミソウは愛好家からの提供だという。