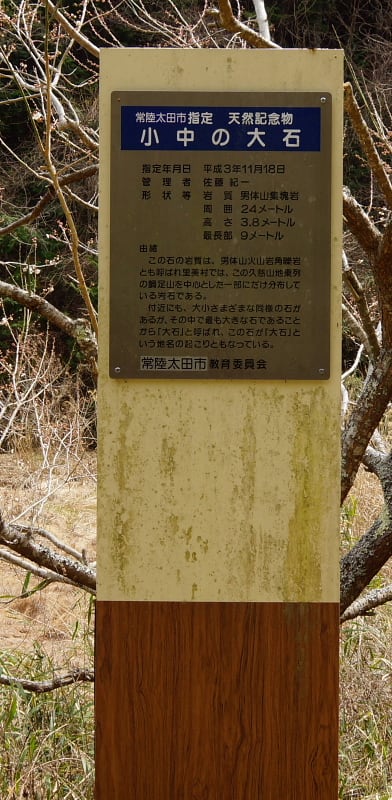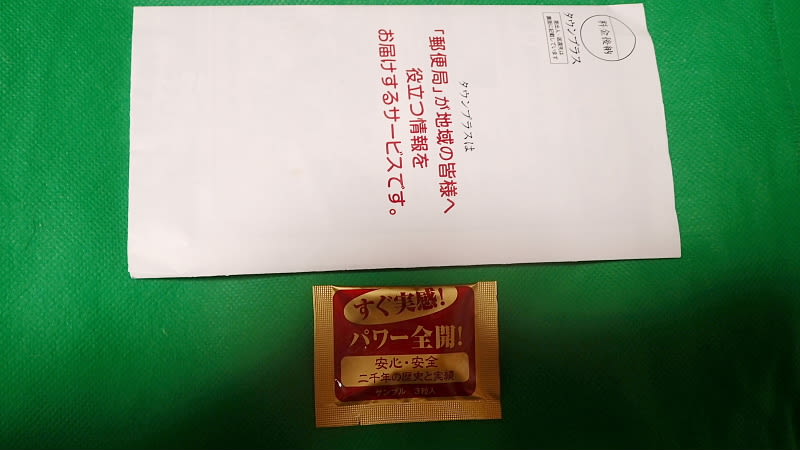小鹿野町両神の節分草自生地に咲く突然変異の節分草
今まで全く見たこともないような突然変異だった。
しべが葉っぱのように変化している異形の節分草
葉というより花弁状というほうがいいかも。
自生地の真ん中に咲いていたので、マクロ撮影ができなかった
のが残念 福島の浄土平の桶沼で見た根本シャクナゲを
彷彿とさせるタイプだ。

上の写真の節分草は、この写真のように二株並んで咲いていた
そのうちの右の株をトリミングしたのが上の写真である。
花友からメールが来たのは二日前だった。
秩父の両神の節分草が、まだ見頃が続いているから見に行きませんか
Kさんが運転する車で行くという。
土曜日は私の予定が入っていたので、日曜日しか行けないと断ったら
それじゃ日曜日に行きましょうということになって、はるばると秩父
まで出かけて行った。。
4時間近くかかって秩父についたのは11時ごろだった。
幸い天気予報は一日晴れの見込みで、絶好の花見日和である。
300円の入場料を払って、自生地に入ると、KさんとIさんが例によって
変わり種の節分草を探してくれる。
今年は、なぜか突然変異した花が沢山生えていた。
真っ先に見つけたのが、一本の茎に花が二輪ついている二輪草のような
節分草だった。
後でKさんに聞いたら、10本以上はあったよという。

背中合わせで二輪が咲く節分草、葉っぱも二輪分ついている?

同じく二輪だが、片方がいじけている花
こういった変わり種の節分草は、しべの色がぬけていたり、茎の色が
薄緑だったりするので、よく見てみると実に多彩である。

茎と葉がうす緑いろ、周りに同じような葉が生えていたから
来年はもっと見られるかもしれない。しべにも注目ね


これは奥の株が二輪咲き

ガク片が離れ離れで茎と葉の色にも注目

おまけはアルビノといわれる緑色の座禅草までが生えていた。
これは変わり種の節分草を紹介した女性の方が、わざわざ
教えてくださった。感謝。お礼のつもりだったのかもしれない。
緑色の座禅草をアルビノと解説しているのは、土井信夫さんが
「月山の花」の中で、緑色の座禅草のことを「まれに苞が緑色の
アルビノ(白化型)がある」と書かれているのを採用した。
山と渓谷の「山に咲く花」2003年版では、
アオザゼンソウと
かかれている事を付記する。
入口の近くには、アズマイチゲも数株生えていたが、まだつぼみだった。
節分草の解説は、リンクしているブログ「花と低山を目指して」の
3月2日の記事をご覧ください。
======================================================================
補足説明
最初の写真で、根本シャクナゲを彷彿とさせると書いたのは
ネモトシャクナゲと呼ばれるシャクナゲは、ハクサンシャクナゲの
雄しべなどが花弁化し、互いにつながって花弁状になり、八重
咲きになったものである。
ゆえに別名ヤエハクサンシャクナゲと呼ばれる。
なお蛇足で付け加えると、福島の吾妻山がこの花の最初の発見地で
1904年中原源治氏の採集した標本により、牧野富太郎博士が
命名した。
和名の「根本石楠花」は、中原源治氏の師であり、福島師範の教授で
あった根本莞爾氏の名前を記念して名づけられたといいます。
1913年(大正2年今から102年前)国指定の天然記念物
1954年(昭和29年今から61年前)には福島県の県花に選ばれた。
見頃は7月中旬が最も良いという。
分布は吾妻山、安達太良山、鳥海山
======================================================================

一面雪が降ったような白さ、、、とHPにかかれているように
花の密度が高い

この自生地の周回路は、自生地のほんの一部で、山の斜面全体に
自生地が広がっている。
日本有数の自生地とか言われるのも納得する広さだ。