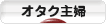『トーマの心臓』 森博嗣 著 (萩尾望都 原作) メディアファクトリー
全編静謐な空気が流れている小説でした。
もちろん自分は小学生の時から萩尾望都にドップリ浸かってる口です。
『ビアンカ』辺りから、萩尾作品が載る掲載誌で読んでいました。
実家には当時の掲載誌の萩尾望都の部分だけを集め、表紙を作り
和とじにした“萩尾望都マイコレクション”が本棚の上の方に並べてあります。
(広い書庫が持てる身であるなら、掲載雑誌をそのまま取っておいた事でしょう)
さらに同じ作品の単行本も段ボールにぎっしり入ってます。
それらを手元に置きたいのは山々何ですが、住宅事情で許されません。
実家に帰る度に眺めてます。
それぐらい好きな萩尾作品の森博嗣による小説化。
読むのをちょっと躊躇いましたが、この表紙です。
日本人設定になっていたのには驚きましたが、
この静かな空気は、書生さんと呼ばれる人間が
実際生きていた時代を彷彿とさせることになりました。
また、原作の少年たちの年齢より若干上に設定されてるようですし、
同級生とのドタバタ部分も殆ど無いため、
さらに空気が研ぎ澄まされていくような印象を受けました。
ただ、トーマ、ユーリ、エーリク・・・日本人なのに名前をそのままにするため
教授がつける渾名という事になっているのが少し違和感。
読み進んでいくと忘れますけどね。頭の中では望都の画が動きます。
最初から最後までオスカーの視点で書かれています。
そして彼はユーリの身に起きた上級生との事件を知らない、
知らないけれど、ユーリの変化には気が付いているという設定で進みます。
原作ではユーリの苦悩を中心にトーマ、エーリク、と話が絡み合い
エーリクの心の変遷とともに、それぞれが少しずつ成長していくように
見えますが、この小説はオスカーの内面を丁寧に追っているようでうす。
このオスカーというキャラクターは当時、萩尾望都のいろんな作品に
登場していた記憶があります。主人公や主な登場人物より少し年上の
彼らより少し世間というものを知っている存在として。
そのため、常にオスカー自身の心模様が前面に出ることはなく、
カッコよくシブイ兄さんはどのように出来上がったのかと。
(オスカーが主人公の話はたぶん『花嫁をひろった男』だったと思います。)
この小説でオスカーが少し見えたような気がしました。
原作と同じストーリーですが自分は全く別物として楽しみました。
読んでいる間は、周りの雑音が遠のく感覚を味わえました。
最後は哀しくはないけれど、少しだけ泣けました。
初版購入特典 応募者全プレ
萩尾望都描き下ろしイラスト入り『トーマの心臓』特製ポストカード3枚セット
いつ届くのかなぁ