2014年3月3日月曜日発行の日本経済新聞紙朝刊の中面に「国立大法人化10年 改革の行方(中)」という解説が載っていたので、拝読しました。
この第2回目の筆者は、2004年4月の国立大学法人化の議論を進めた当時の国立大学協会副会長だった、元一橋大学学長の石弘光さんです。積極的に推進派した方です。
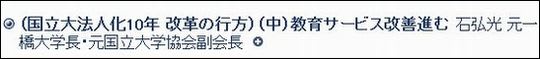
来月2014年4月は国立大学が国立大学法人という独立行政法人になって丸10年目になるため、国立大学法人化とは何だったかというの議論が盛んになっています。
当時、議論を進めた国立大学協会の主要メンバーとしては、文部科学省傘下の一出先に過ぎなかった国立大学に独立した法人格を与えて「民間的な発想で国立大学を経営させることと、大学(学長)の裁量権を大幅に拡大し、研究と教育の質を高めることを目指した」と説明します。
独立した経営主体として「市場と競争に常に向き合うことによって」大学の活性化と個性化を図る仕組みになると考えたそうです。
国立大学法人化後は「各大学では教育に大きく軸足を移した」と語ります。その証拠に、「現在は講義プランやシラバス(授業・学習計画)が事前に学生に提示され、学生による授業評価も始まり、講義の内容や質が高まった」と分析しています。
このことは、国立大学によっては、国立大学法人化の前から部分的に始まっており、その後も拡充が議論されていたので、国立大学法人化によって普及したといえるのかどうかは疑問です。
石さんは「国立大学法人化によって、主体性の無かった国立大学が社会貢献や地域貢献に精を出し、開かれた大学に脱皮した」と高く評価します。
このことも、以前の国立大学でも、現在の運営費交付金などの予算配分が少なくなれば、自然と社会貢献や地域貢献に精を出すのではないかと感じます。
石さんは、国立大学法人化以降に、大学の経営主体がどの程度機能しているのか分からない点を問題点として指摘します。
もう一つの狙いだった研究水準は、法人化を契機に本当に向上したのかどうか疑問を持っているようです。
現実的には、“研究大学”と呼ばれる競争的研究資金をたくさんもらっている(提案公募に選ばれている)、約20の有名大学と、それ以外の大学(主に地方大学)では予算規模の差が大きくなり、独立国立法人化の評価はかなり分かれることと思います。
この「国立大法人化10年 改革の行方」は毎週月曜日に掲載されるようです。2014年2月24日月曜日発行の日本経済新聞紙朝刊には「国立大法人化10年 改革の行方(上)」が掲載されました。筆者は当時の国立大学協会会長だった、元東京大学学長の佐々木毅さんです。
佐々木さんは運営費交付金が減って、大学の教育現場にしわ寄せが出ているとし、学長の裁量権も広がらなかったと指摘します。結局、何のための法人化だったのかしっかり議論し、目指す方向を提示できなかったとします。
2013年10月に東京大学が開催した「国立大学法人化 10年」のシンポジウムでは、当時関係した各省庁の担当者がパネルディスカッションをしました。国立大学側からの改革ではなく、行政改革の一環として、公務員削減による上からの改革だったと、当時の行政担当者は語りました。日本には改革ができる人が育っているのかという重い課題が突きつけられました。
日本の“知”をつくり出す中核となる大学、その中の主力になるだろう国立大学法人とは何なのか、日本の成長エンジンになれるのかという大きな課題を考え続けることが大切だと考えています。
この第2回目の筆者は、2004年4月の国立大学法人化の議論を進めた当時の国立大学協会副会長だった、元一橋大学学長の石弘光さんです。積極的に推進派した方です。
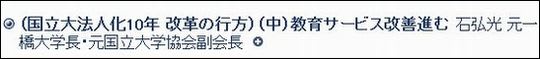
来月2014年4月は国立大学が国立大学法人という独立行政法人になって丸10年目になるため、国立大学法人化とは何だったかというの議論が盛んになっています。
当時、議論を進めた国立大学協会の主要メンバーとしては、文部科学省傘下の一出先に過ぎなかった国立大学に独立した法人格を与えて「民間的な発想で国立大学を経営させることと、大学(学長)の裁量権を大幅に拡大し、研究と教育の質を高めることを目指した」と説明します。
独立した経営主体として「市場と競争に常に向き合うことによって」大学の活性化と個性化を図る仕組みになると考えたそうです。
国立大学法人化後は「各大学では教育に大きく軸足を移した」と語ります。その証拠に、「現在は講義プランやシラバス(授業・学習計画)が事前に学生に提示され、学生による授業評価も始まり、講義の内容や質が高まった」と分析しています。
このことは、国立大学によっては、国立大学法人化の前から部分的に始まっており、その後も拡充が議論されていたので、国立大学法人化によって普及したといえるのかどうかは疑問です。
石さんは「国立大学法人化によって、主体性の無かった国立大学が社会貢献や地域貢献に精を出し、開かれた大学に脱皮した」と高く評価します。
このことも、以前の国立大学でも、現在の運営費交付金などの予算配分が少なくなれば、自然と社会貢献や地域貢献に精を出すのではないかと感じます。
石さんは、国立大学法人化以降に、大学の経営主体がどの程度機能しているのか分からない点を問題点として指摘します。
もう一つの狙いだった研究水準は、法人化を契機に本当に向上したのかどうか疑問を持っているようです。
現実的には、“研究大学”と呼ばれる競争的研究資金をたくさんもらっている(提案公募に選ばれている)、約20の有名大学と、それ以外の大学(主に地方大学)では予算規模の差が大きくなり、独立国立法人化の評価はかなり分かれることと思います。
この「国立大法人化10年 改革の行方」は毎週月曜日に掲載されるようです。2014年2月24日月曜日発行の日本経済新聞紙朝刊には「国立大法人化10年 改革の行方(上)」が掲載されました。筆者は当時の国立大学協会会長だった、元東京大学学長の佐々木毅さんです。
佐々木さんは運営費交付金が減って、大学の教育現場にしわ寄せが出ているとし、学長の裁量権も広がらなかったと指摘します。結局、何のための法人化だったのかしっかり議論し、目指す方向を提示できなかったとします。
2013年10月に東京大学が開催した「国立大学法人化 10年」のシンポジウムでは、当時関係した各省庁の担当者がパネルディスカッションをしました。国立大学側からの改革ではなく、行政改革の一環として、公務員削減による上からの改革だったと、当時の行政担当者は語りました。日本には改革ができる人が育っているのかという重い課題が突きつけられました。
日本の“知”をつくり出す中核となる大学、その中の主力になるだろう国立大学法人とは何なのか、日本の成長エンジンになれるのかという大きな課題を考え続けることが大切だと考えています。









