2014年2月24日発行の日本経済新聞紙夕刊の一面に掲載された、見出し「ネット通販 シニアつかむ」という記事を拝読しました。
Webサイトなどを利用した通信販売の2013年の世帯支出が6万9607円と前年比14パーセント増となったと、総務省の家計消費状態調査の結果として発表されたそうです。
この消費状態調査はWebサイトでの通信販売や大手スーパー各社が展開するいわゆる“ネットスーパー”を通じた買い物の動向調査です。
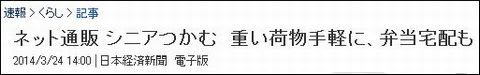
同記事よると、その特徴は中高年層での利用が伸びていることです。伸び率は、50歳代で前年比23パーセント、60歳代で同21パーセント、70歳代で同18パーセントで、いずれも全体の伸びを上回っているとのことです。
例えば、通信販売サイトの「ヤフー ショッピング」では、中高年齢層は家庭菜園で使う野菜の種や、運ぶのに思いフルーツ缶詰などの購入比率が高いそうです。また、セブン-イレブン・ジャパンでは栄養バランスを考えた“日替わり弁当”を宅配する「セブン・ミール」の利用が増えているそうです。高齢化社会のニーズを反映した伸びです。
その一方で、利用金額は40歳代の11万4000円に比べて、60歳代は80パーセント強、60歳代は約50パーセント、70歳代は約20パーセントと、定期収入が減る高齢者はまだあまり購入していません。
ただし、ネット通販での支出傾向を年収別に分析すると、200万円台は44パーセント増、300万円台は17パーセント増と増える傾向にあるそうです。Webサイトは販売価格を明示してあるので、実売価格を比較して安い方を購入する動向があるとのことです。
さらに、高齢者は割れたセンベイなどの“訳あり商品”を購入する傾向が高まっているそうです。ある種の生活防衛術です。
日本政策投資銀行によると、日本は小売りの中でのネット通販の比率が2011年時点で2.8パーセントと、先進国の米国や英国に比べて低く、成長の余地が大きいとの分析です。英国では、ネット通販が10パーセントを超えているネット通販大国です。
日本の高年齢化を部分的に反映して、ネット通販依存度が高まりそうです。逆説的ですが、いわゆる“限界集落”と呼ばれる過疎地の方が、高齢者によるネット通販依存度が高まりそうです。なかなか複雑な動機を感じます。
Webサイトなどを利用した通信販売の2013年の世帯支出が6万9607円と前年比14パーセント増となったと、総務省の家計消費状態調査の結果として発表されたそうです。
この消費状態調査はWebサイトでの通信販売や大手スーパー各社が展開するいわゆる“ネットスーパー”を通じた買い物の動向調査です。
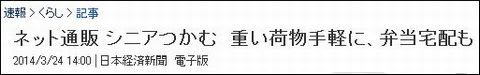
同記事よると、その特徴は中高年層での利用が伸びていることです。伸び率は、50歳代で前年比23パーセント、60歳代で同21パーセント、70歳代で同18パーセントで、いずれも全体の伸びを上回っているとのことです。
例えば、通信販売サイトの「ヤフー ショッピング」では、中高年齢層は家庭菜園で使う野菜の種や、運ぶのに思いフルーツ缶詰などの購入比率が高いそうです。また、セブン-イレブン・ジャパンでは栄養バランスを考えた“日替わり弁当”を宅配する「セブン・ミール」の利用が増えているそうです。高齢化社会のニーズを反映した伸びです。
その一方で、利用金額は40歳代の11万4000円に比べて、60歳代は80パーセント強、60歳代は約50パーセント、70歳代は約20パーセントと、定期収入が減る高齢者はまだあまり購入していません。
ただし、ネット通販での支出傾向を年収別に分析すると、200万円台は44パーセント増、300万円台は17パーセント増と増える傾向にあるそうです。Webサイトは販売価格を明示してあるので、実売価格を比較して安い方を購入する動向があるとのことです。
さらに、高齢者は割れたセンベイなどの“訳あり商品”を購入する傾向が高まっているそうです。ある種の生活防衛術です。
日本政策投資銀行によると、日本は小売りの中でのネット通販の比率が2011年時点で2.8パーセントと、先進国の米国や英国に比べて低く、成長の余地が大きいとの分析です。英国では、ネット通販が10パーセントを超えているネット通販大国です。
日本の高年齢化を部分的に反映して、ネット通販依存度が高まりそうです。逆説的ですが、いわゆる“限界集落”と呼ばれる過疎地の方が、高齢者によるネット通販依存度が高まりそうです。なかなか複雑な動機を感じます。









